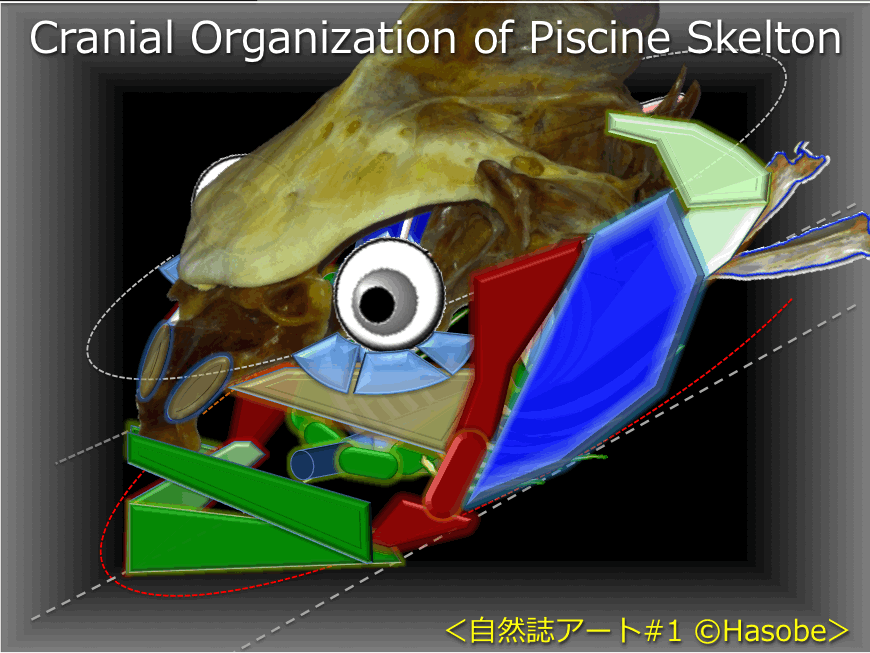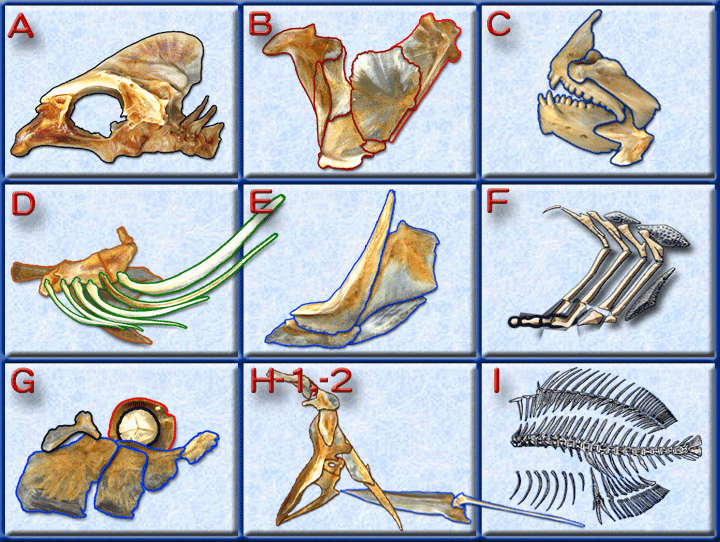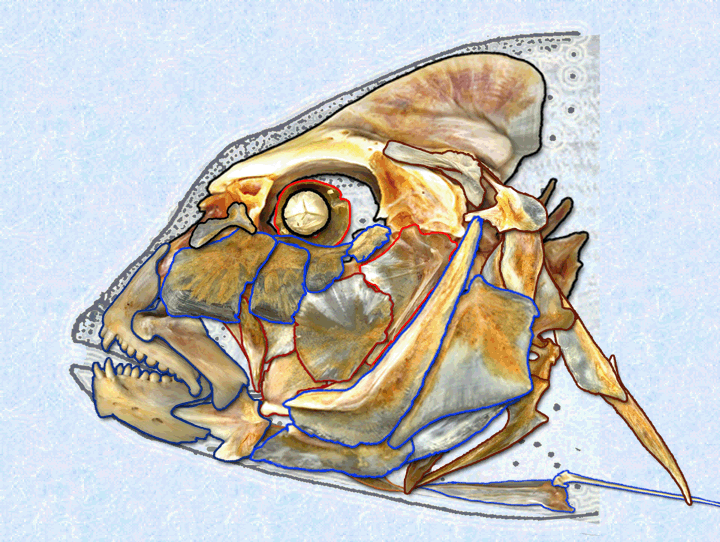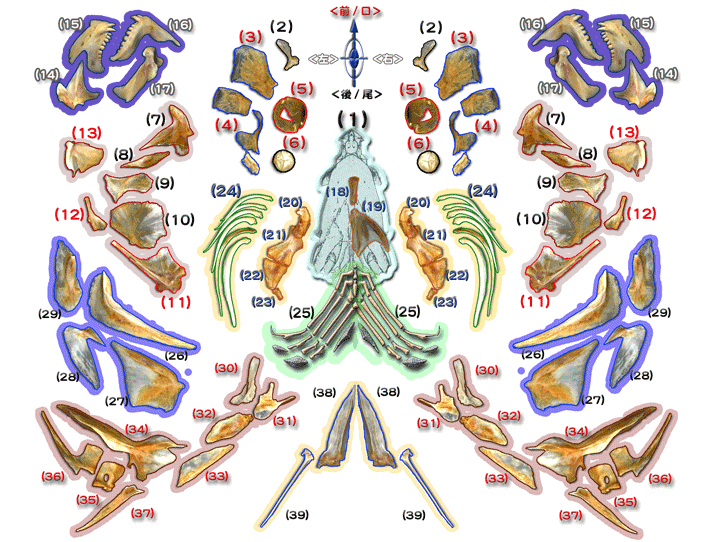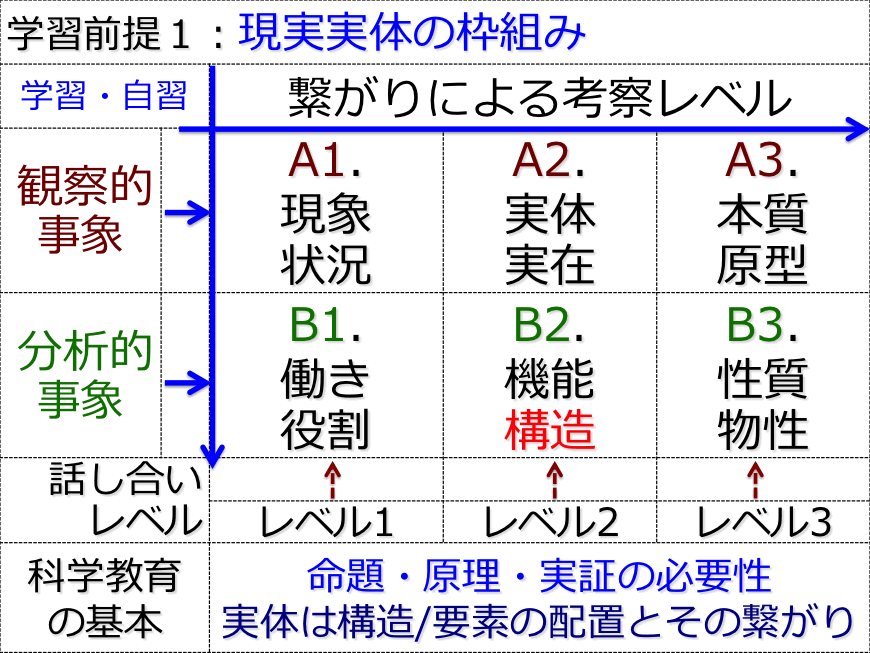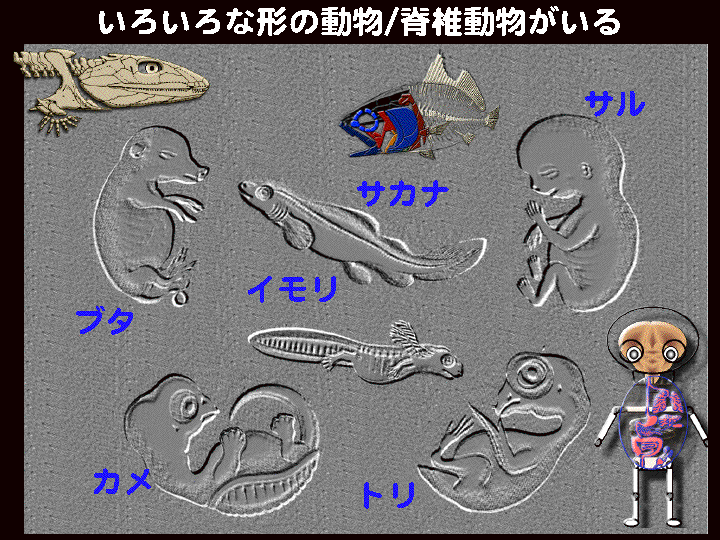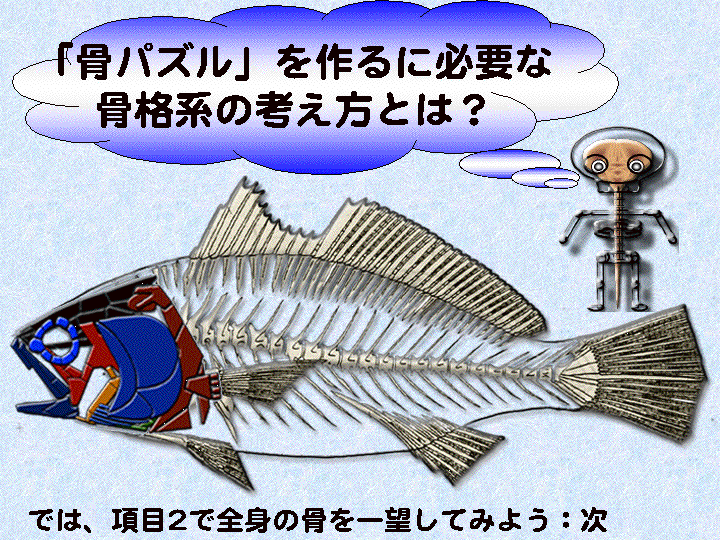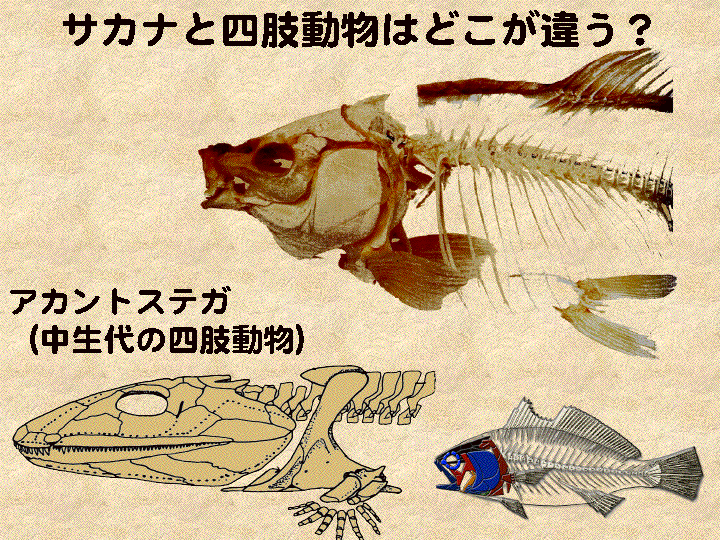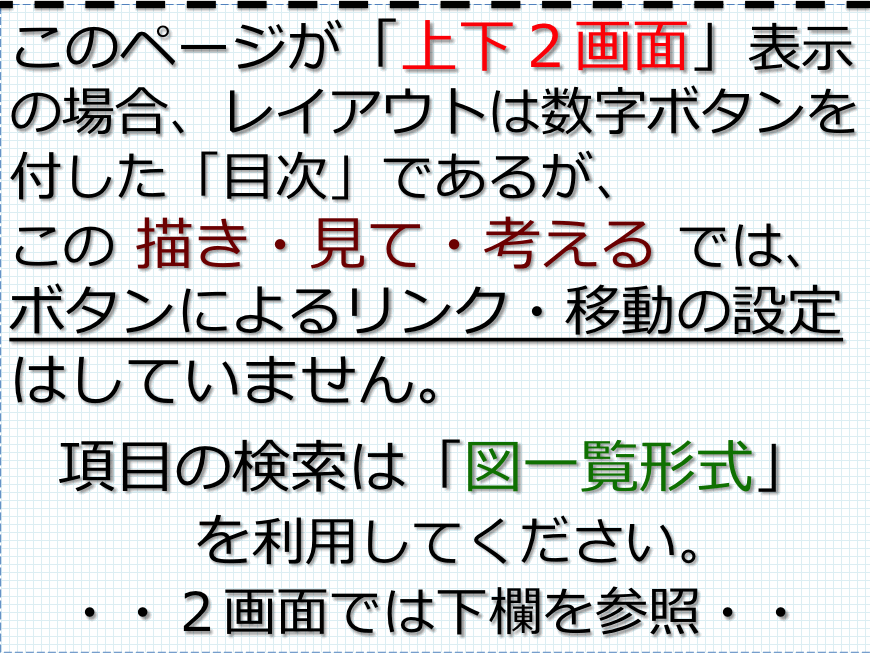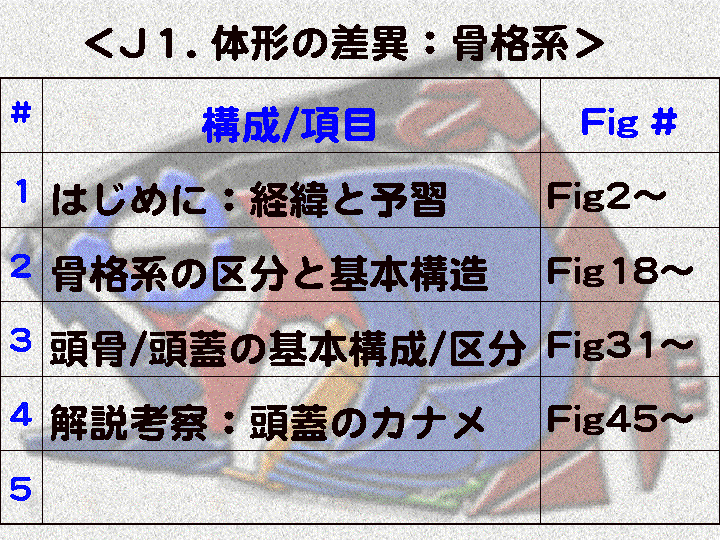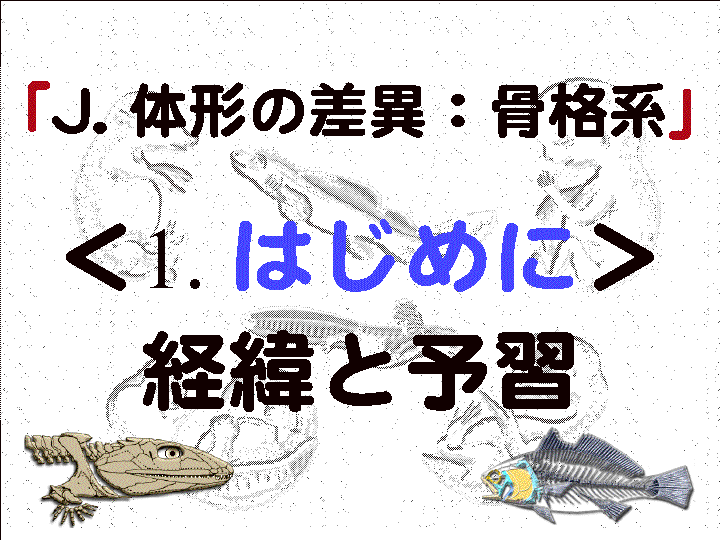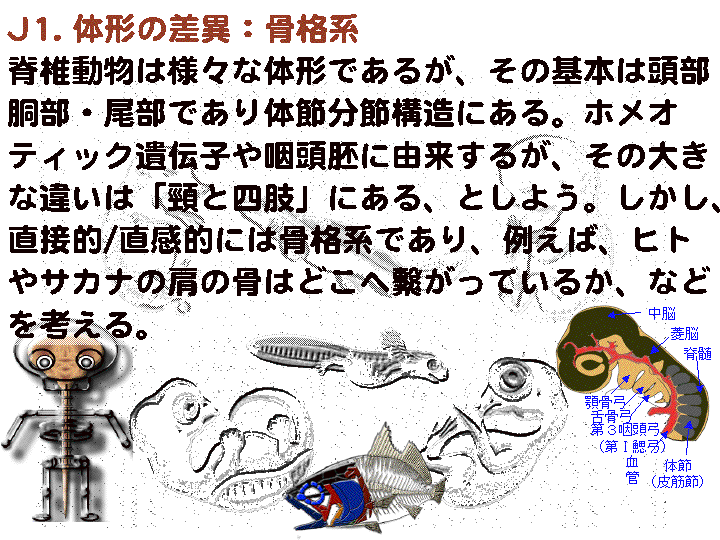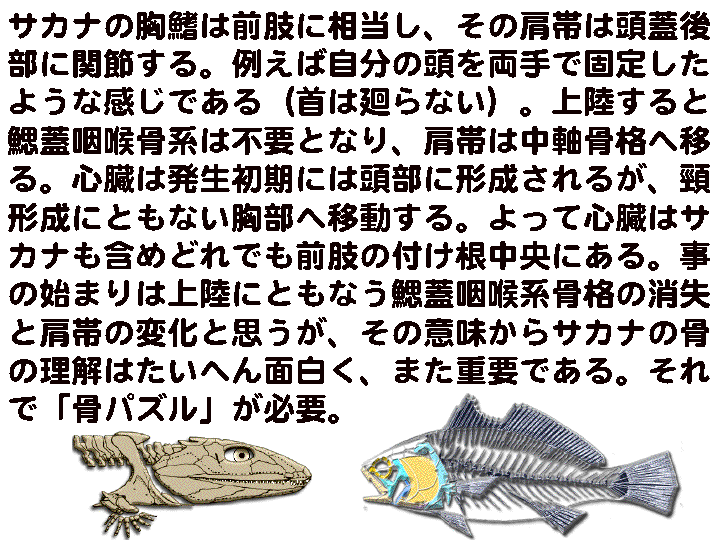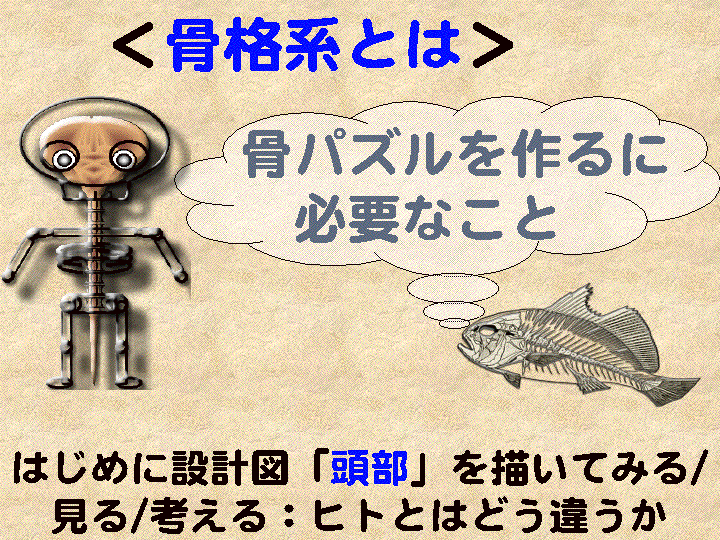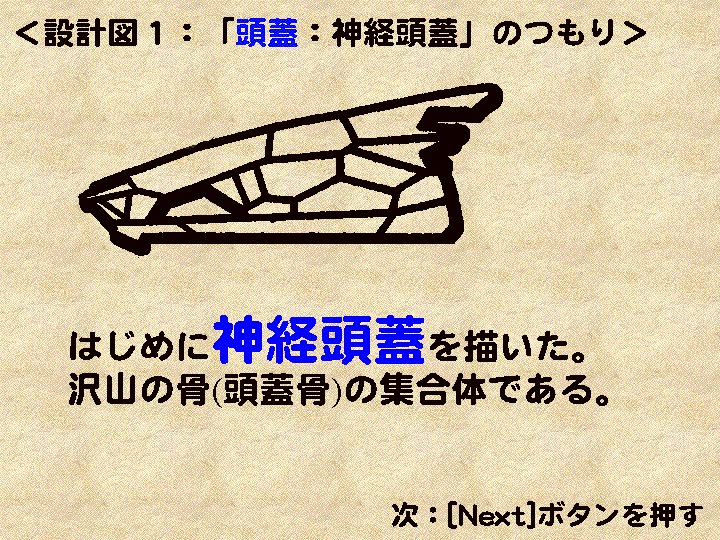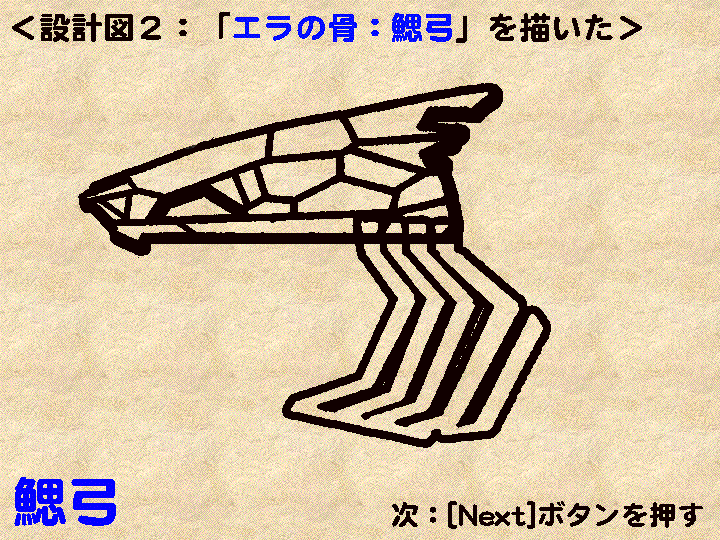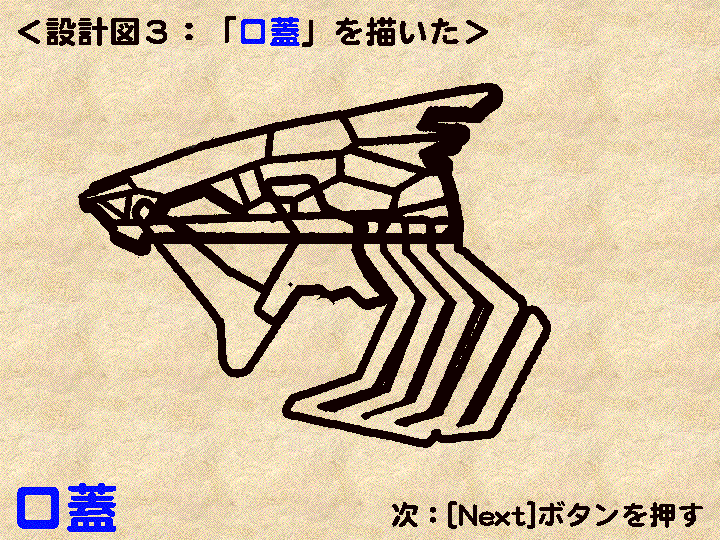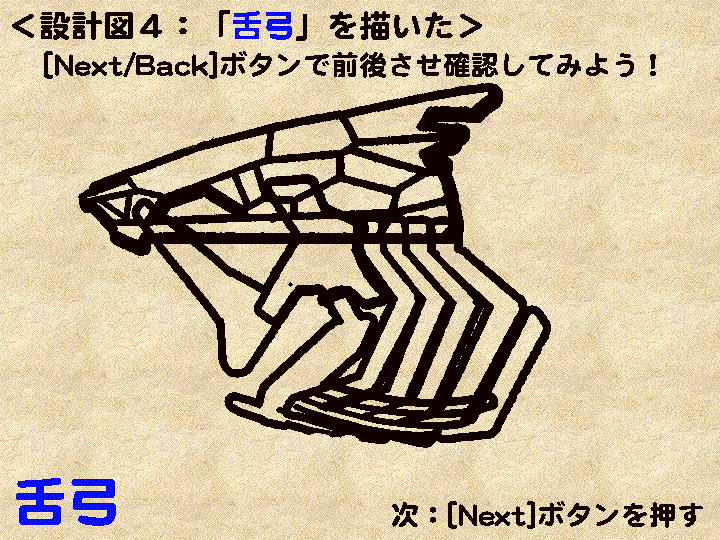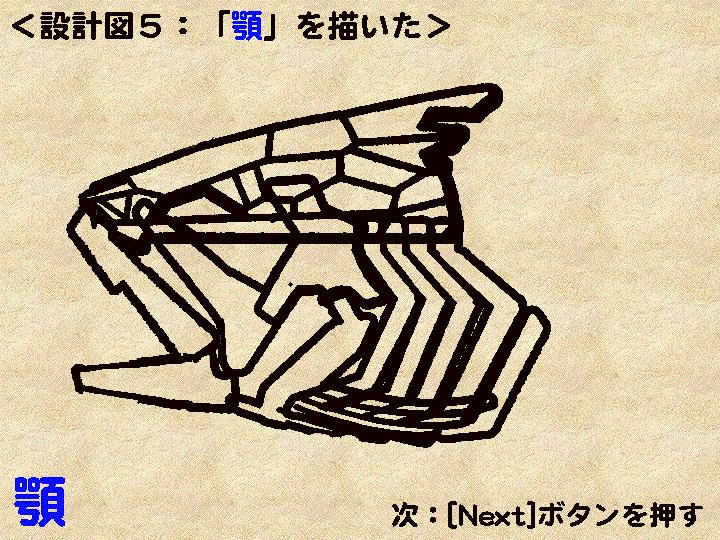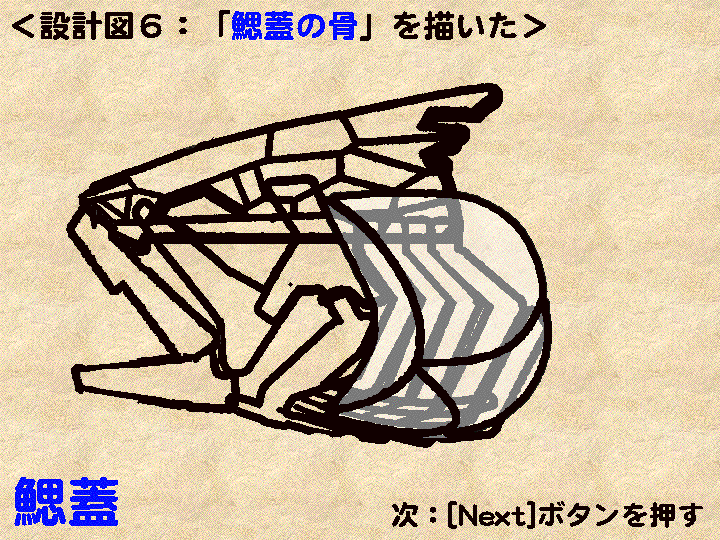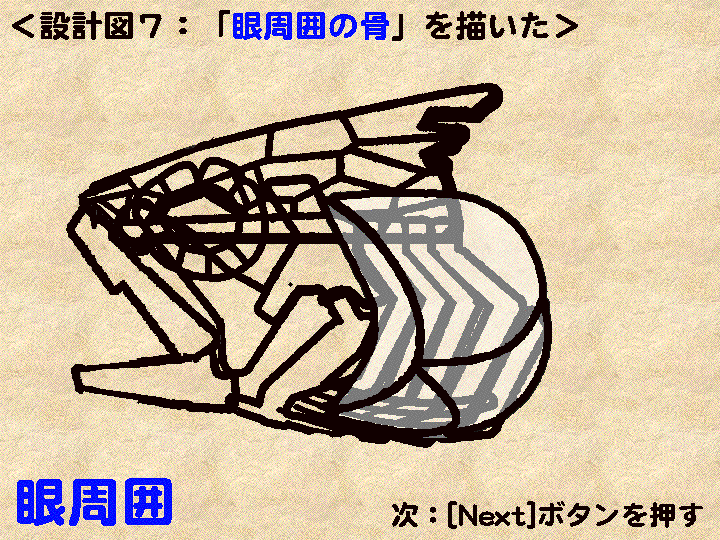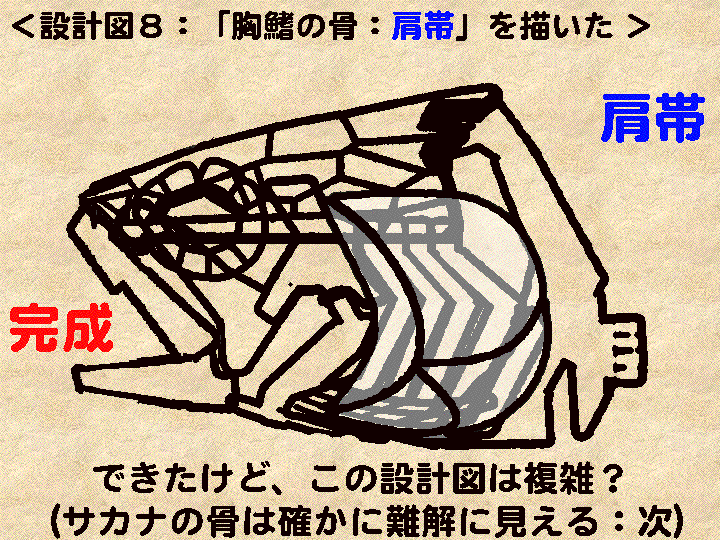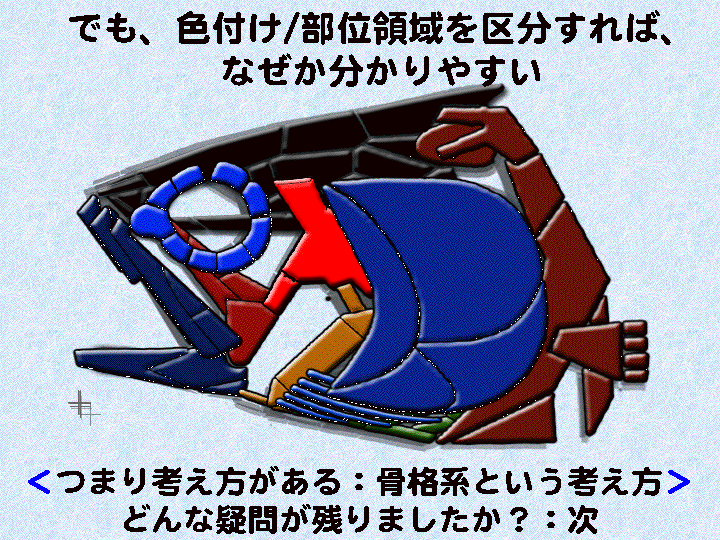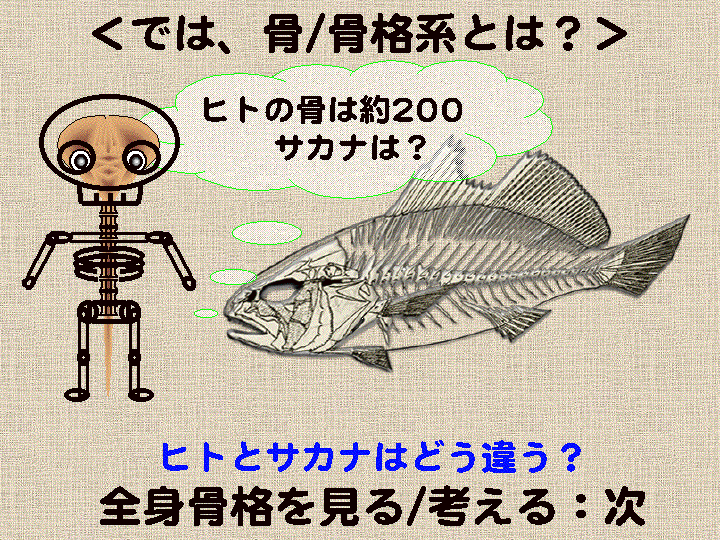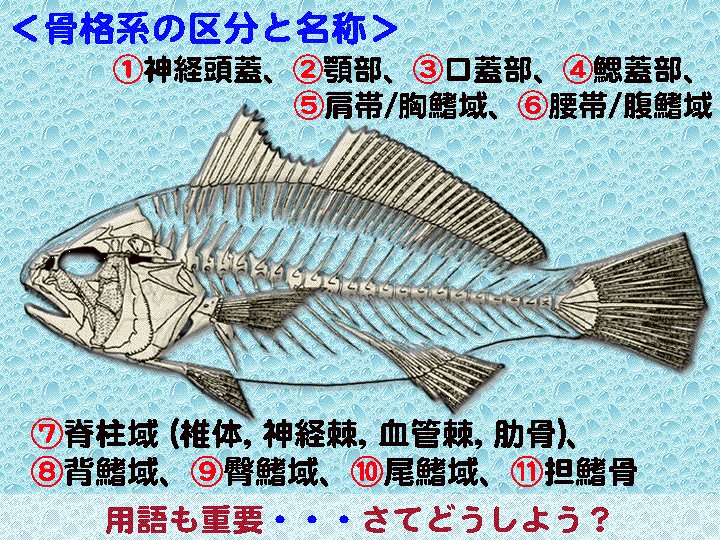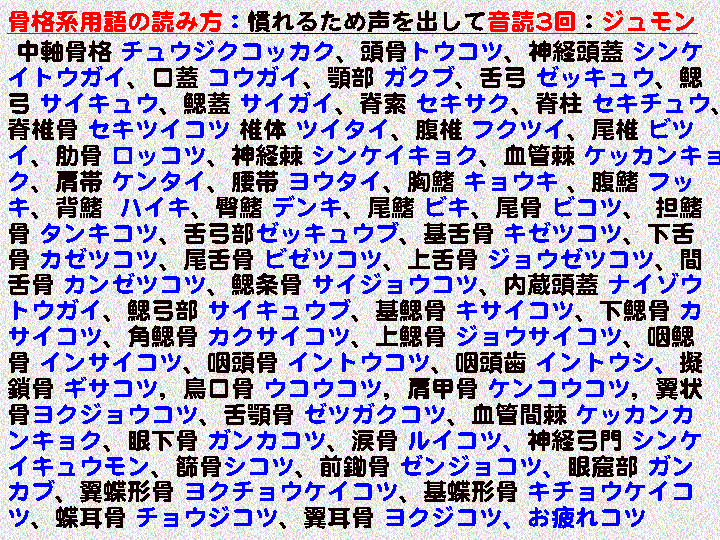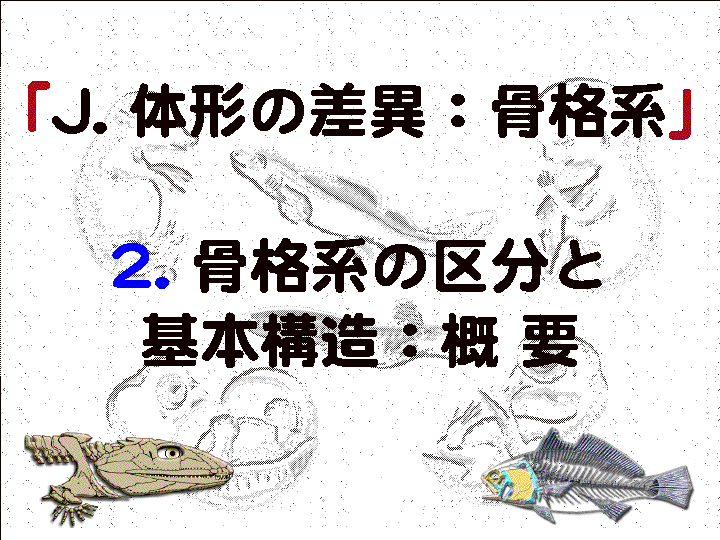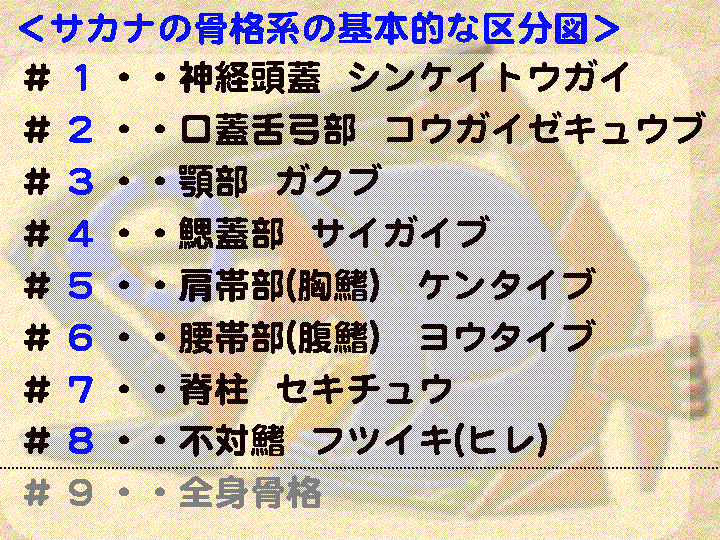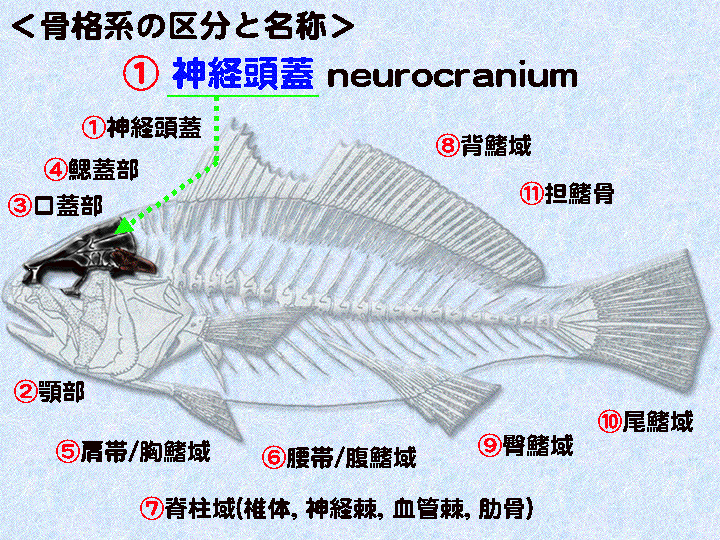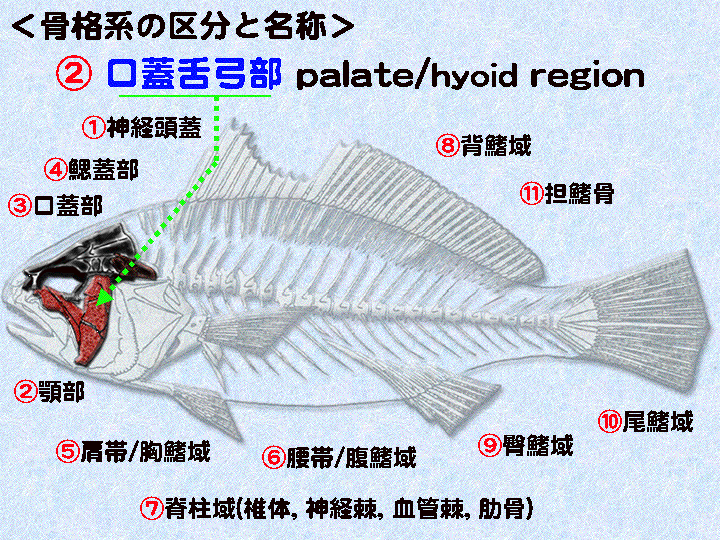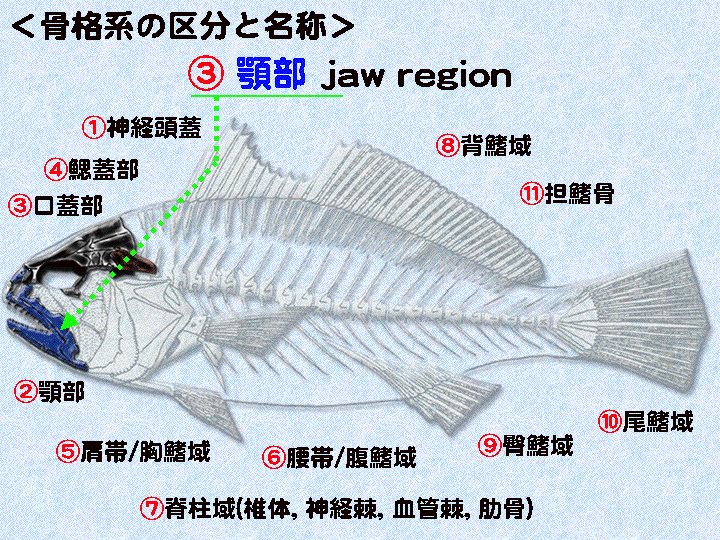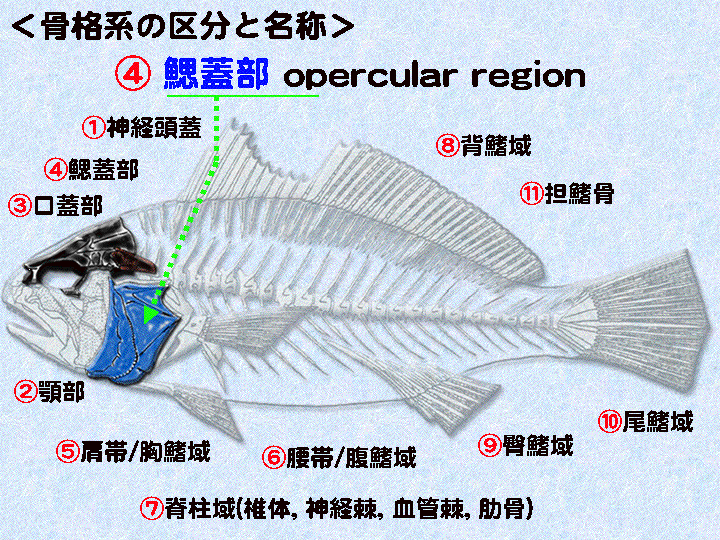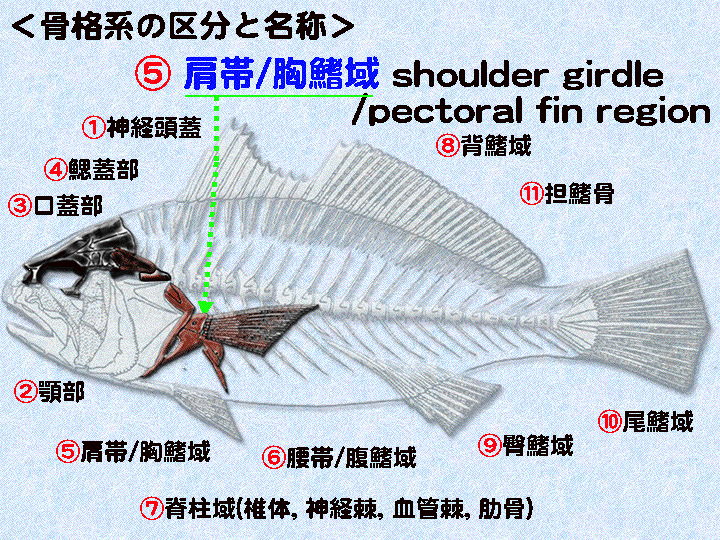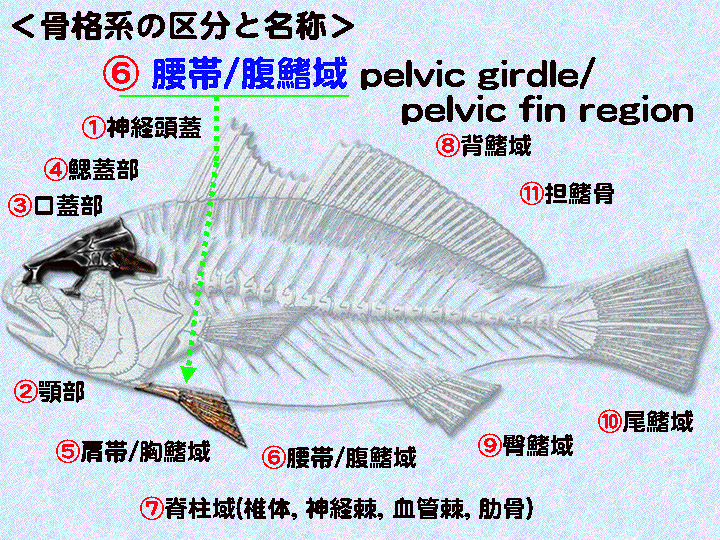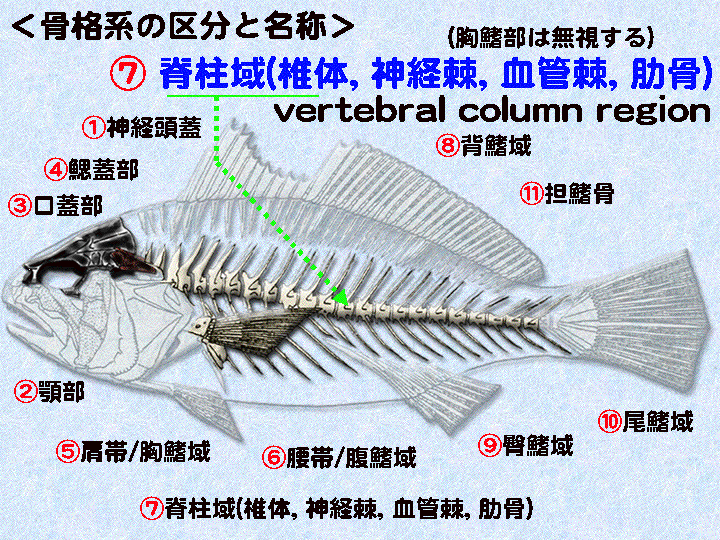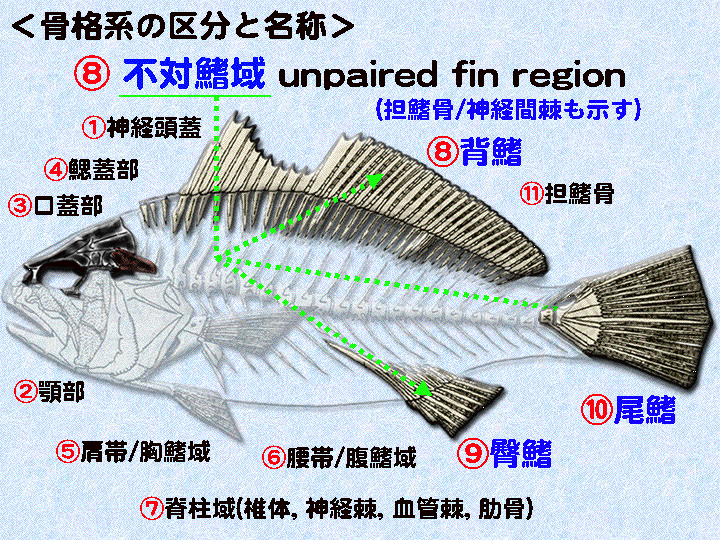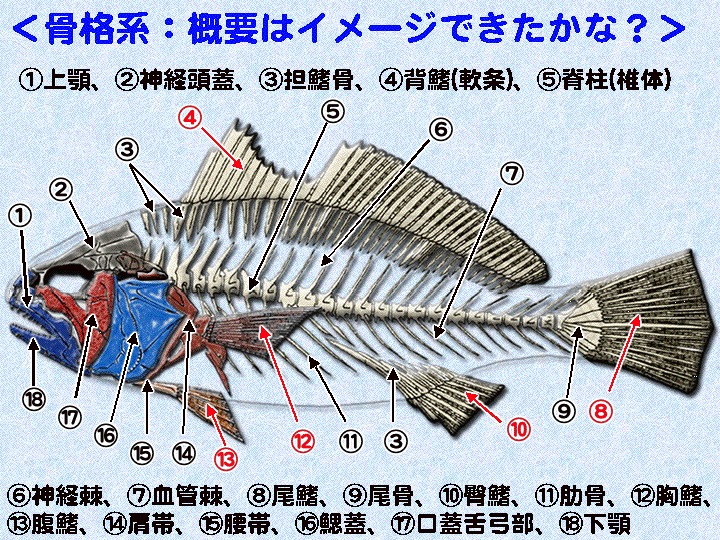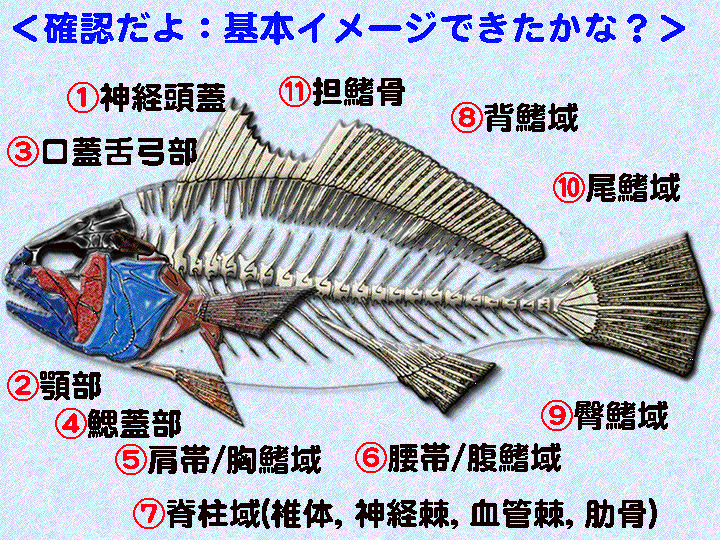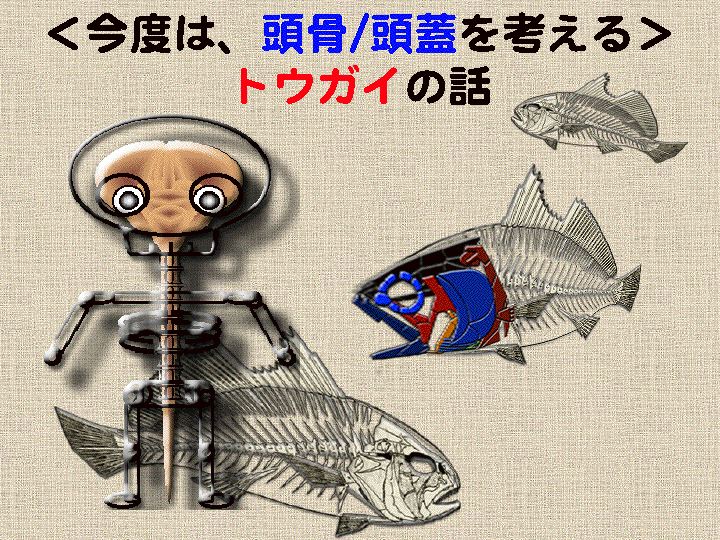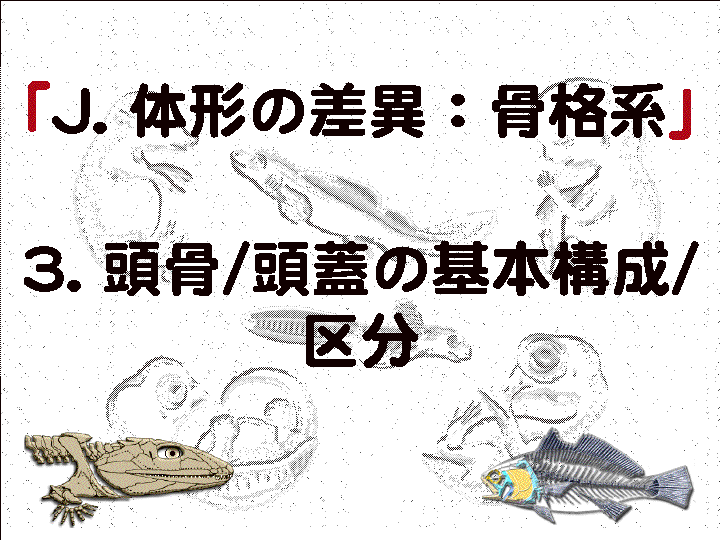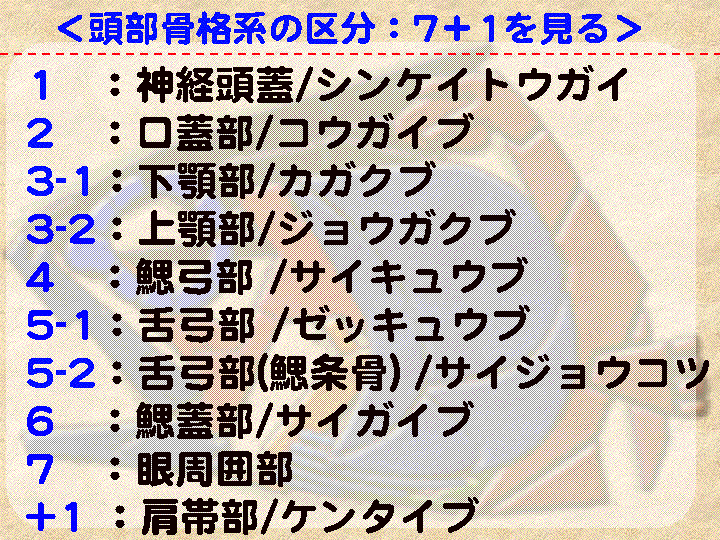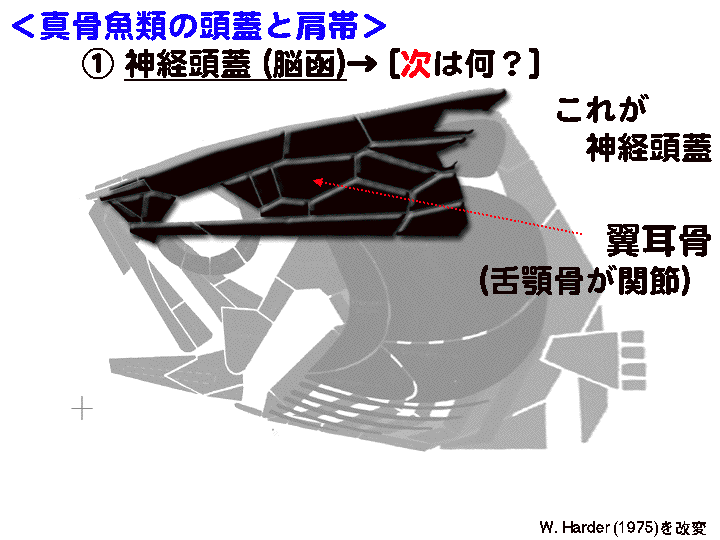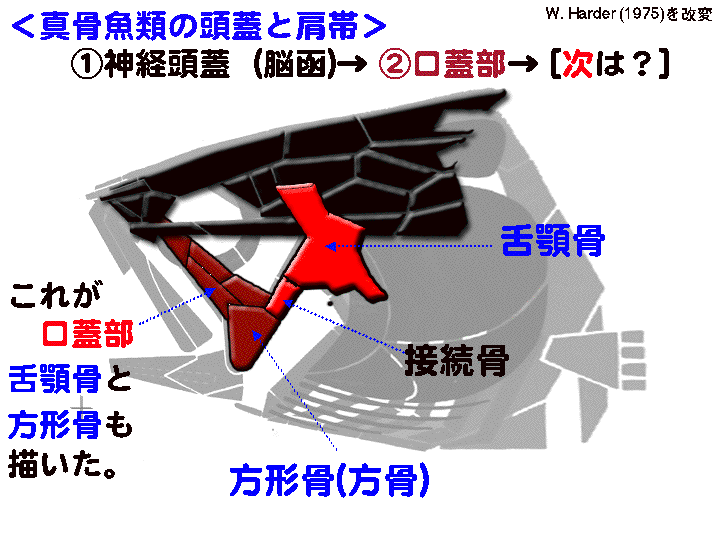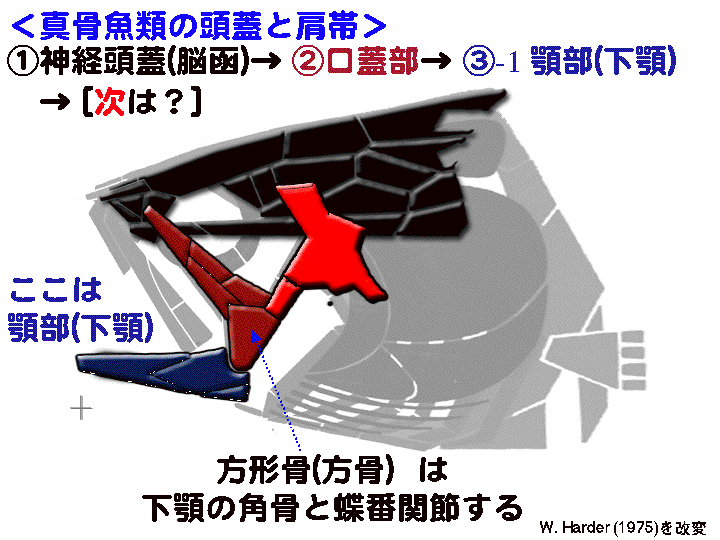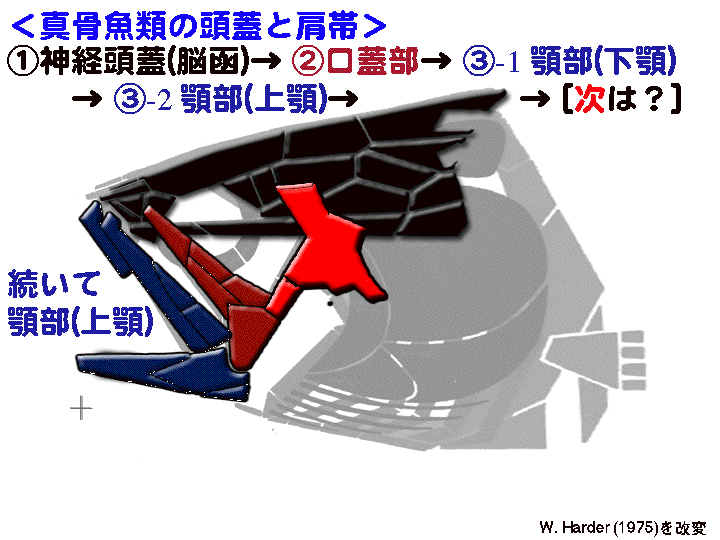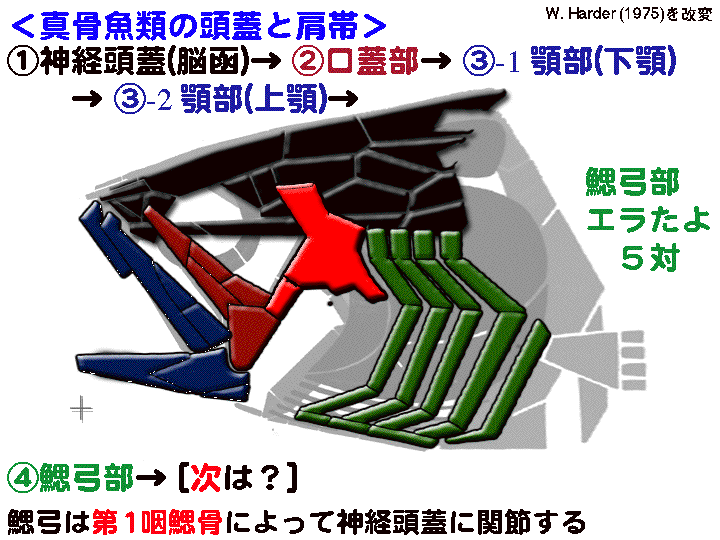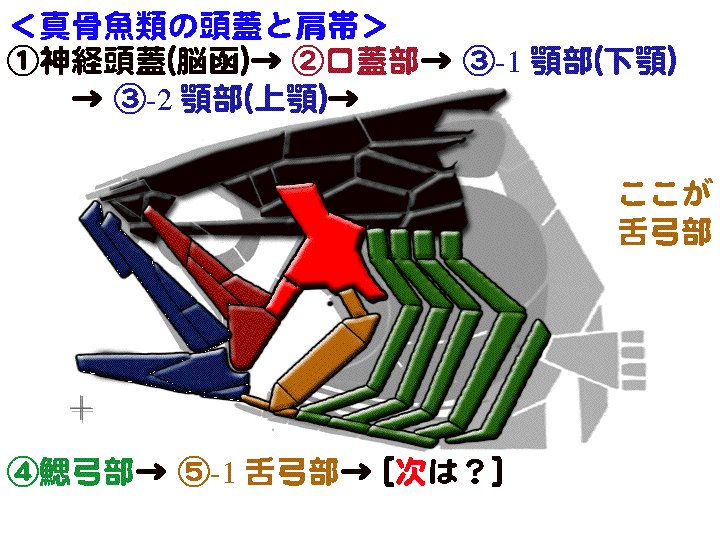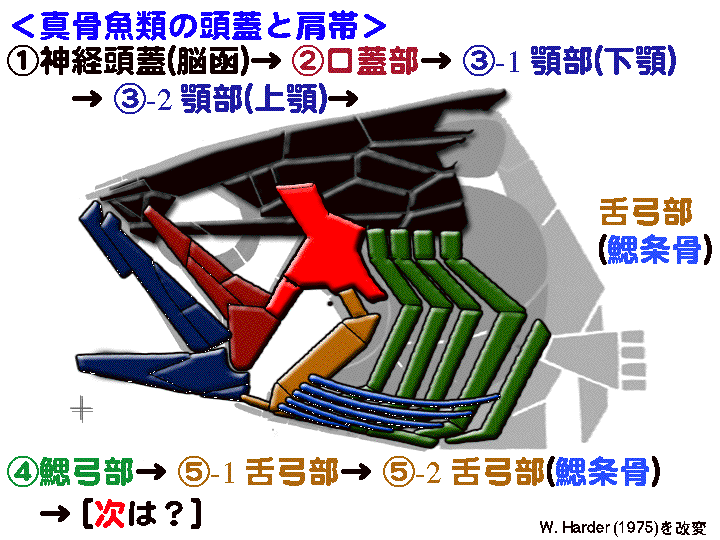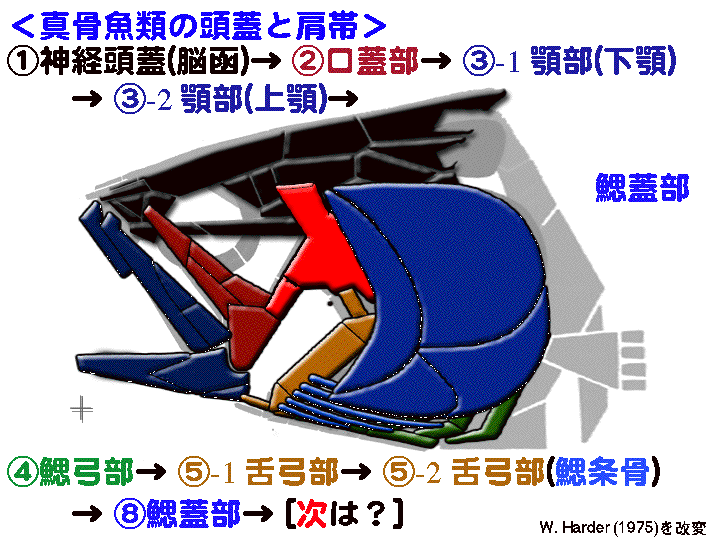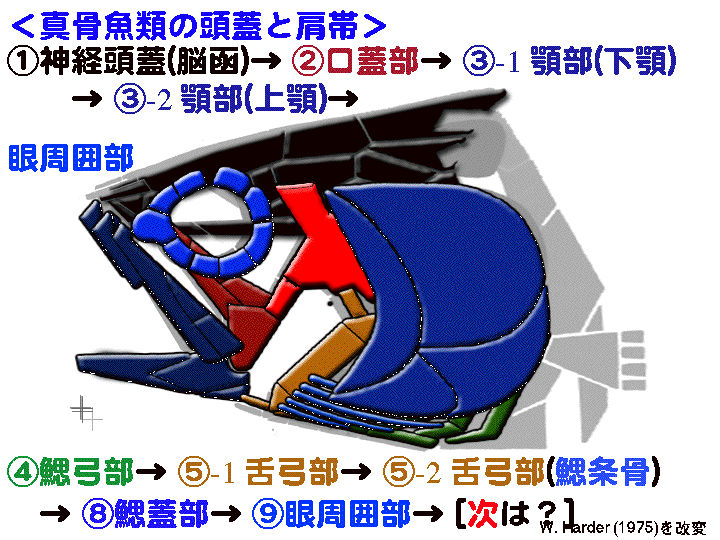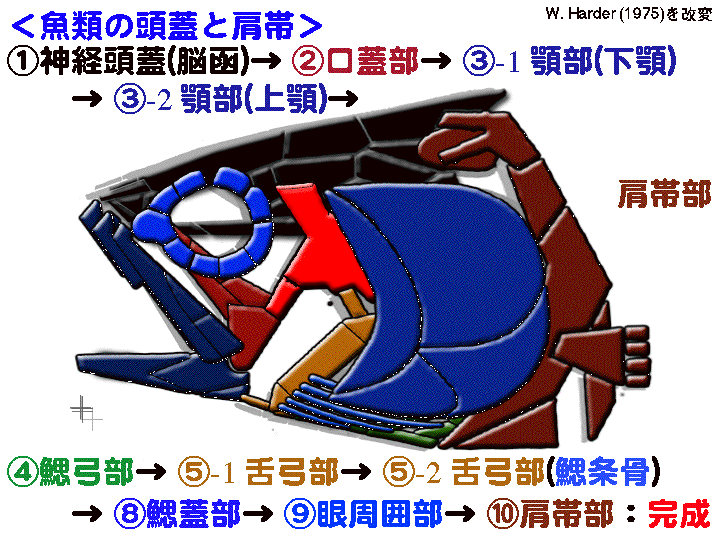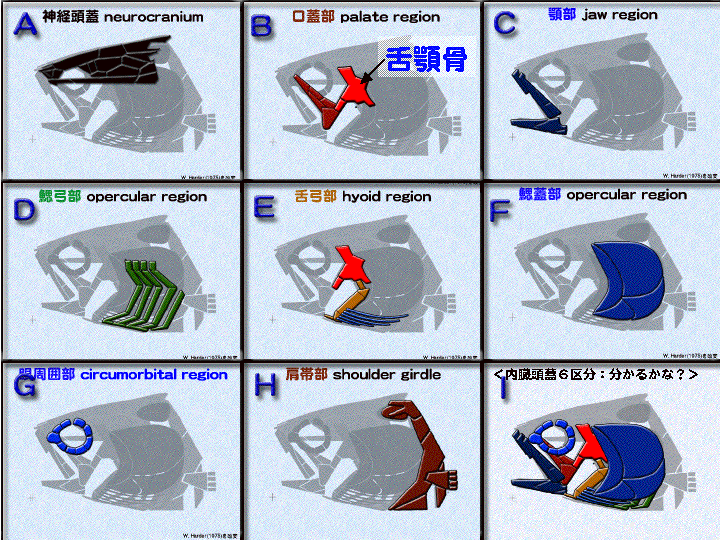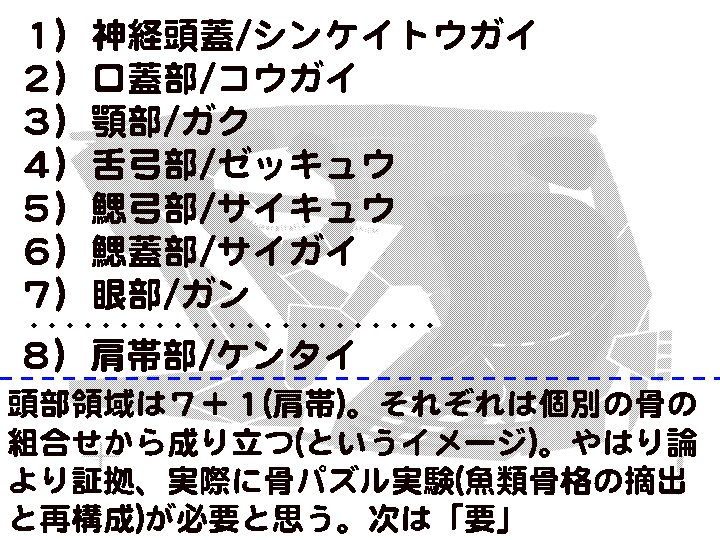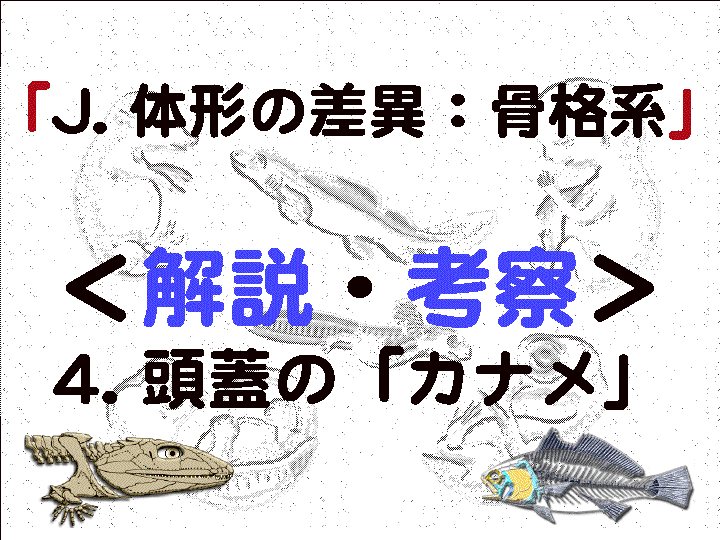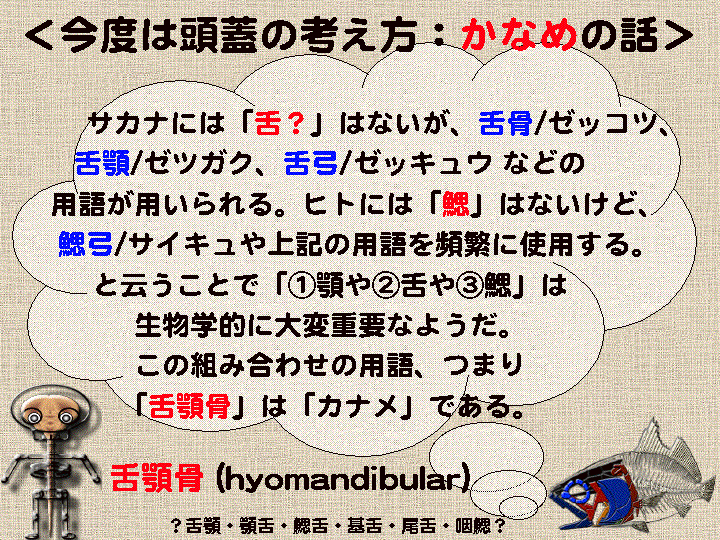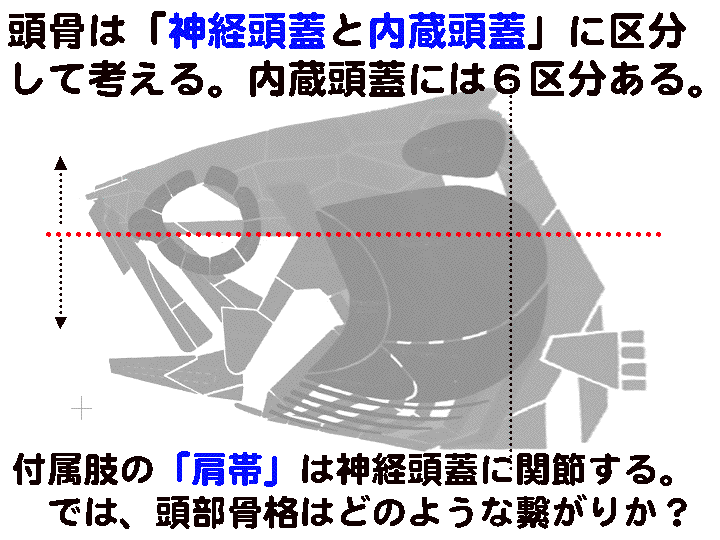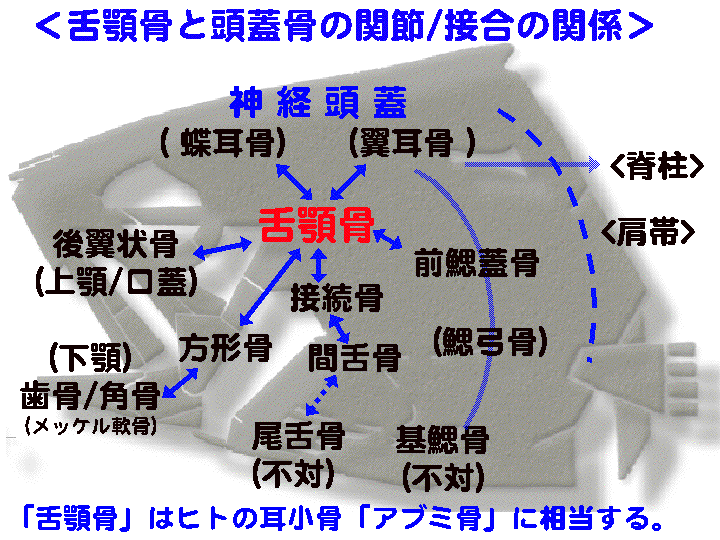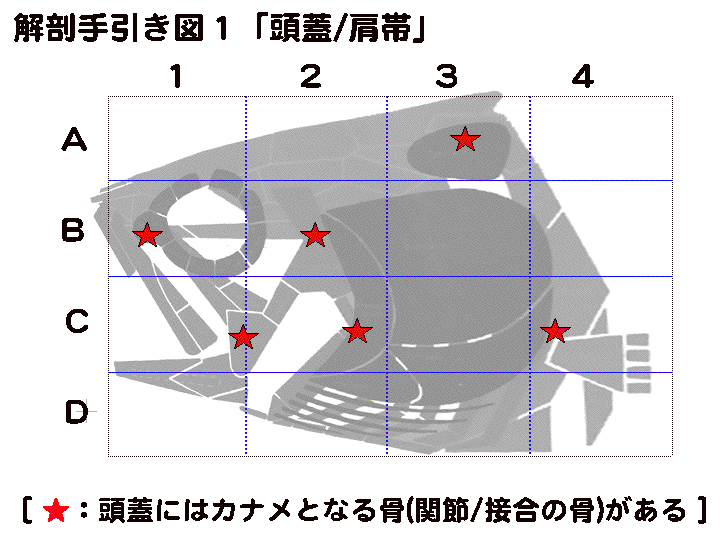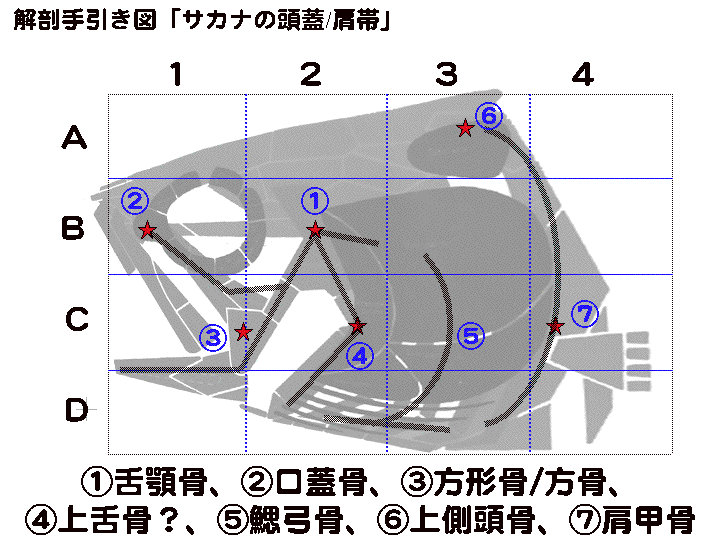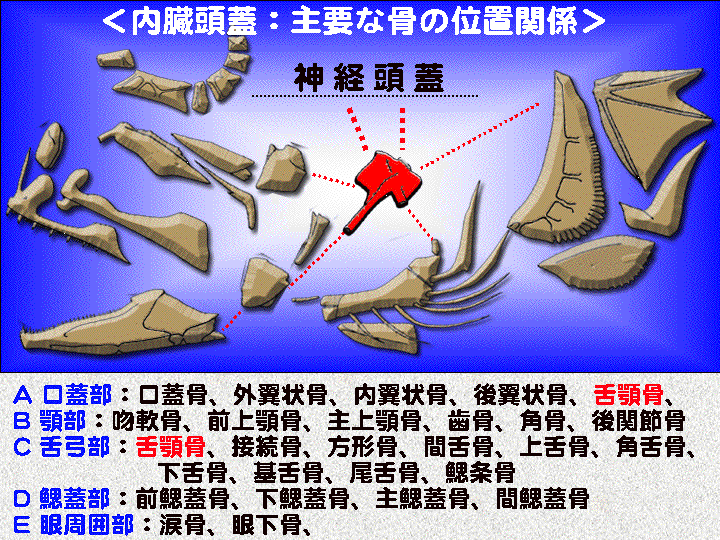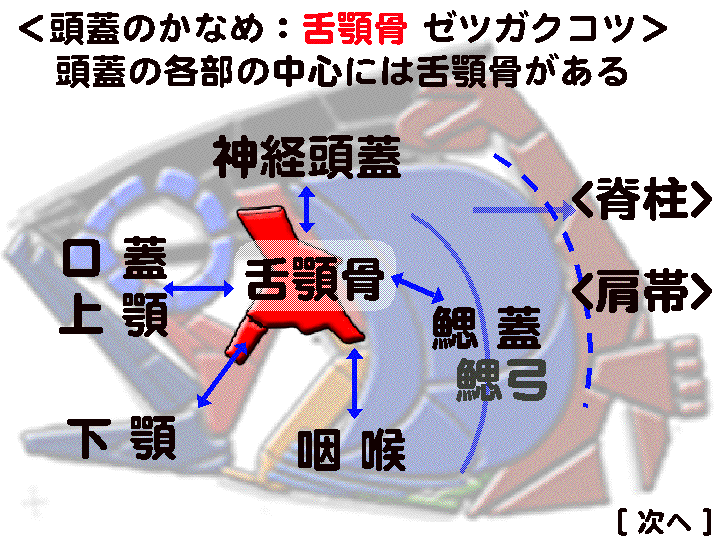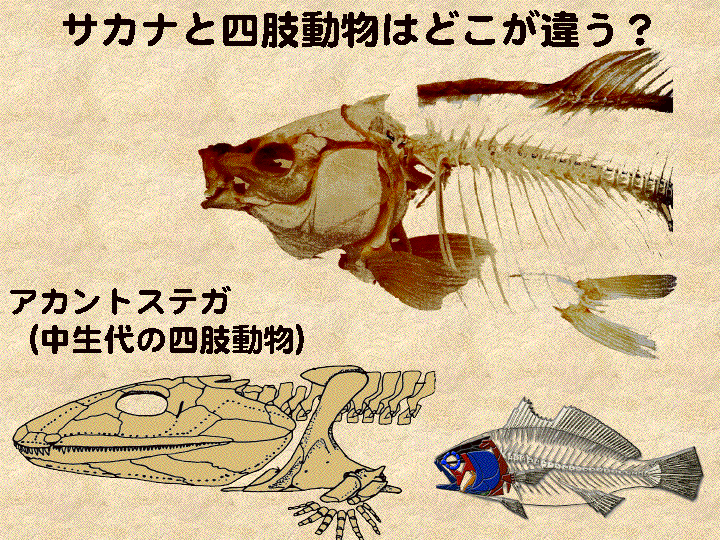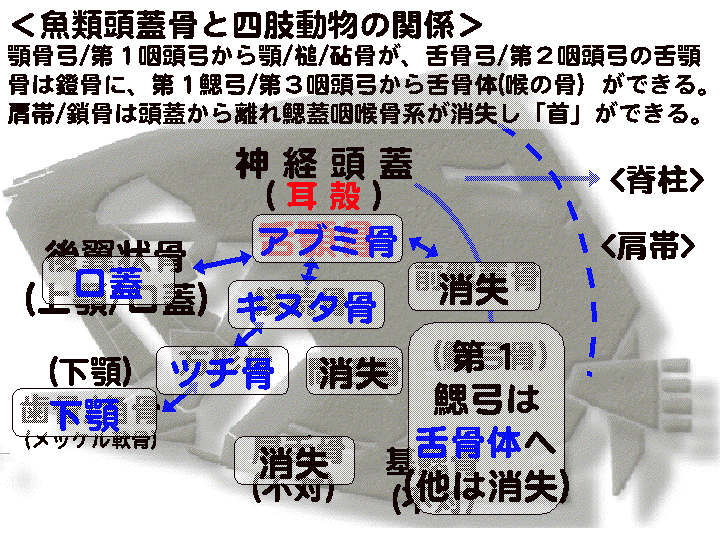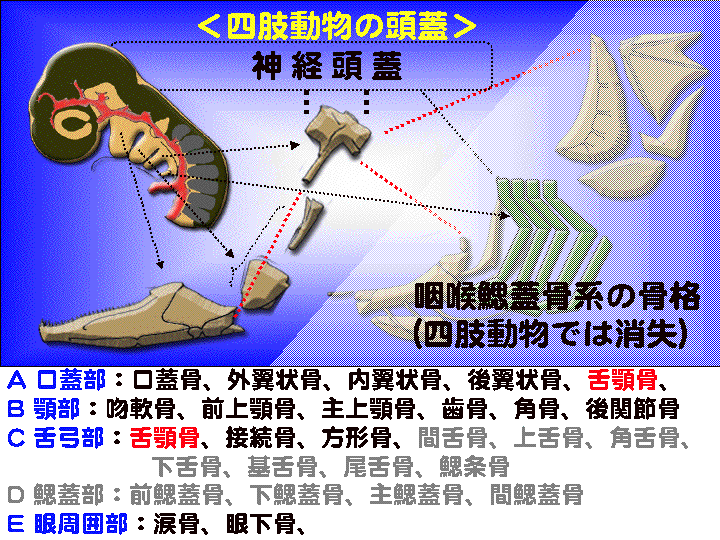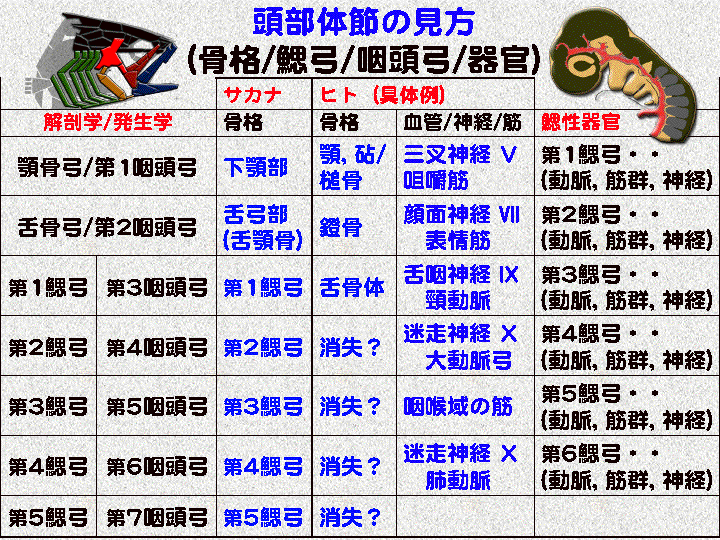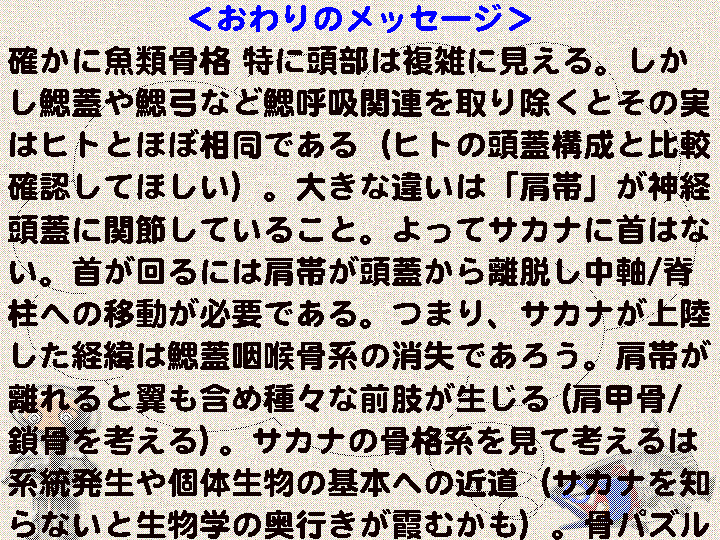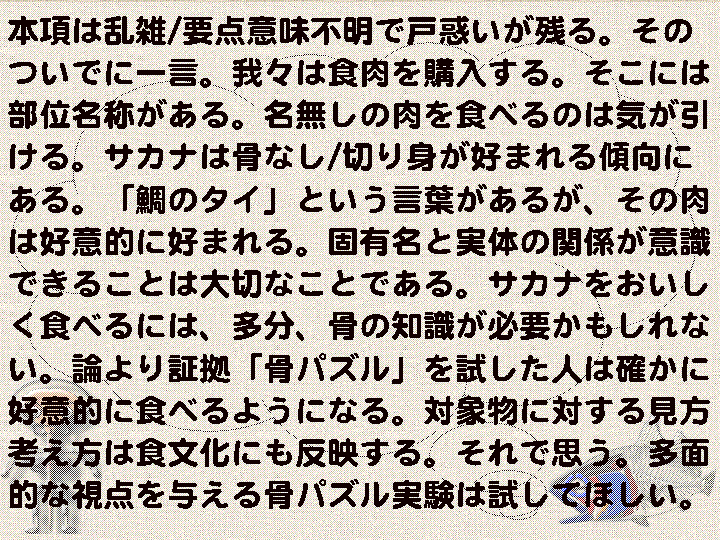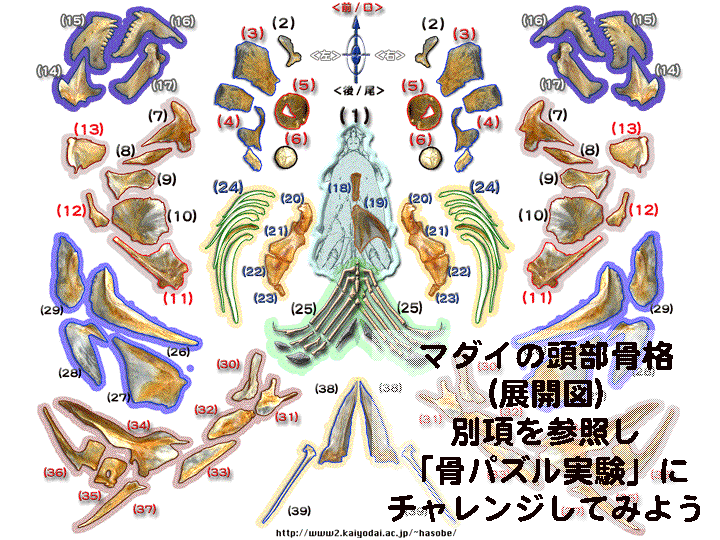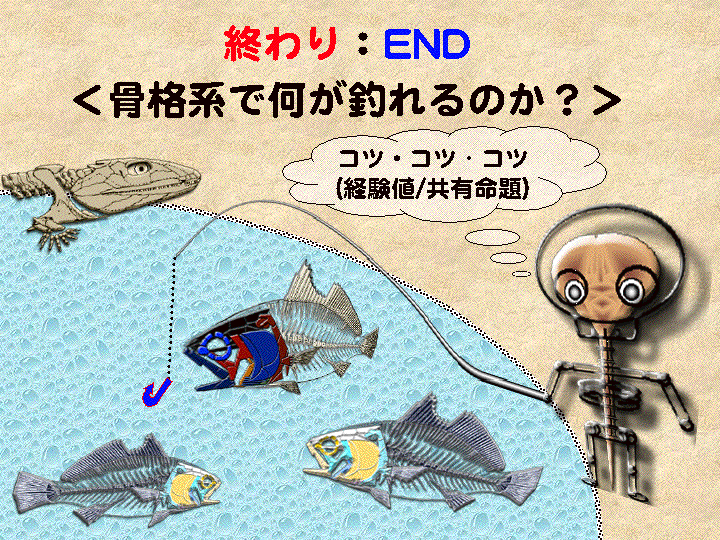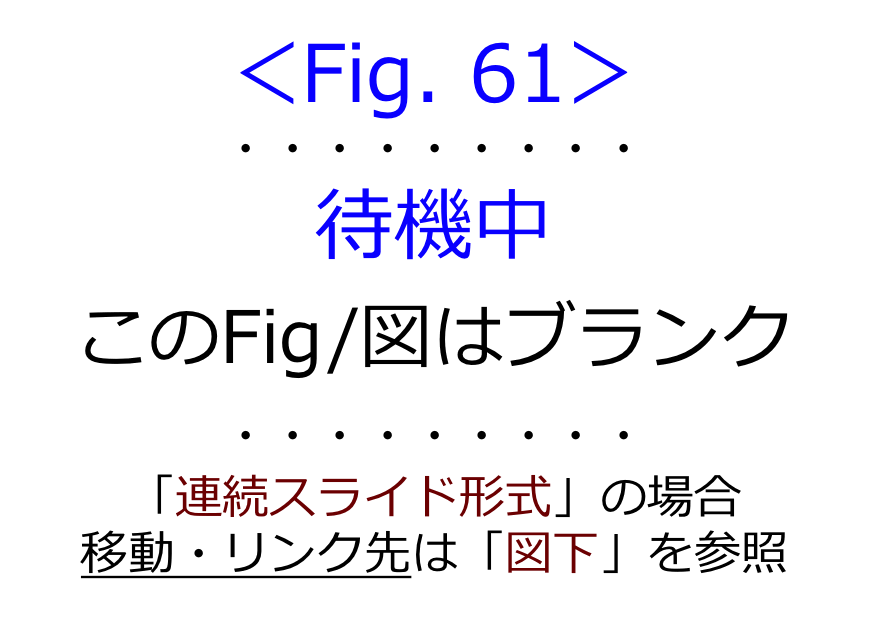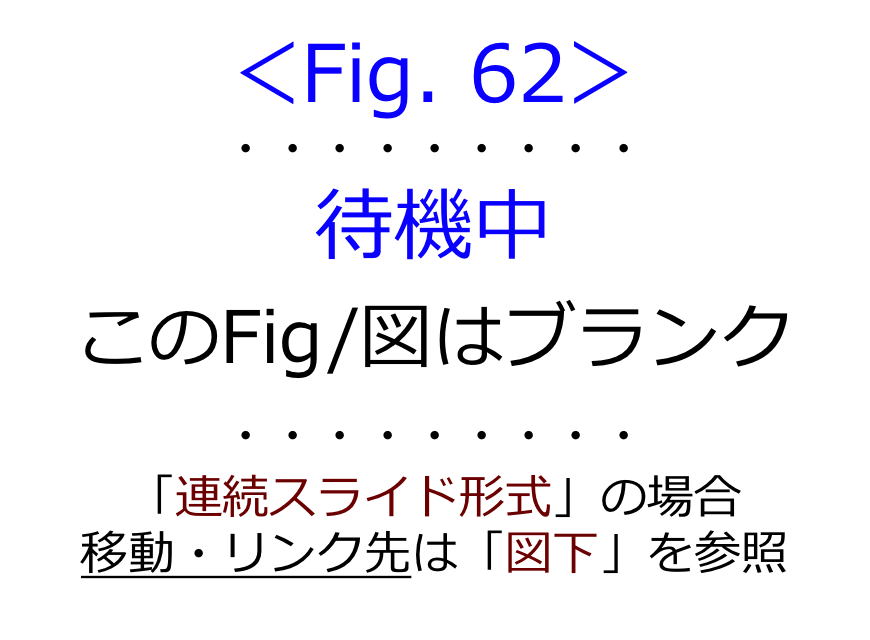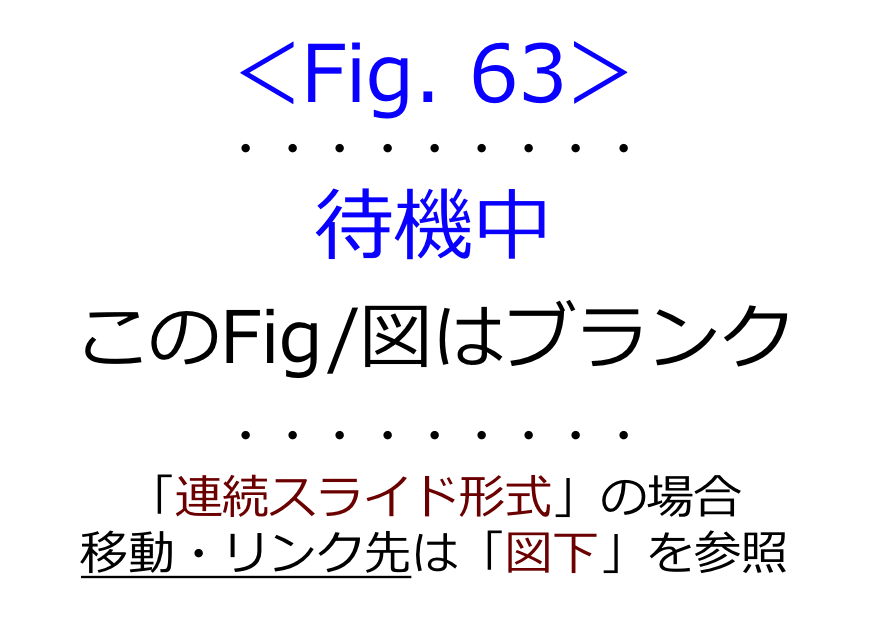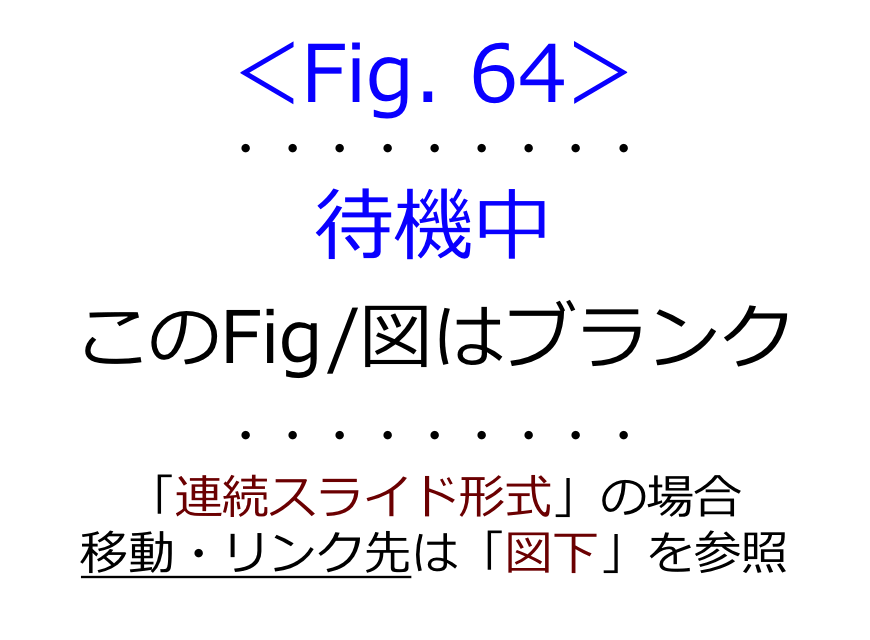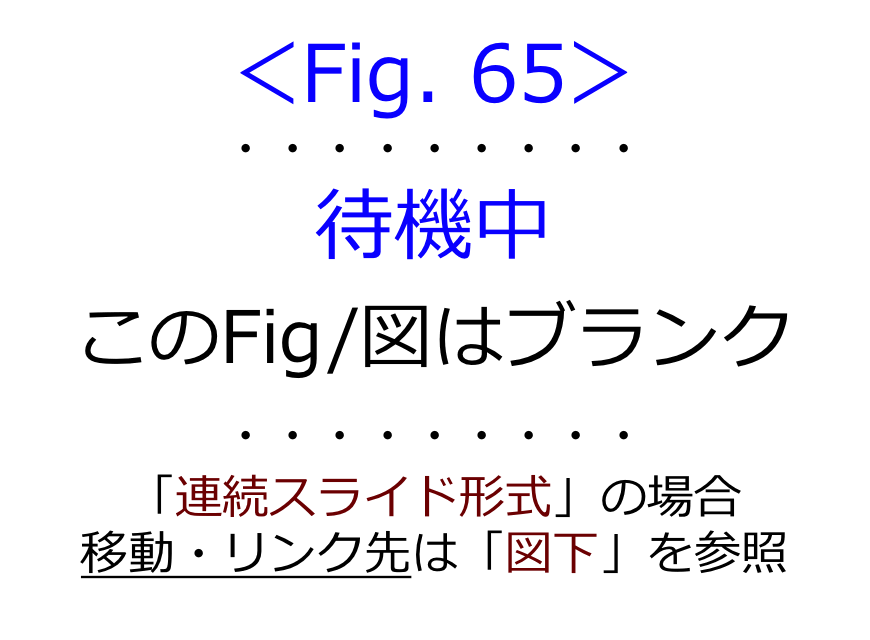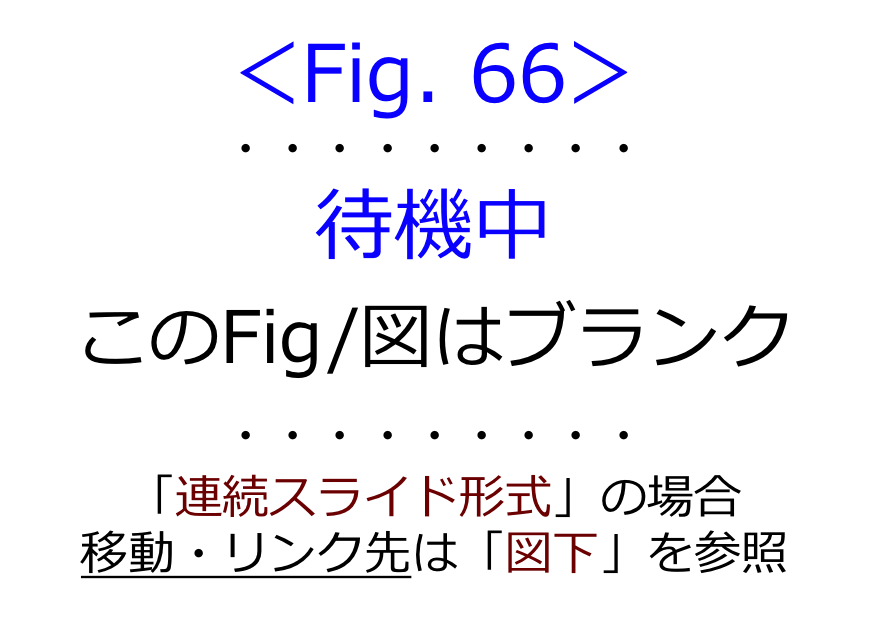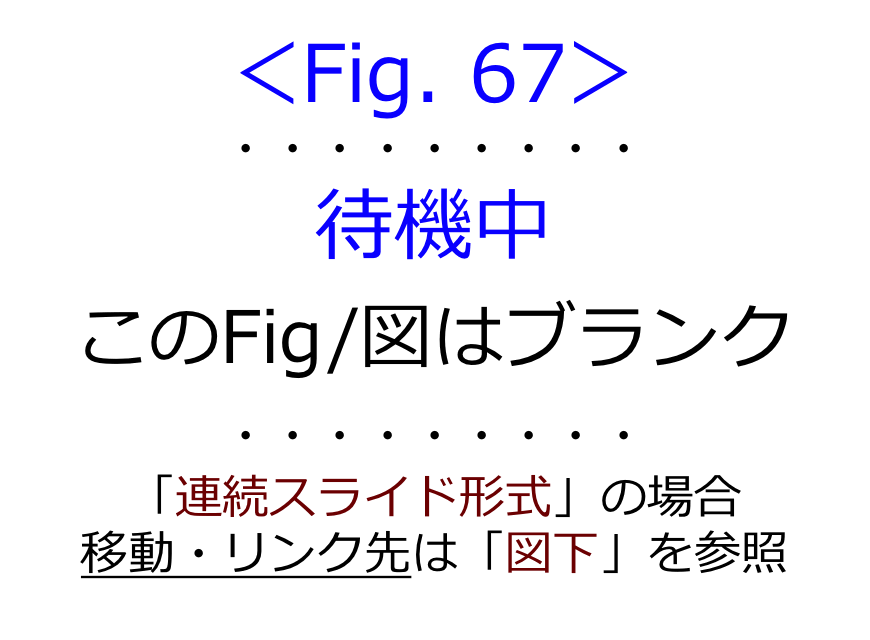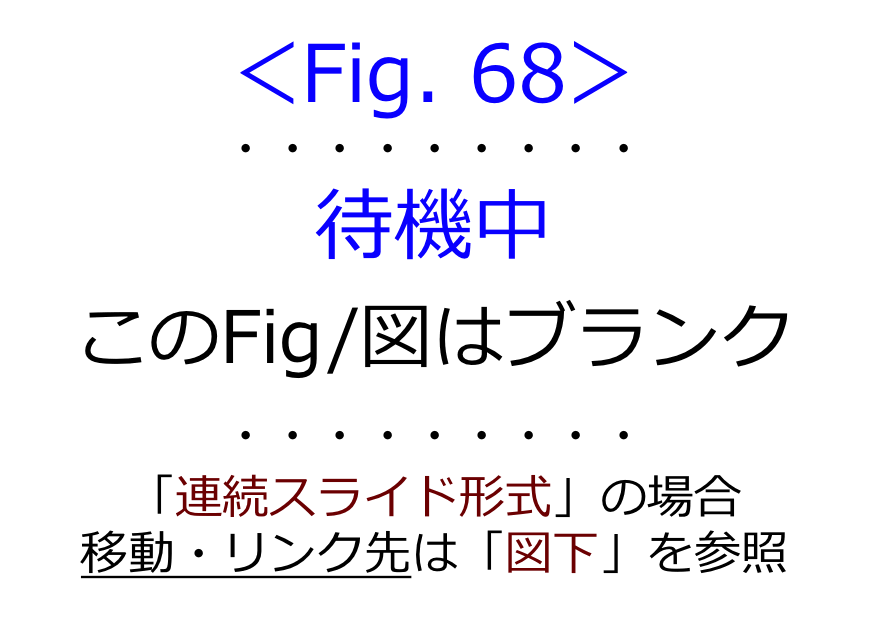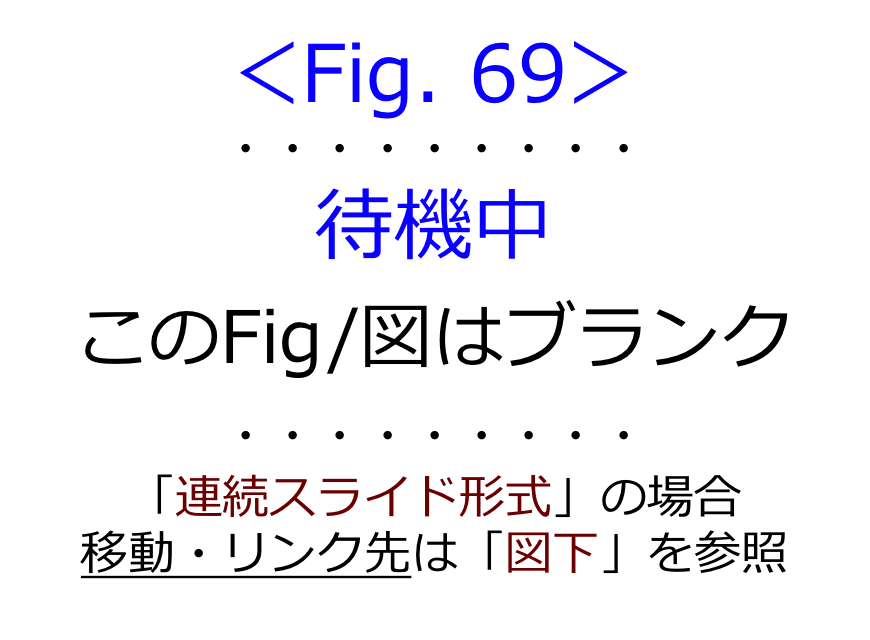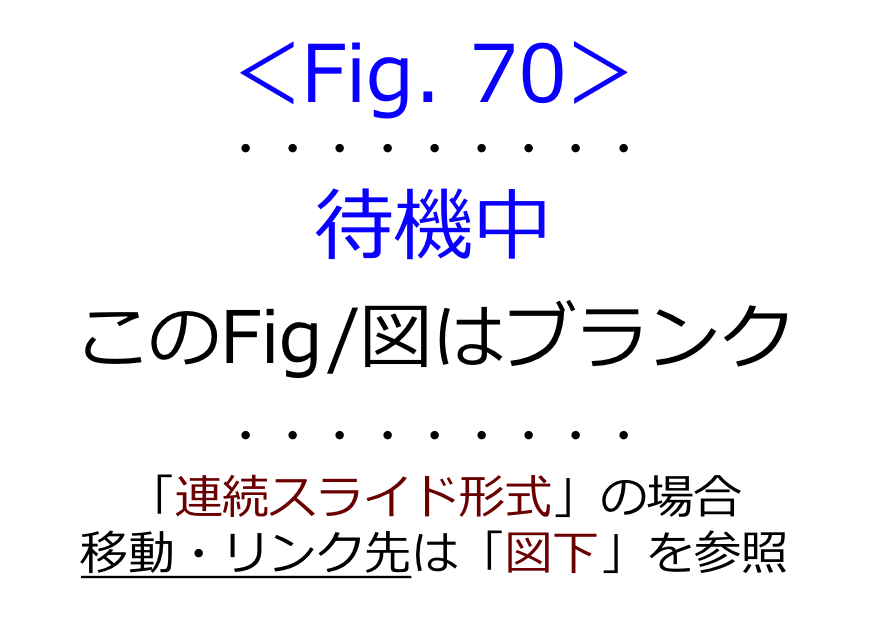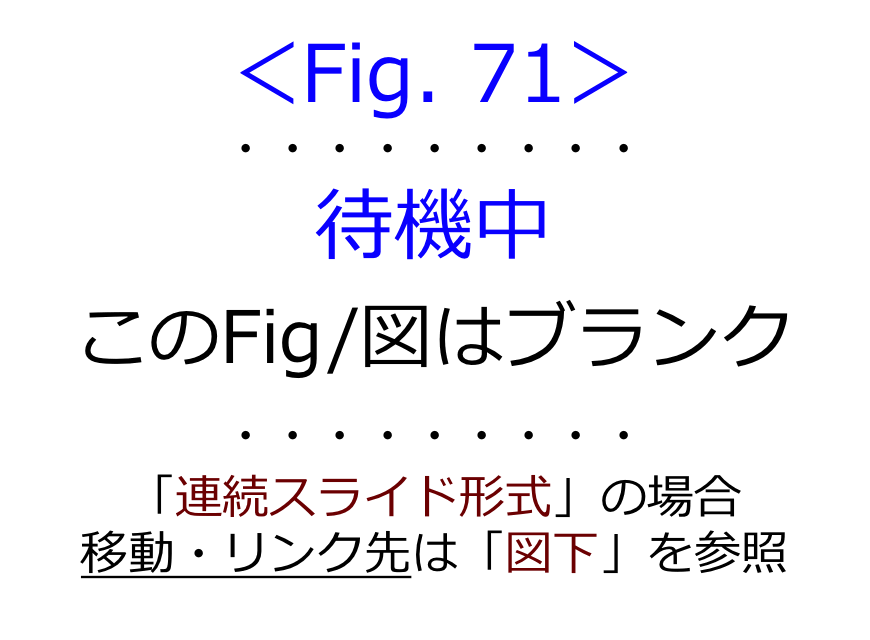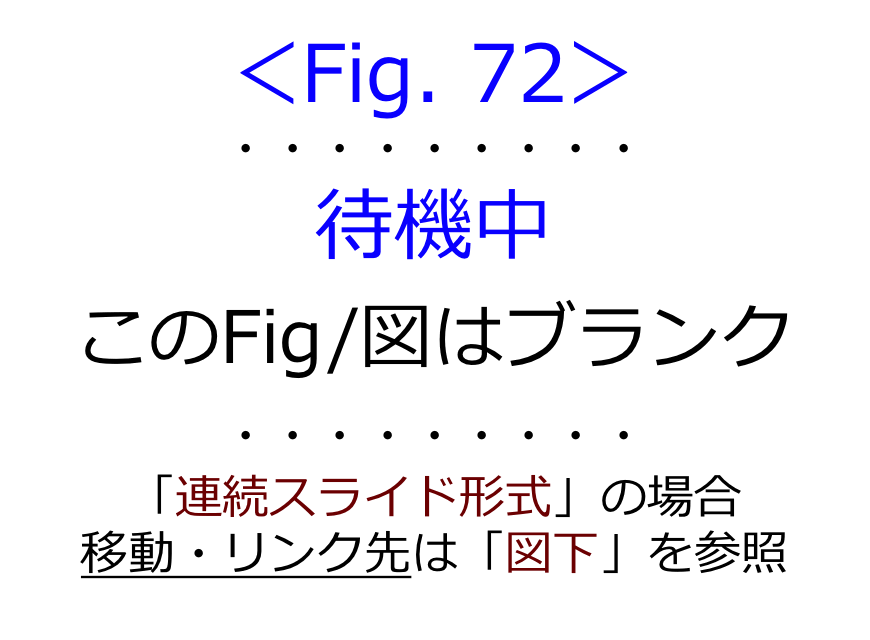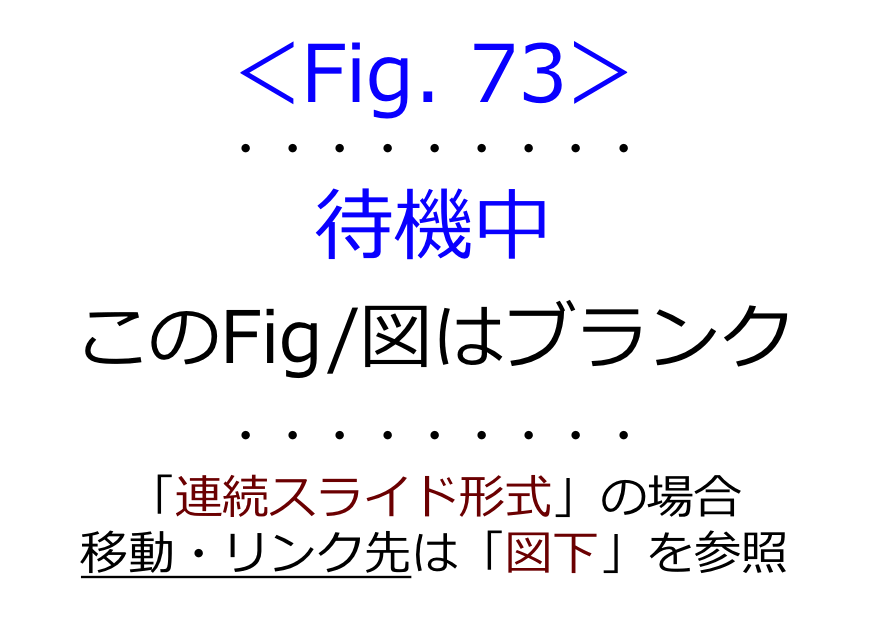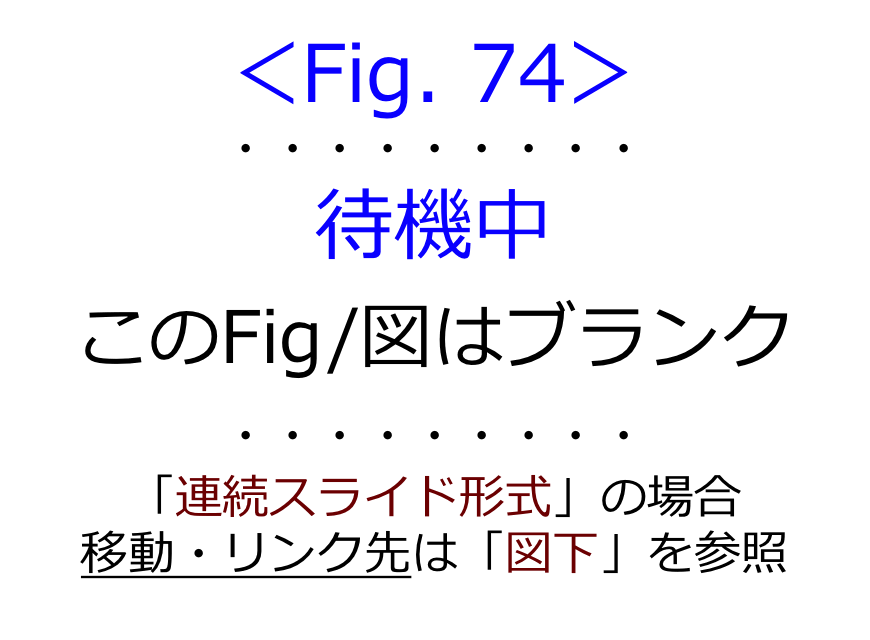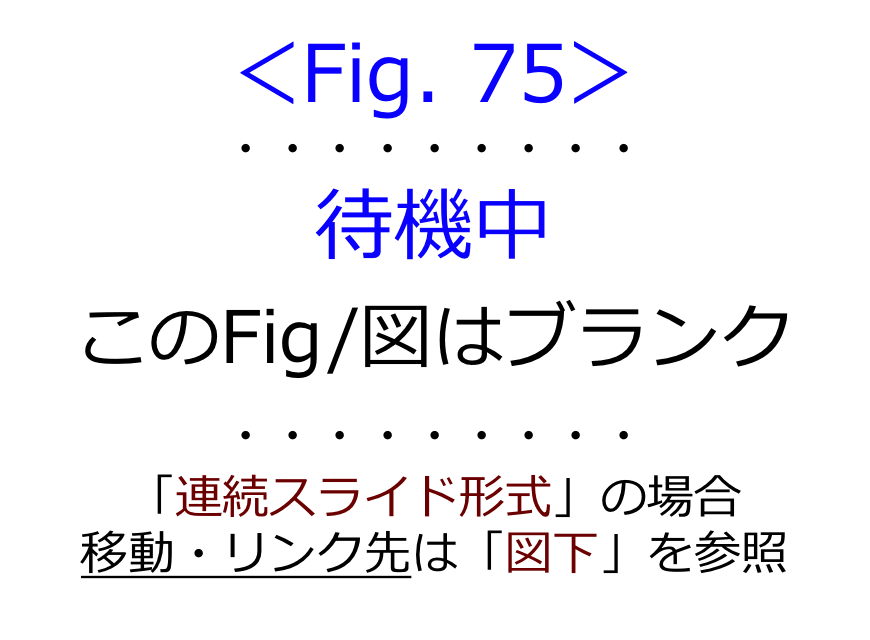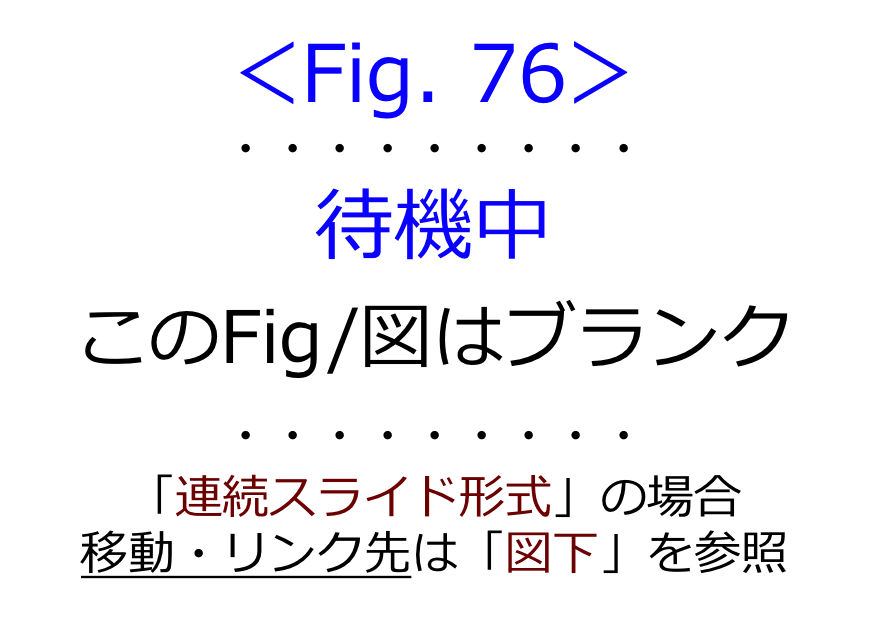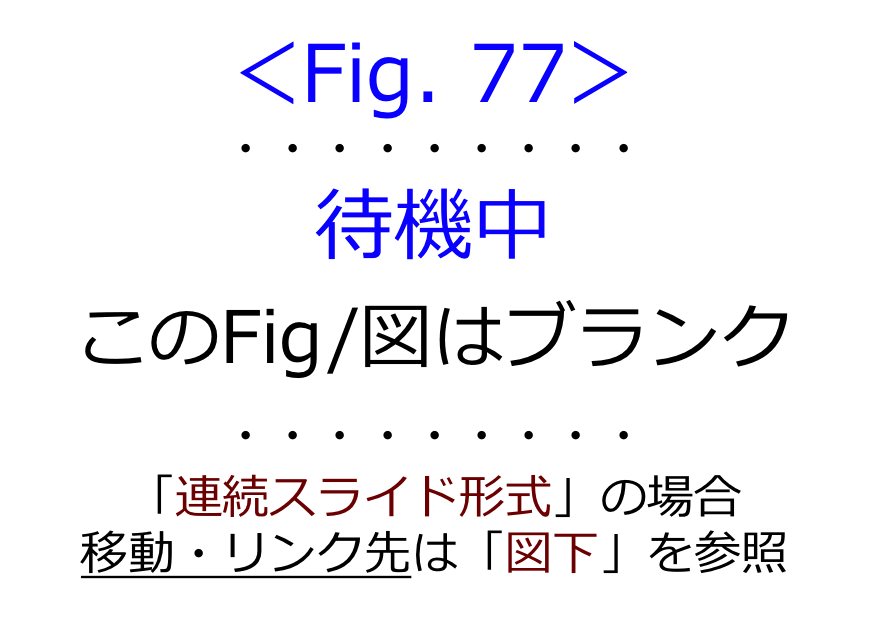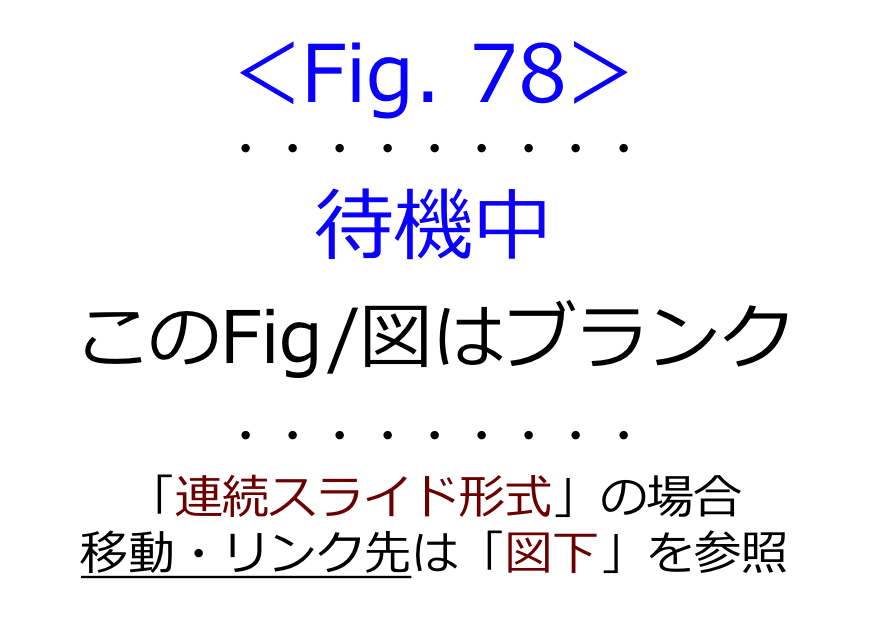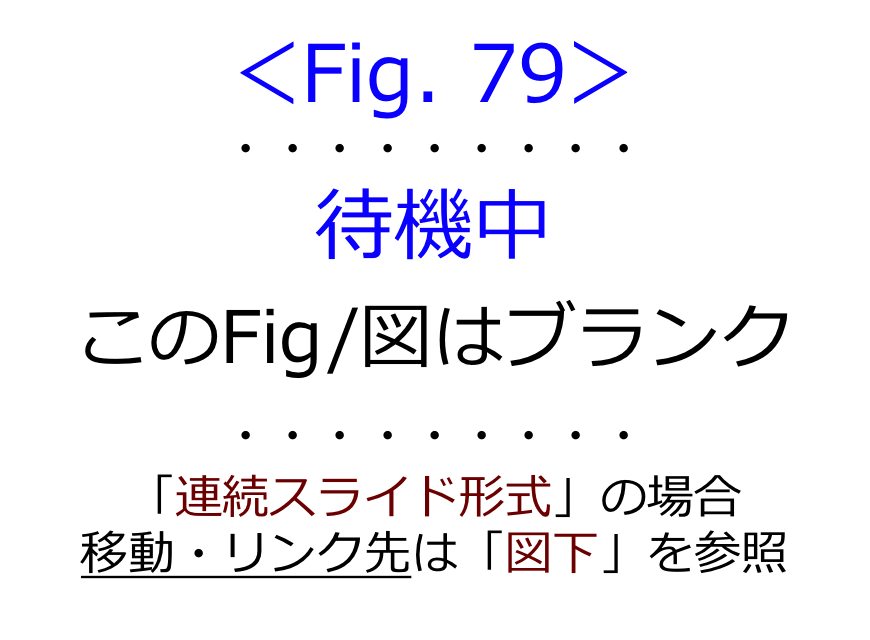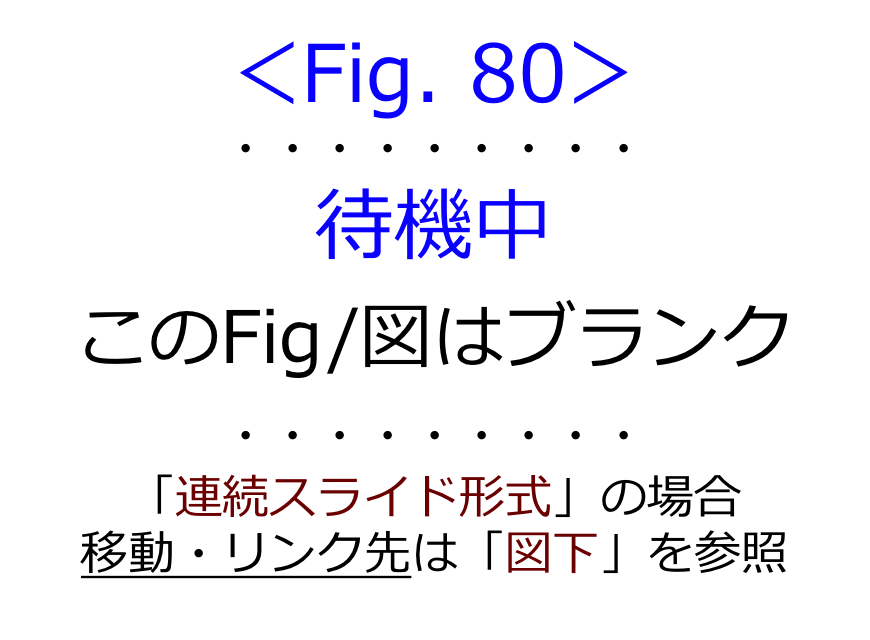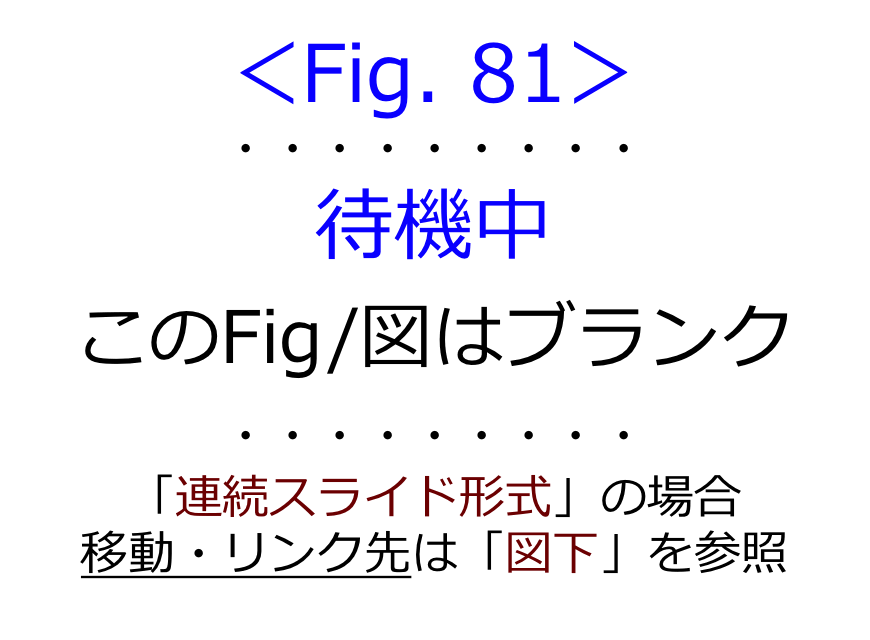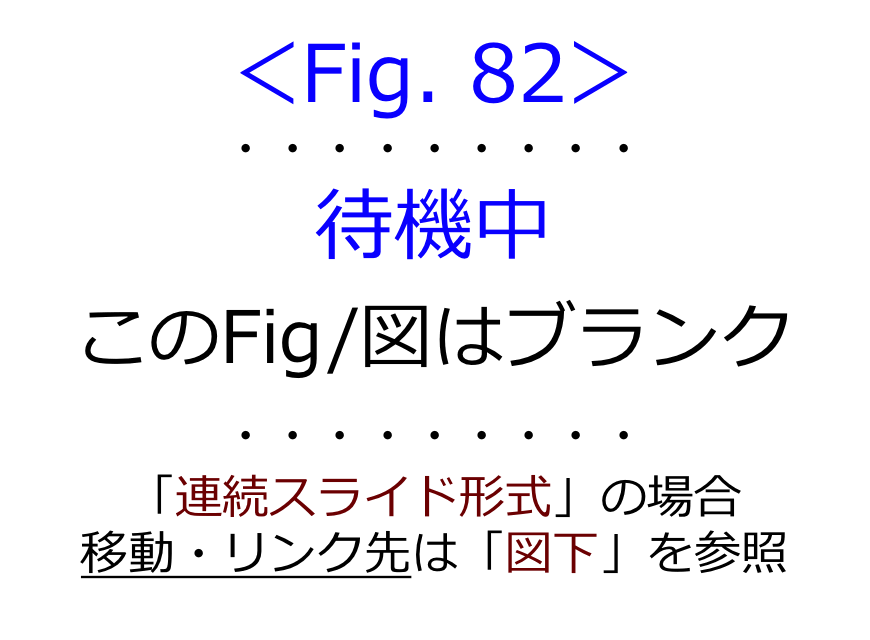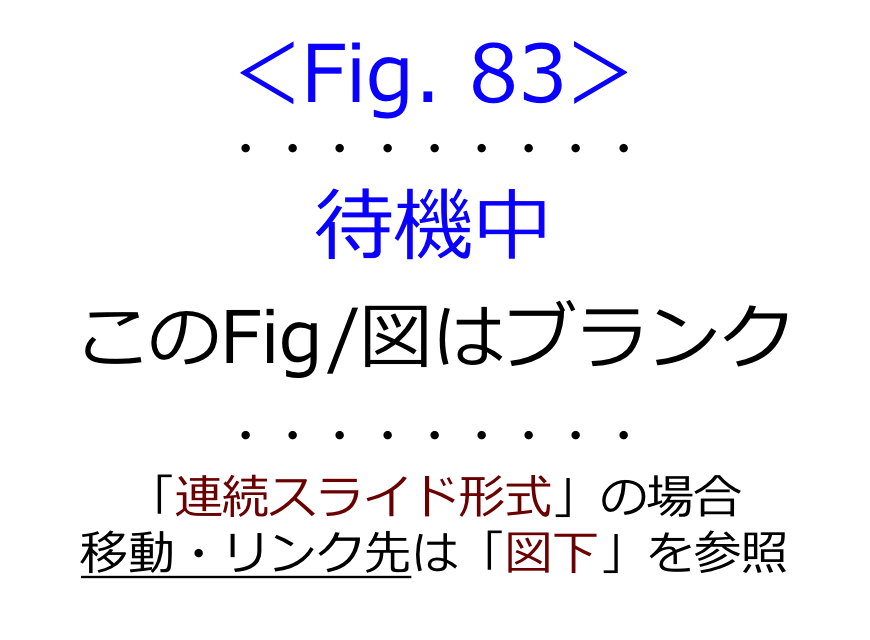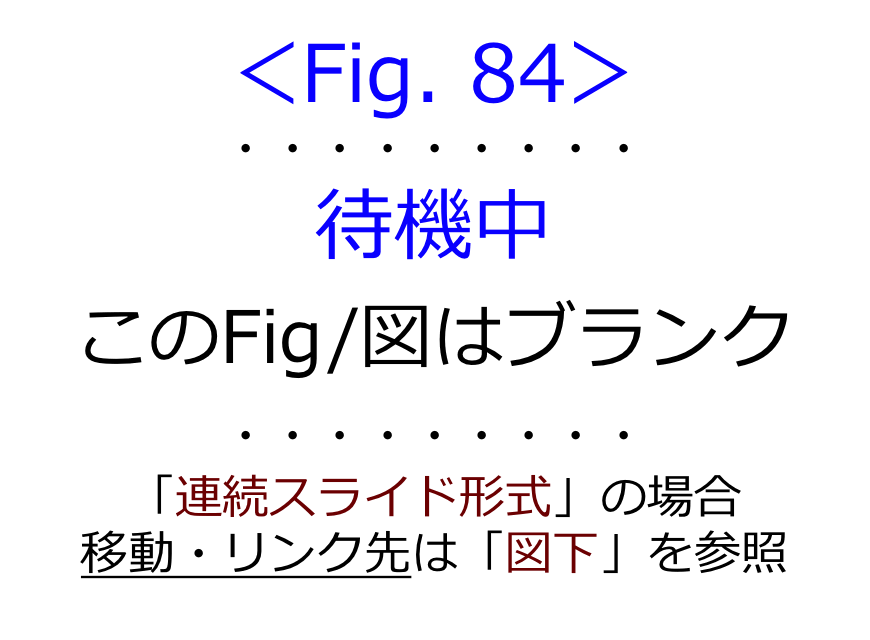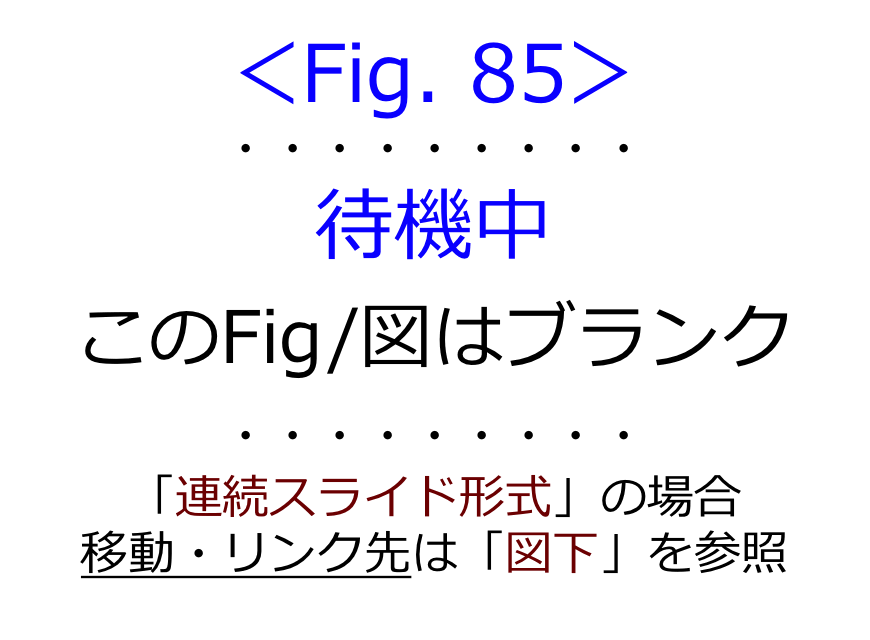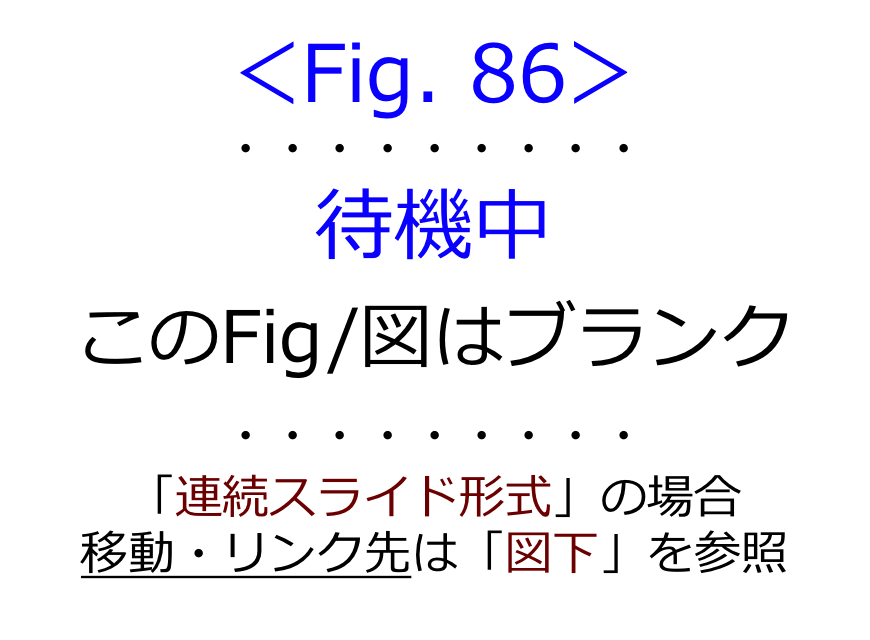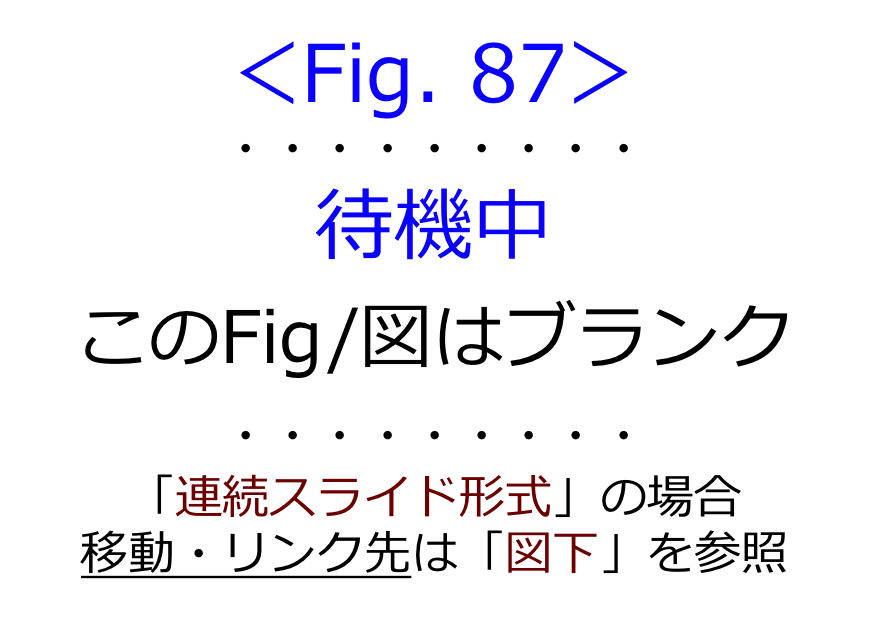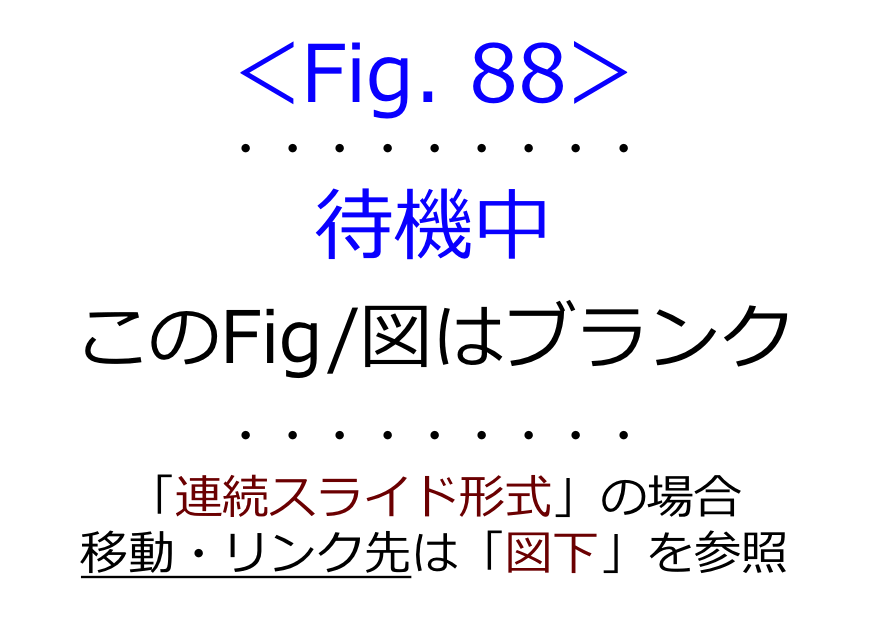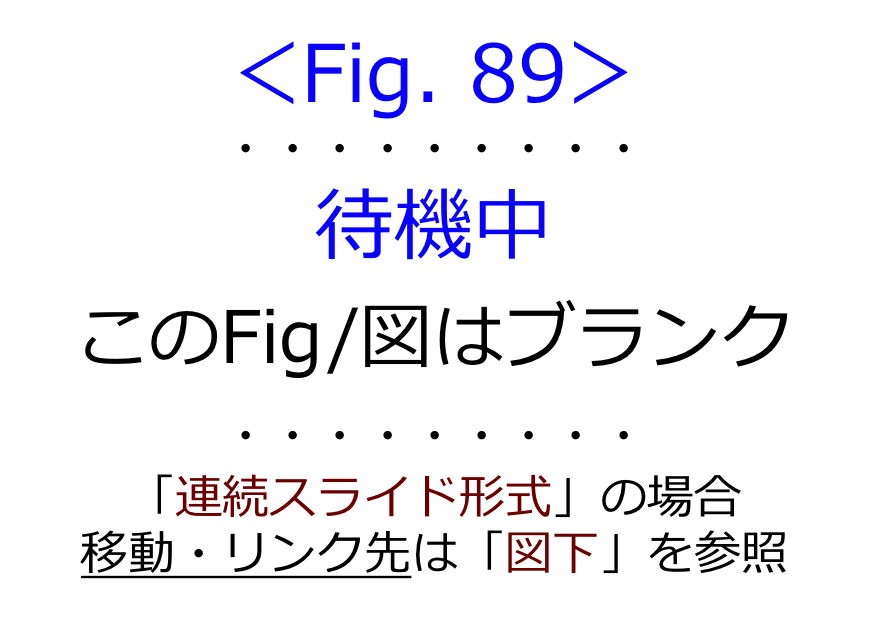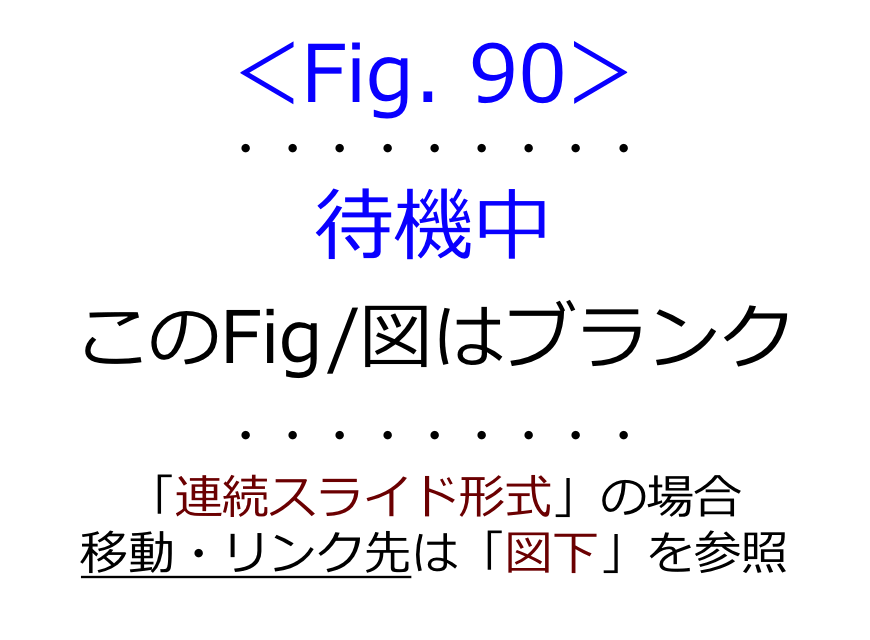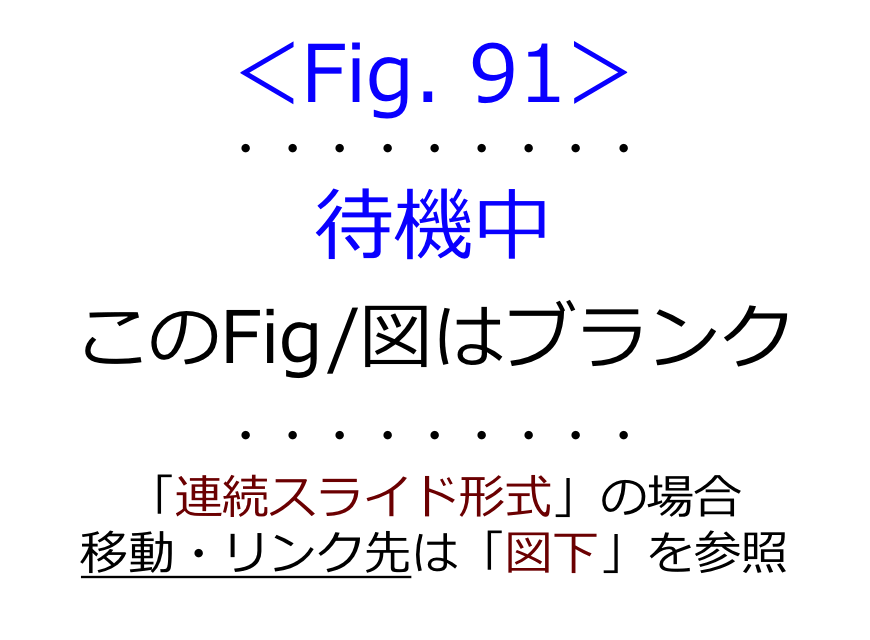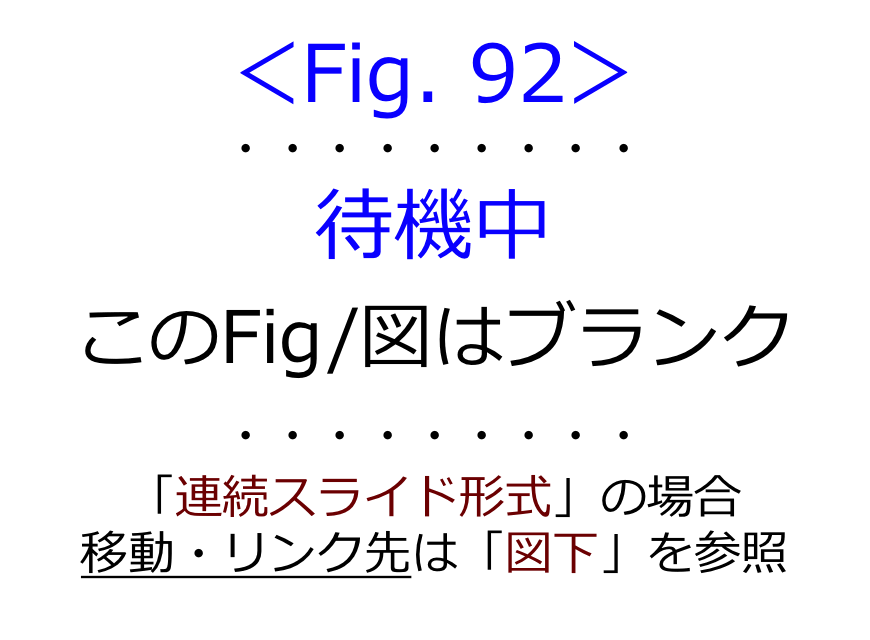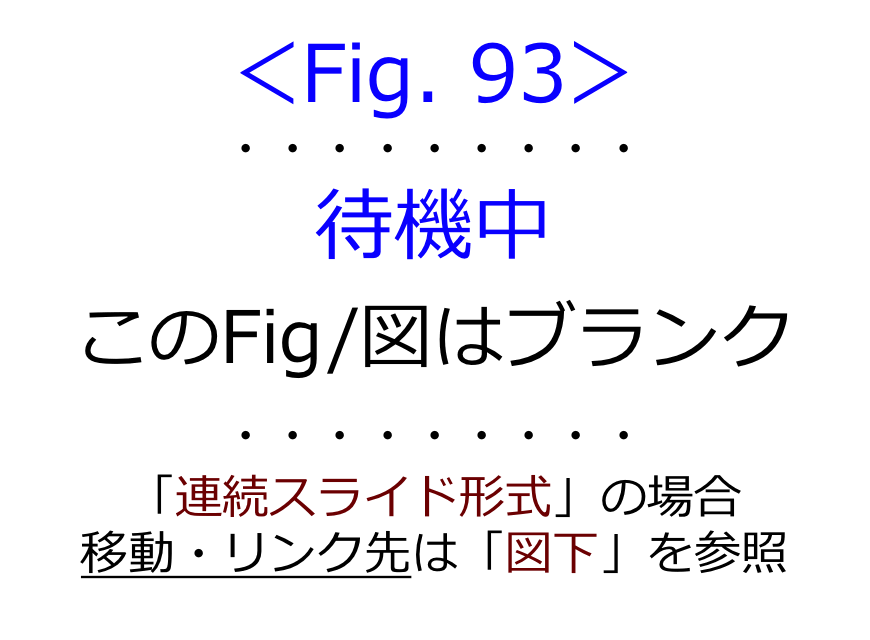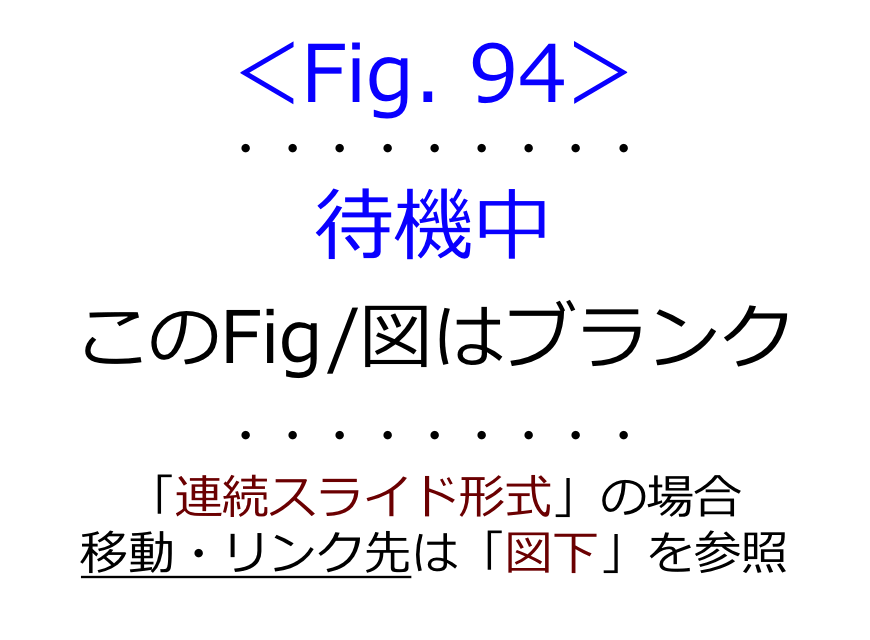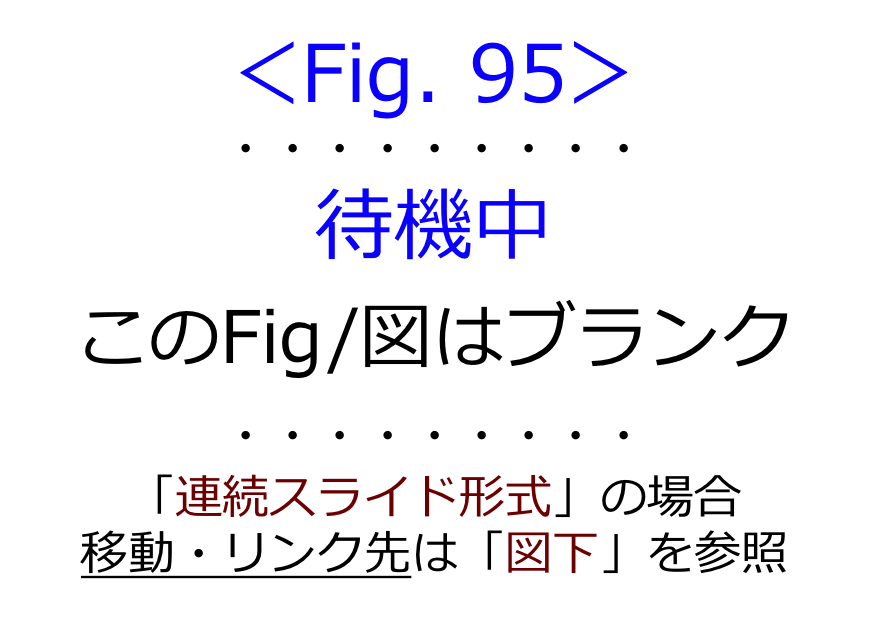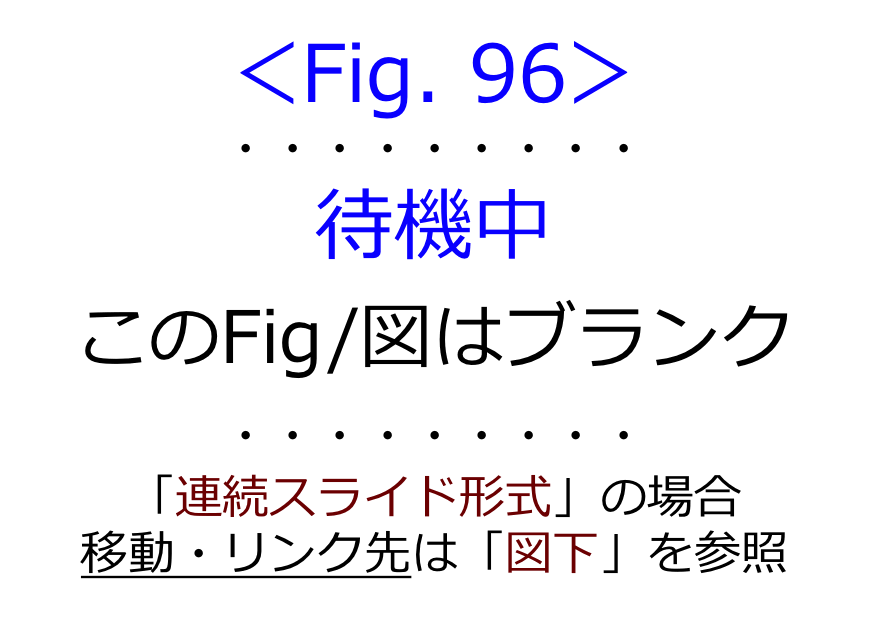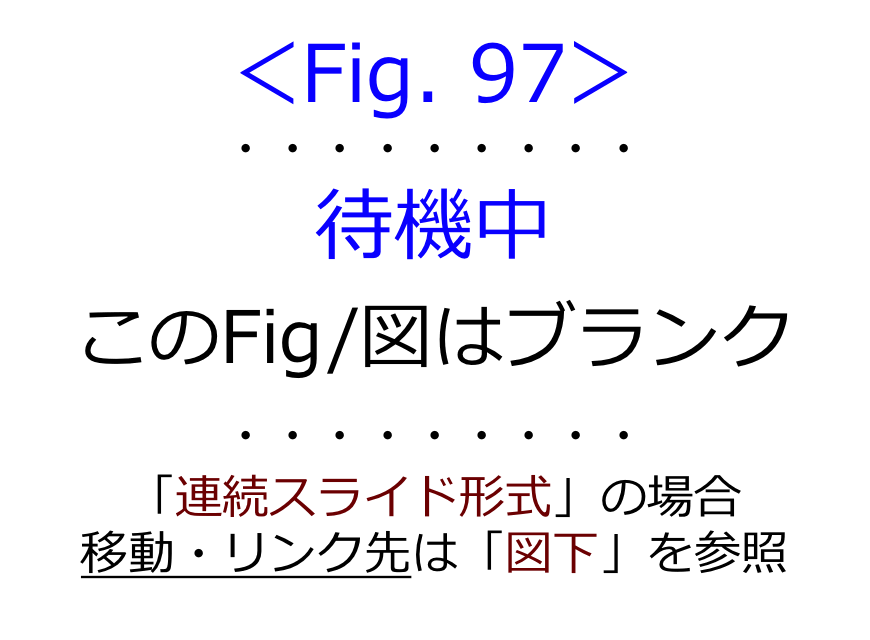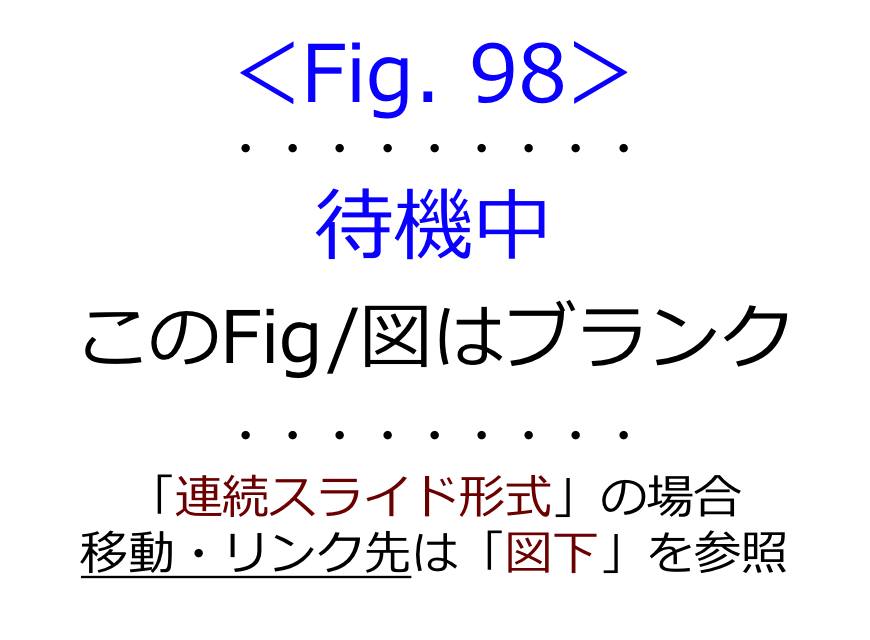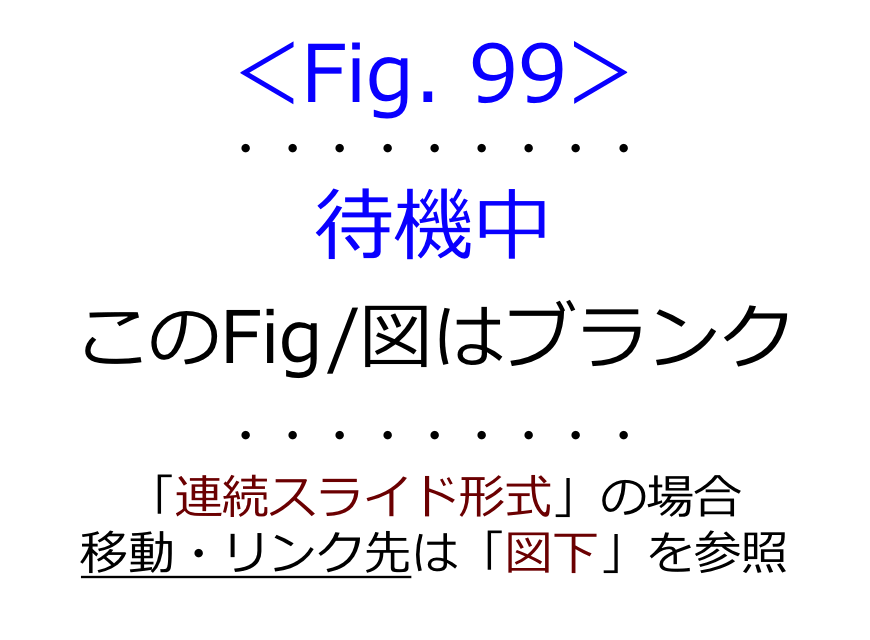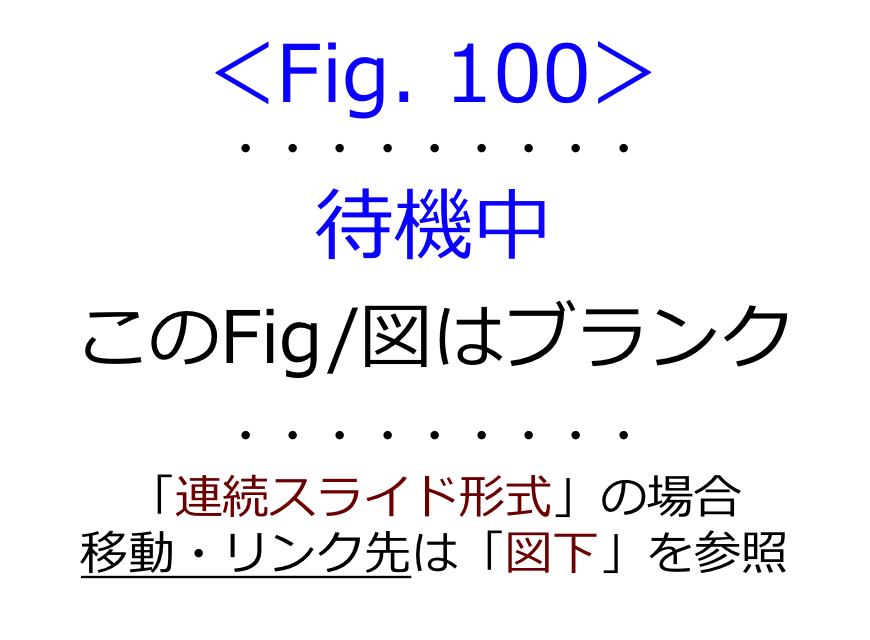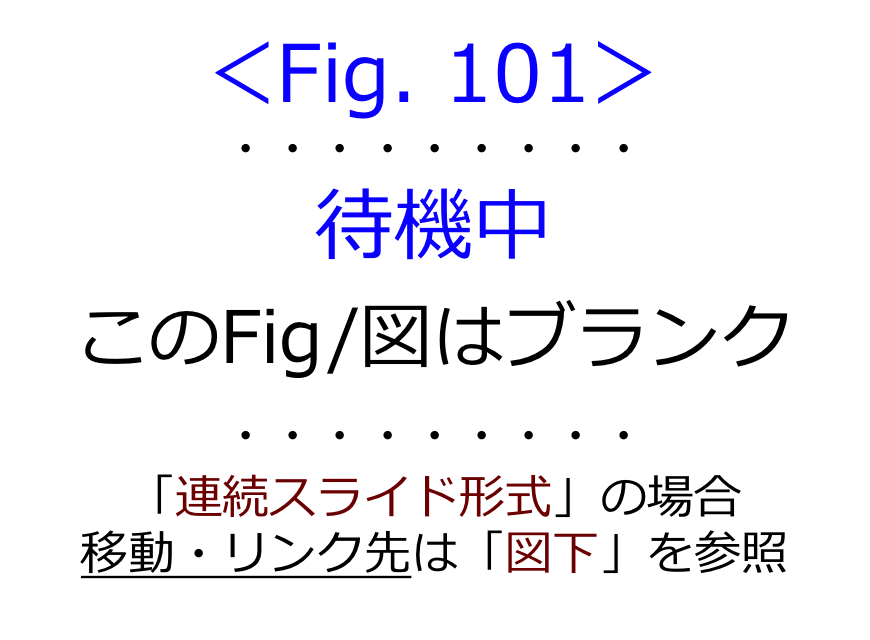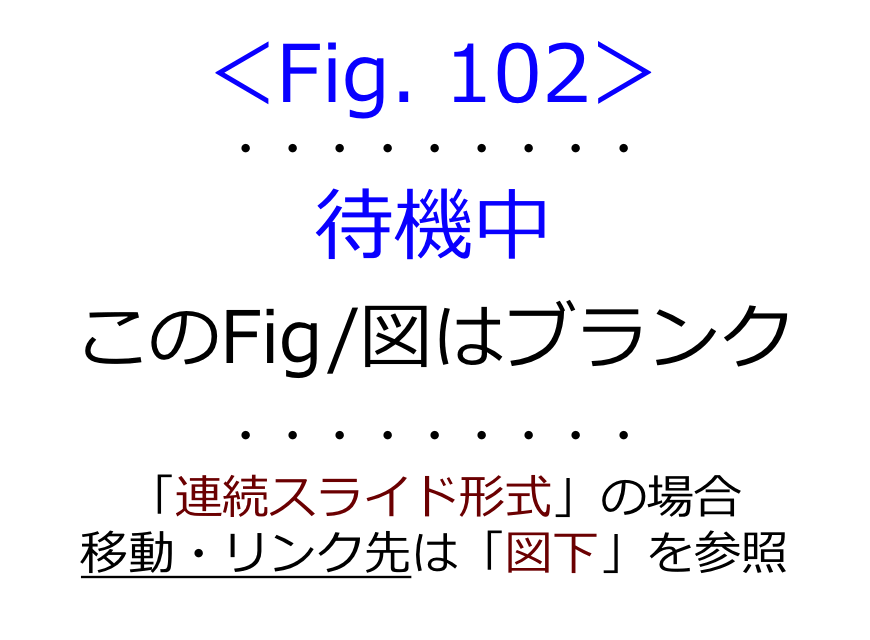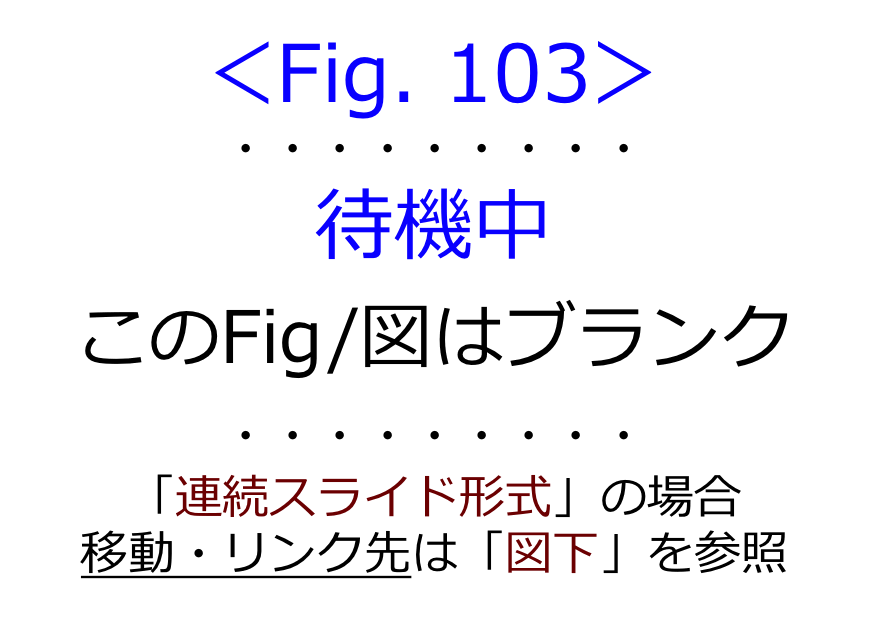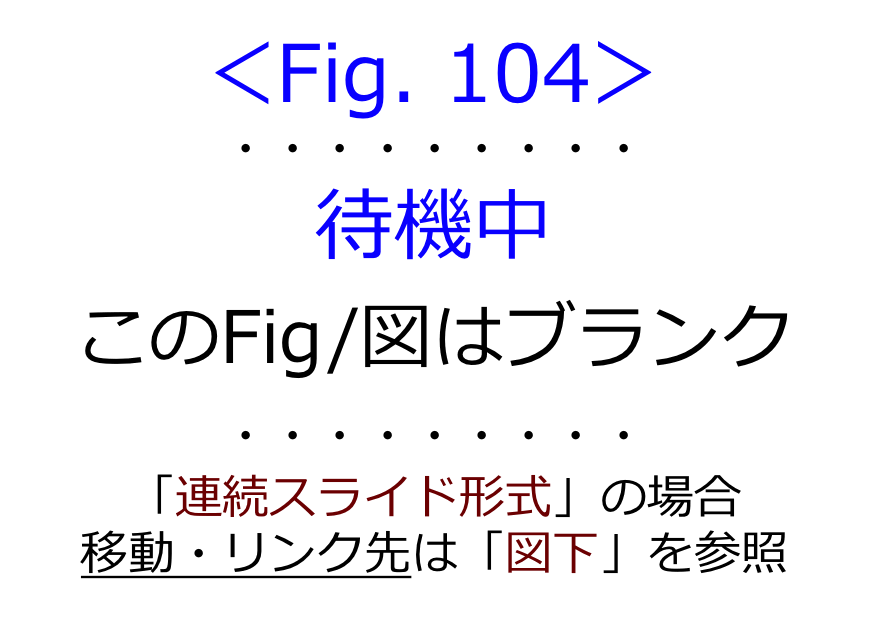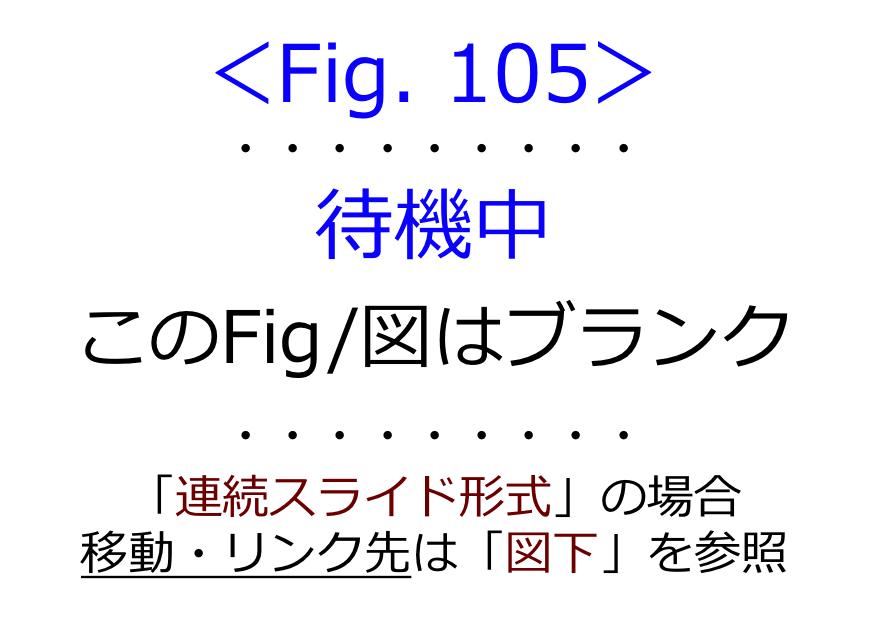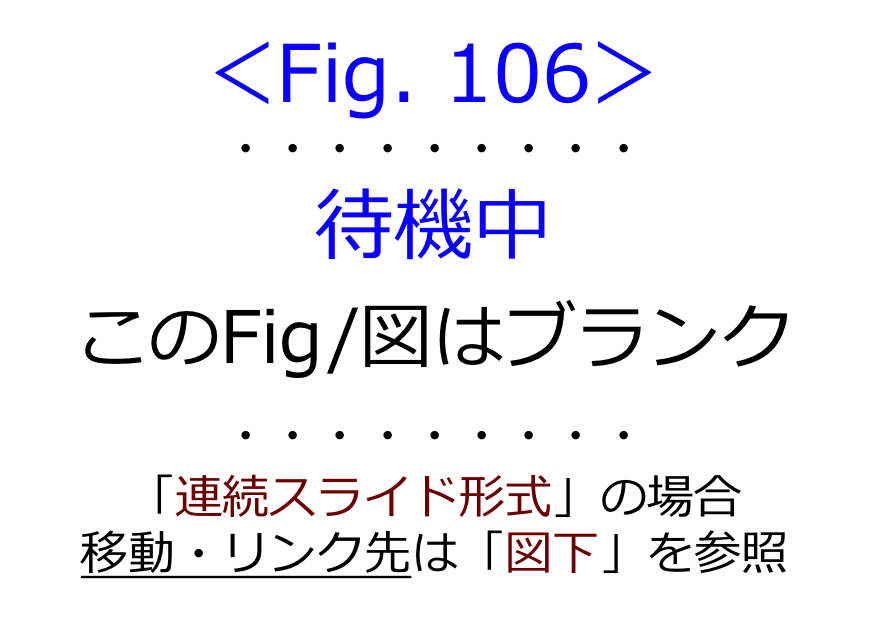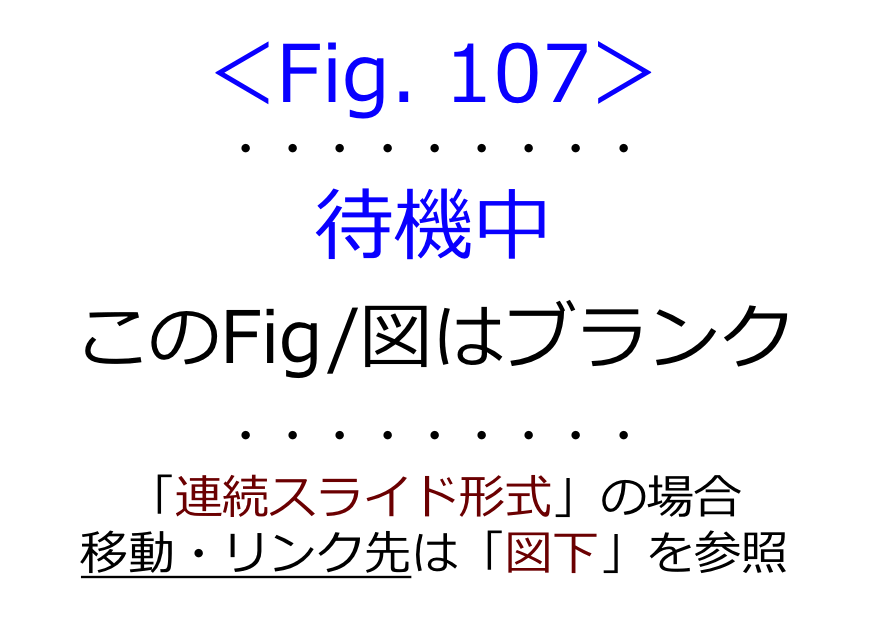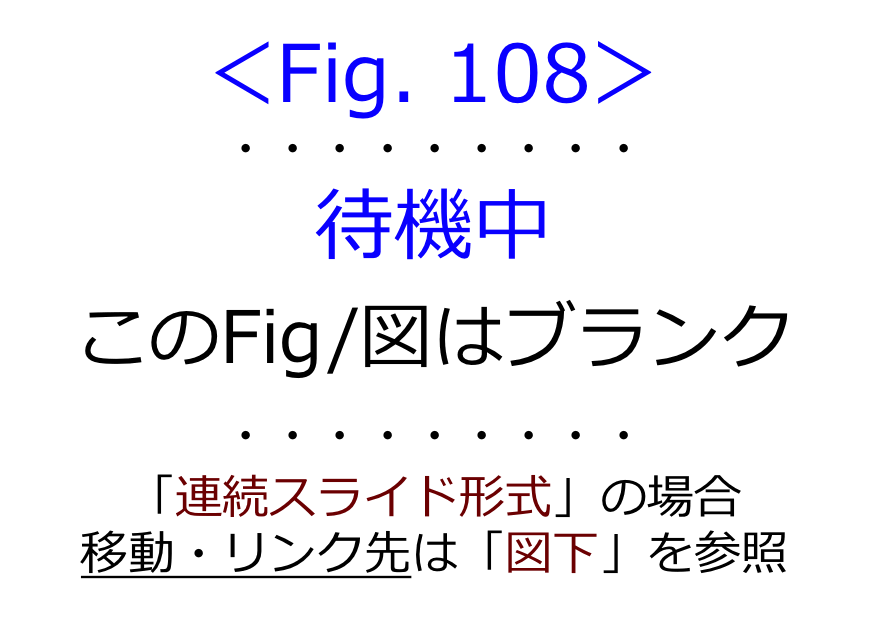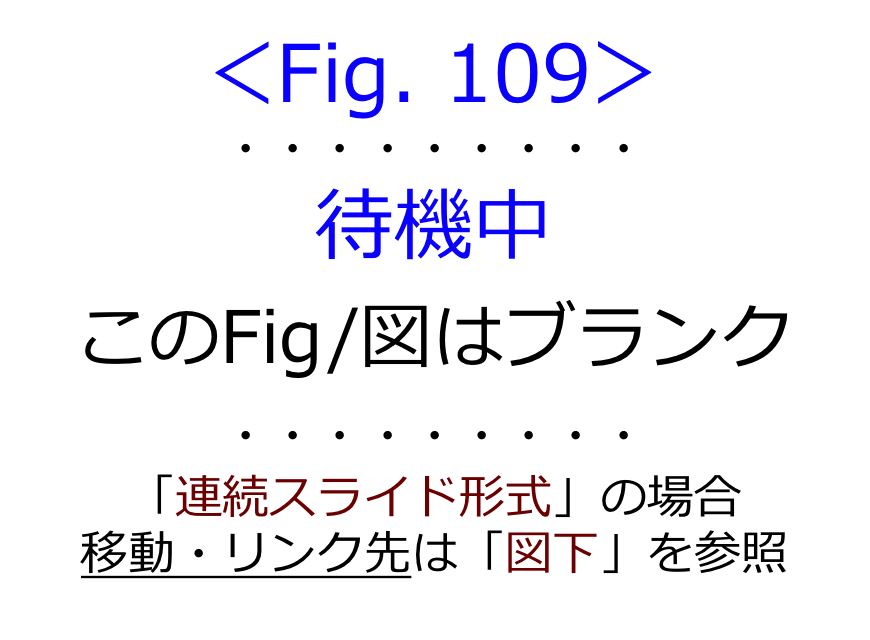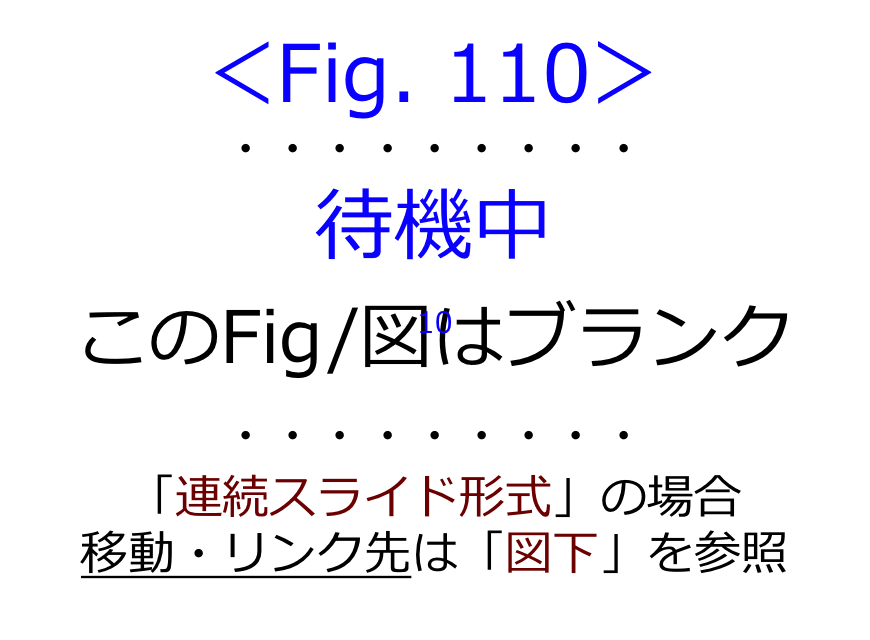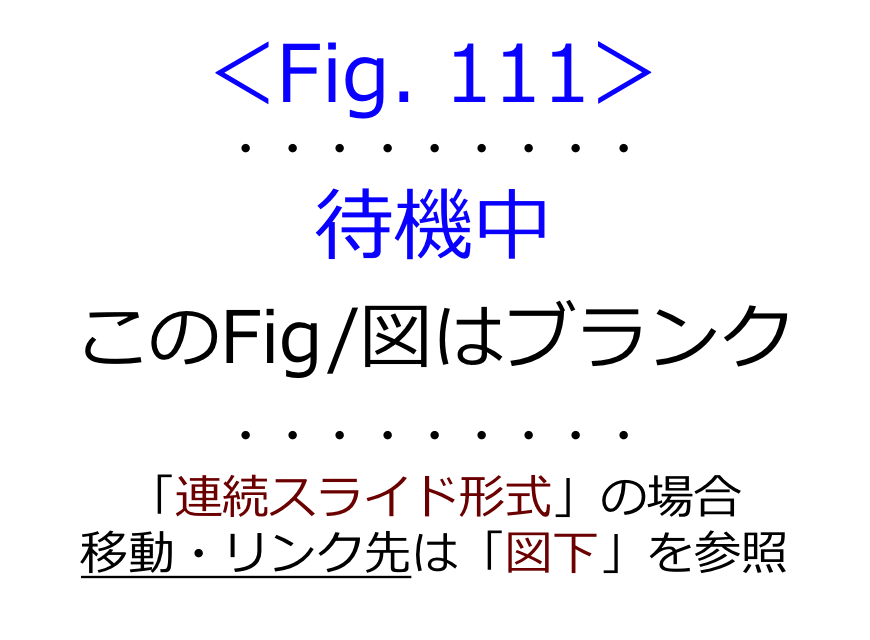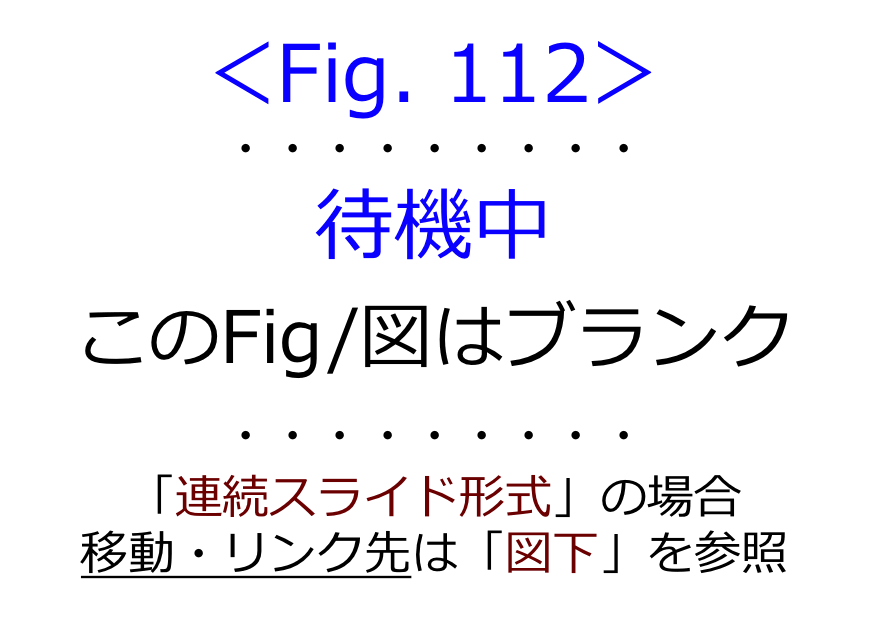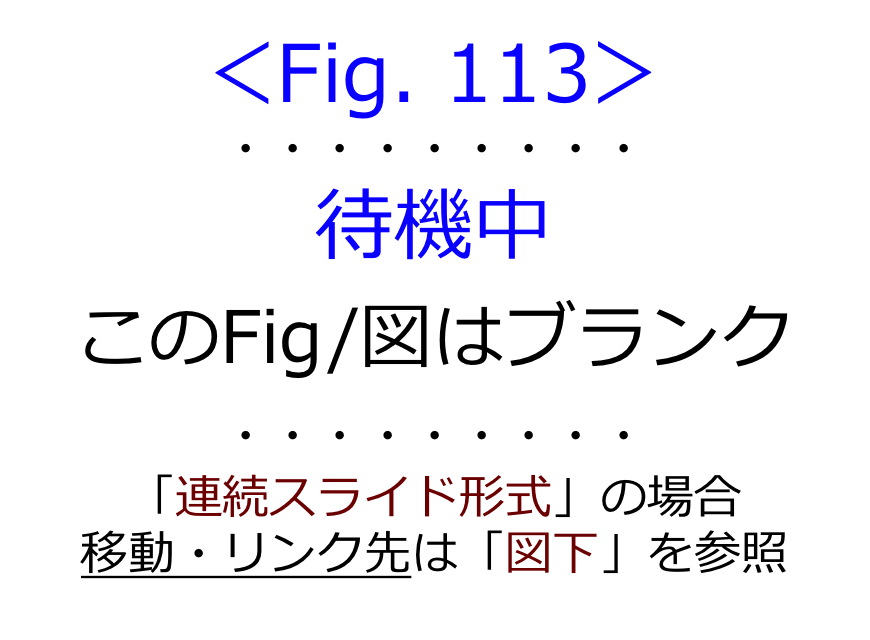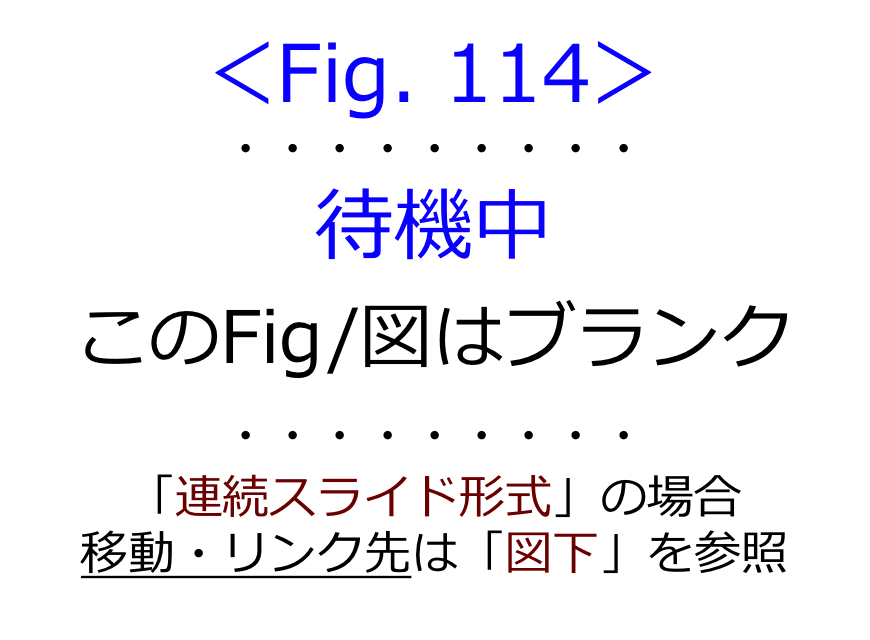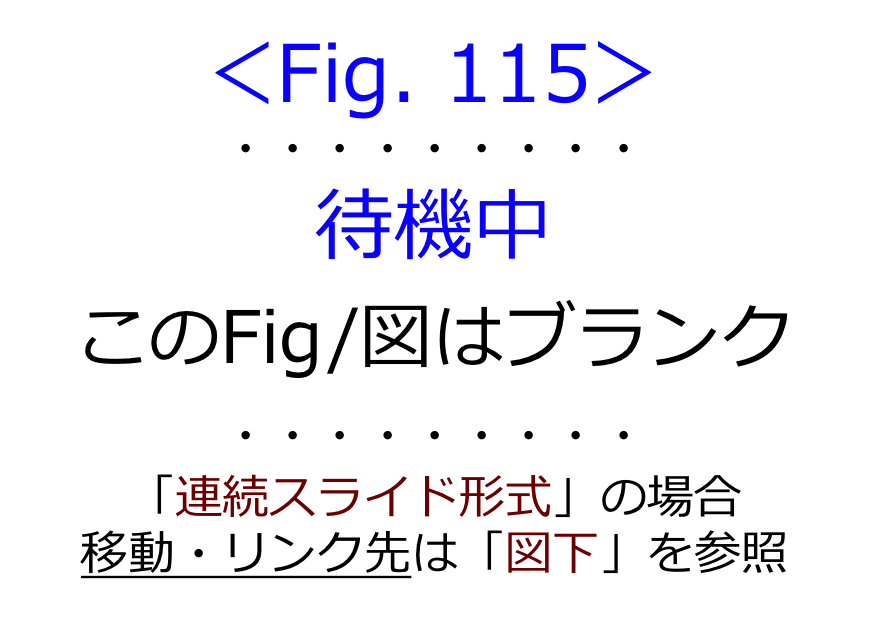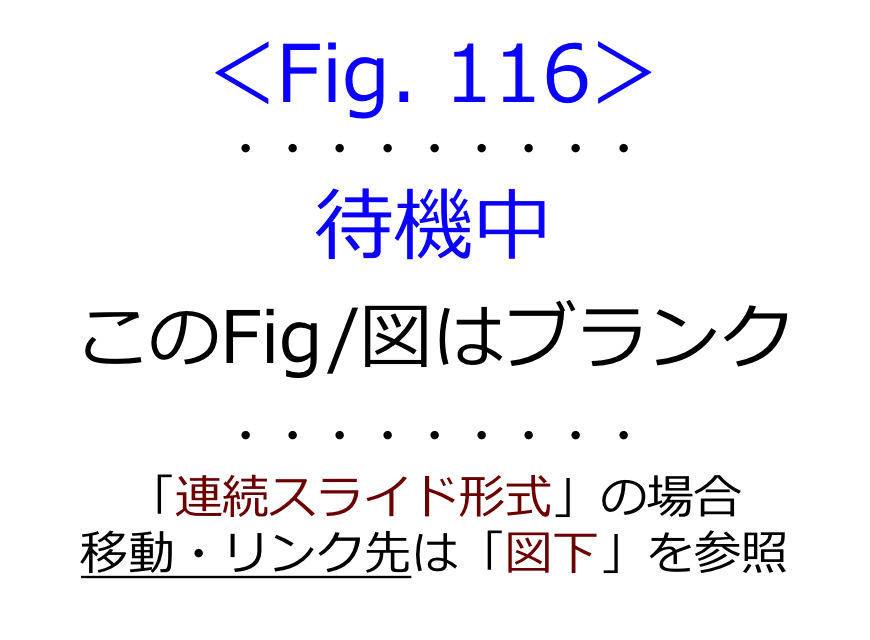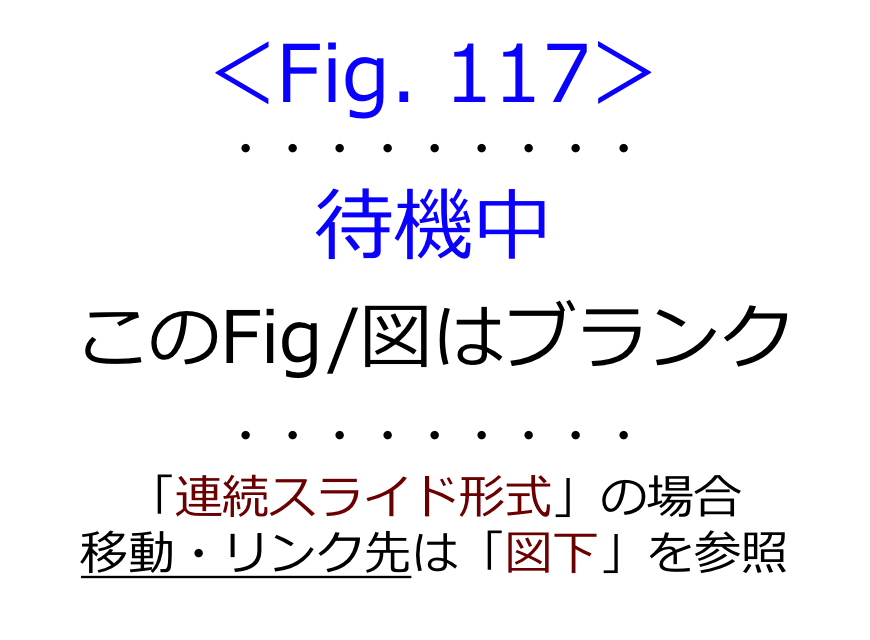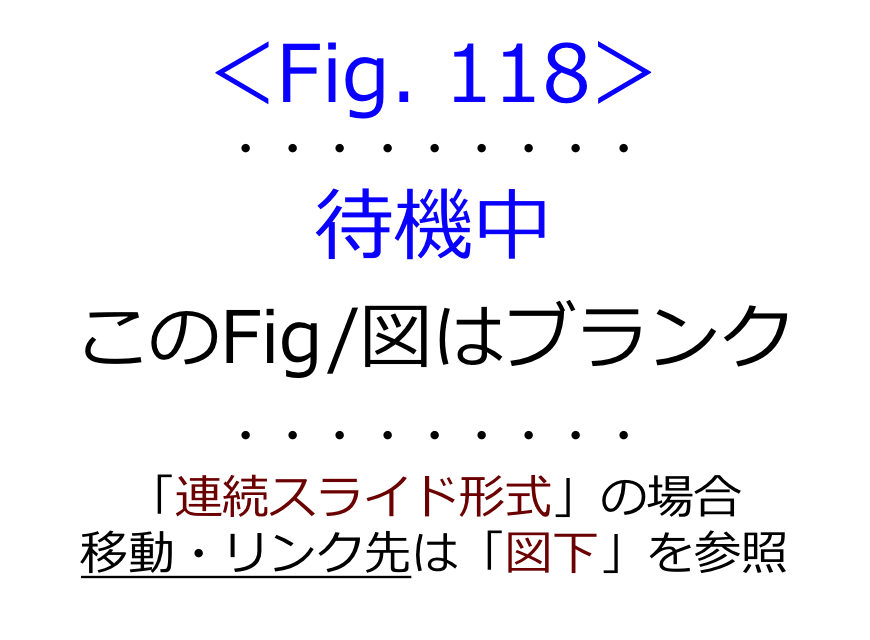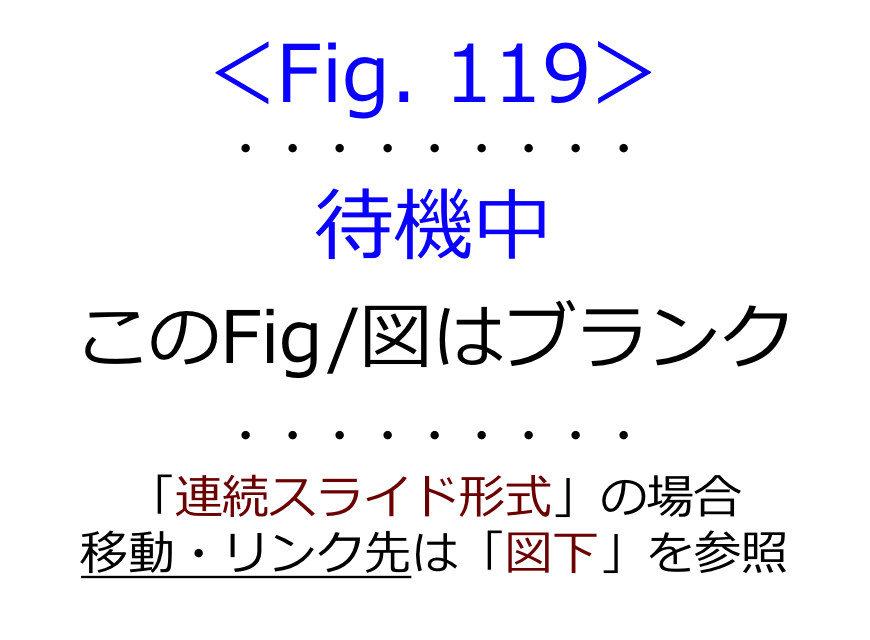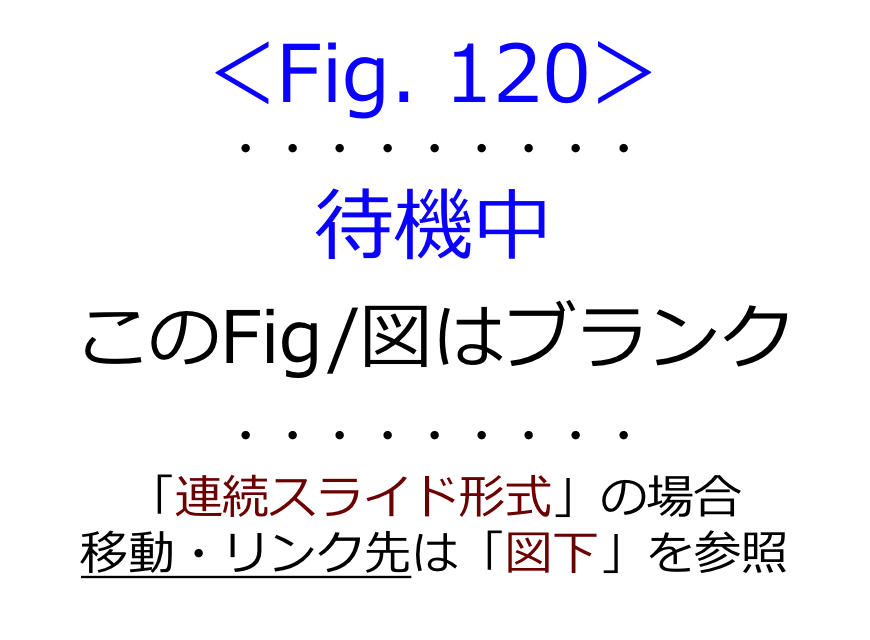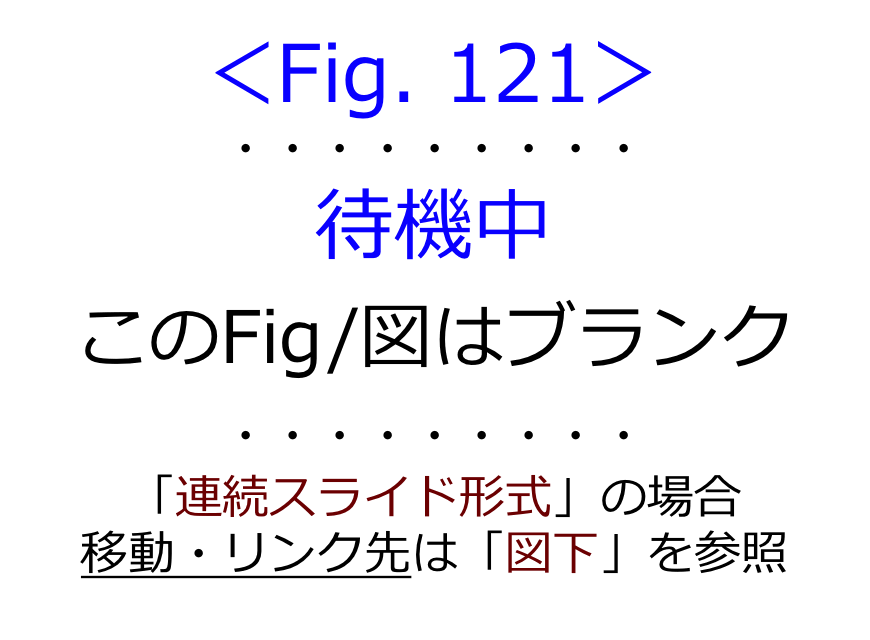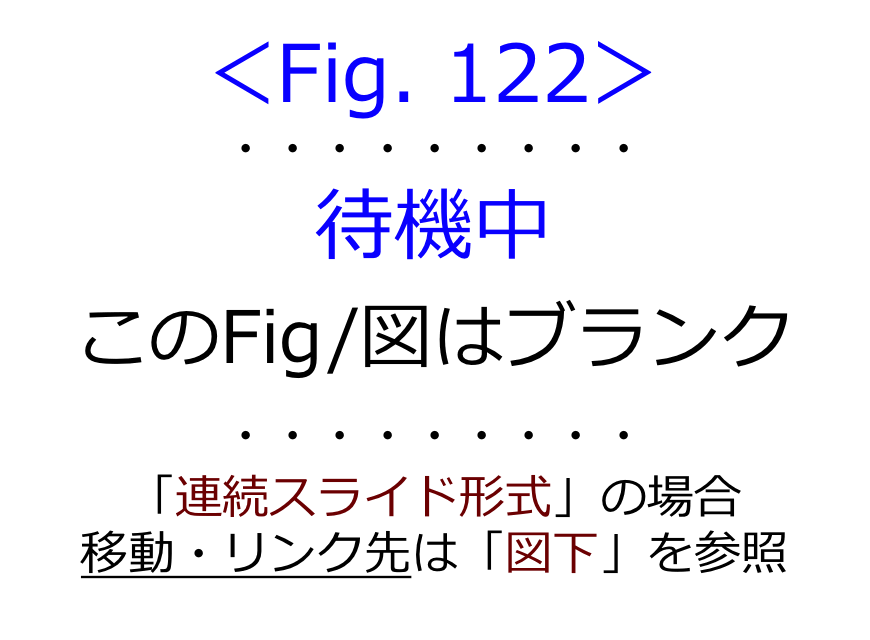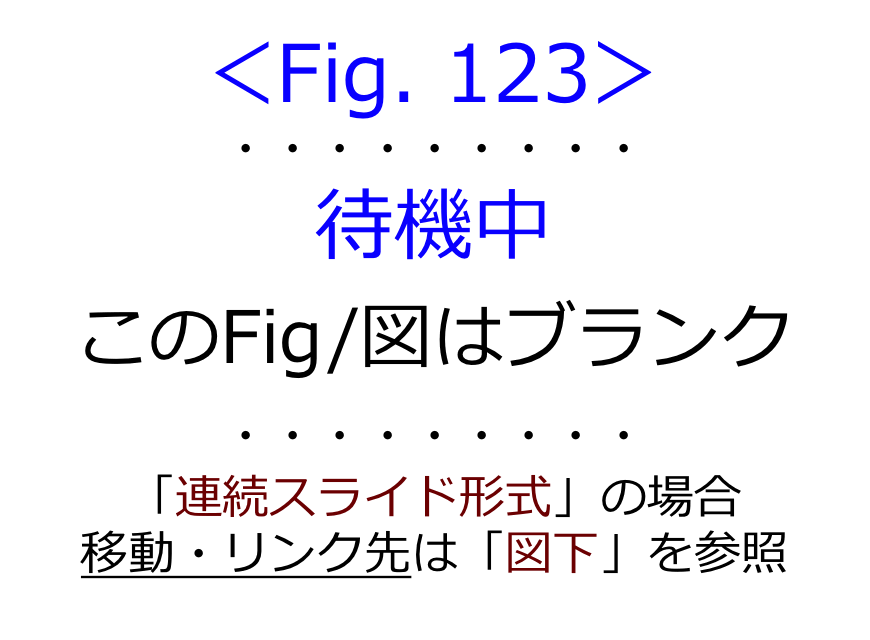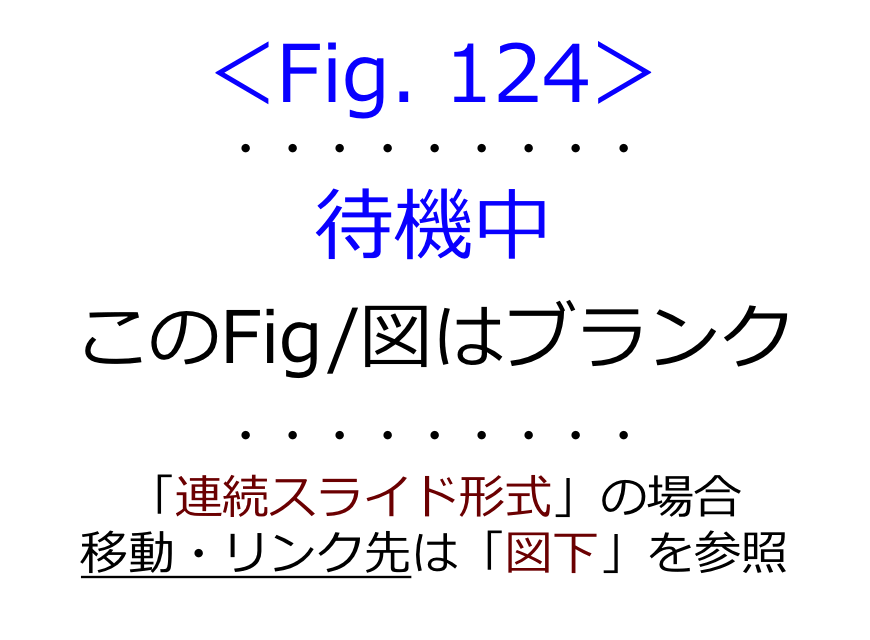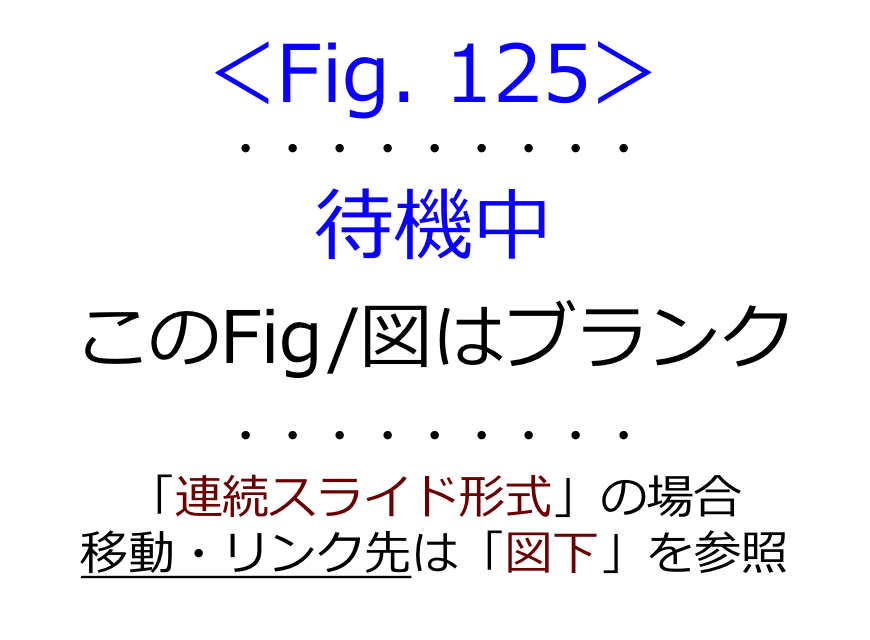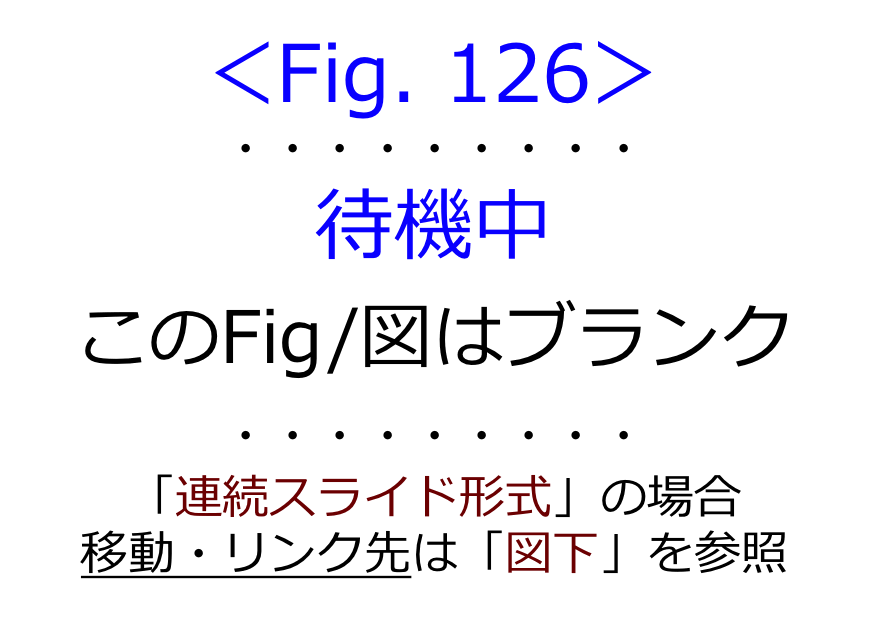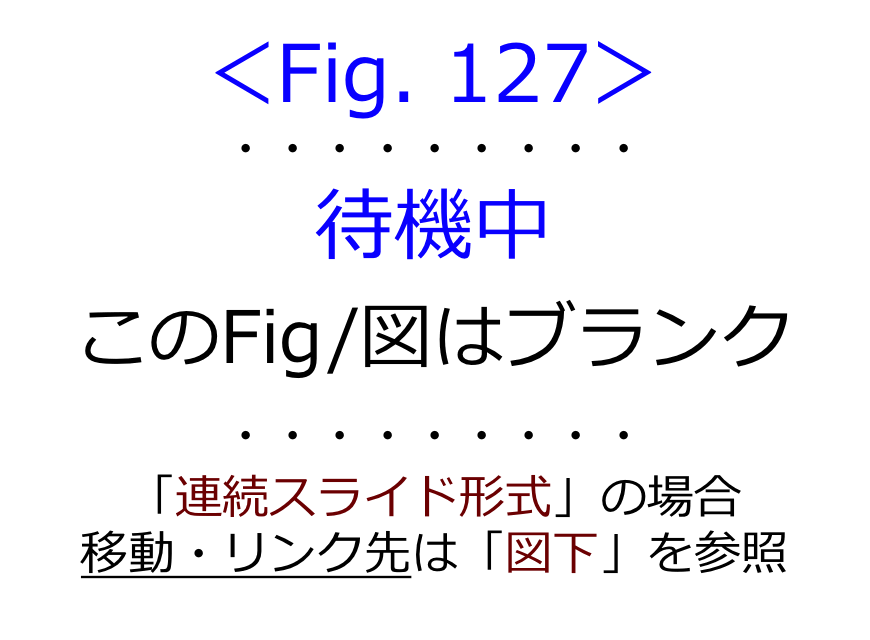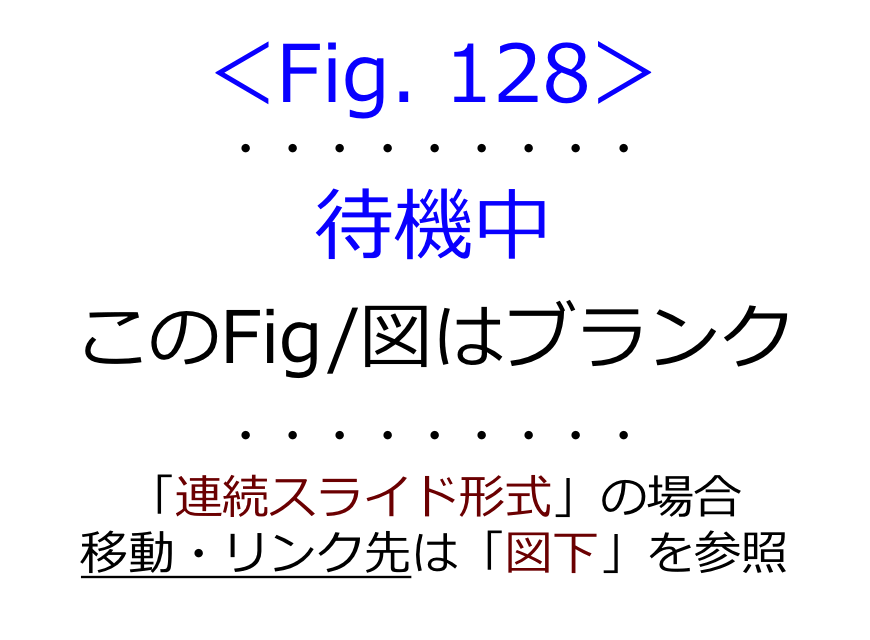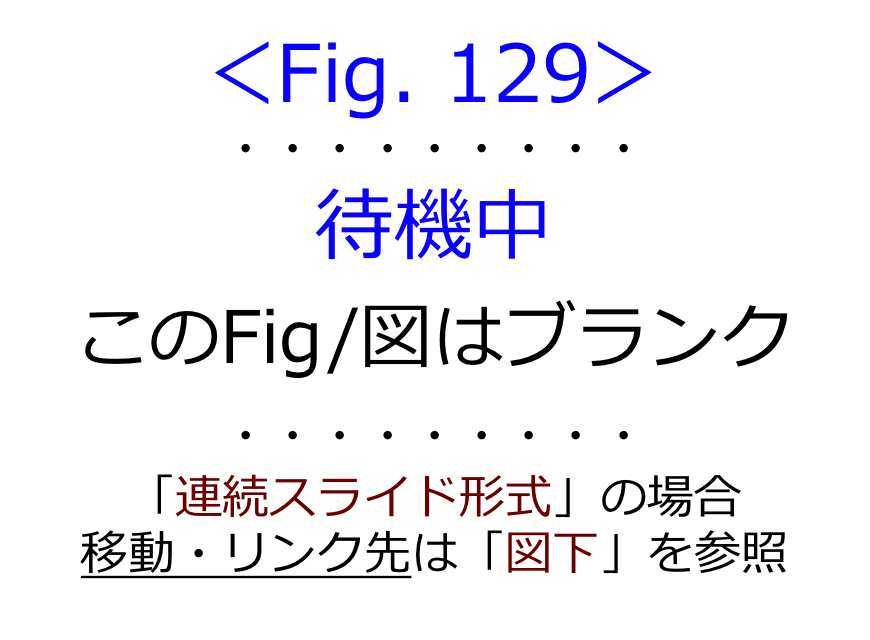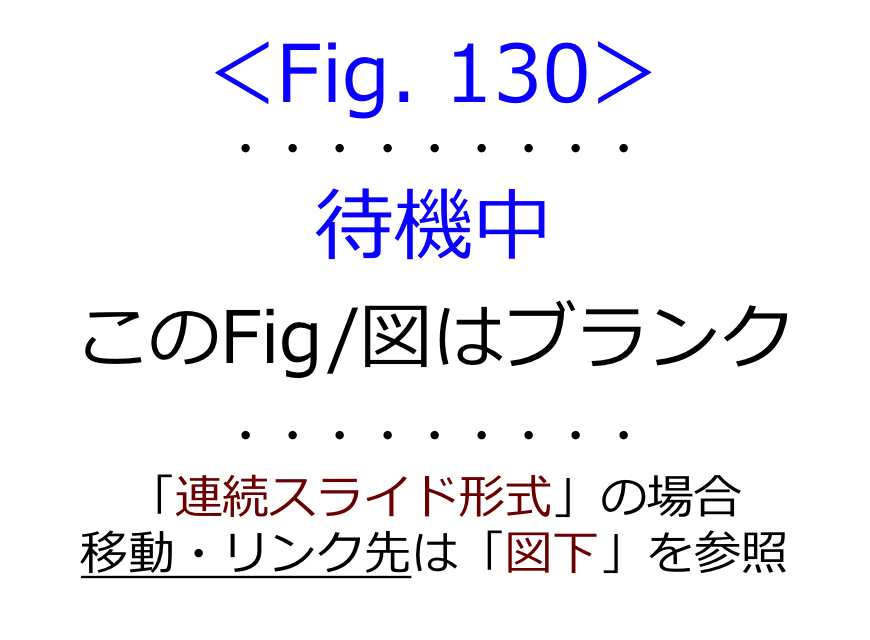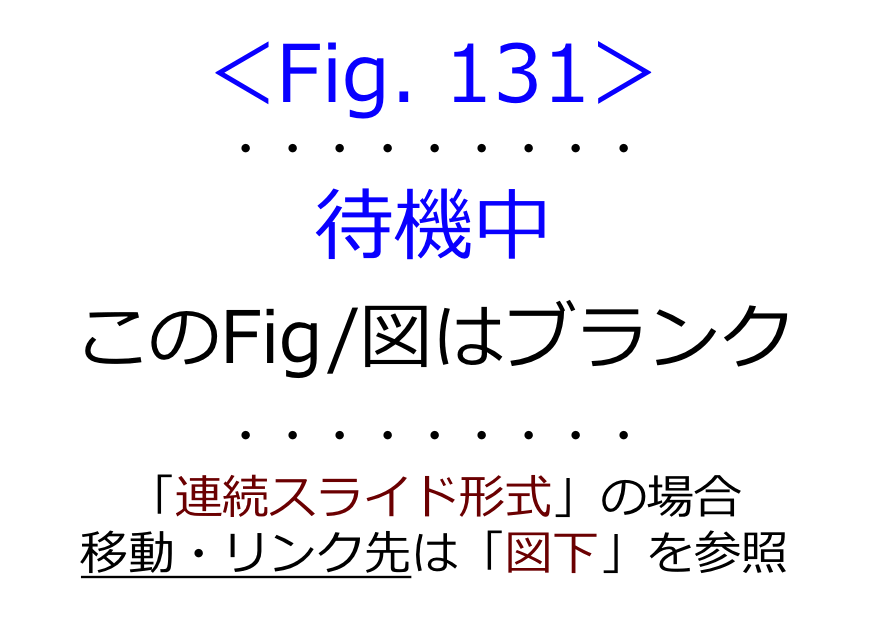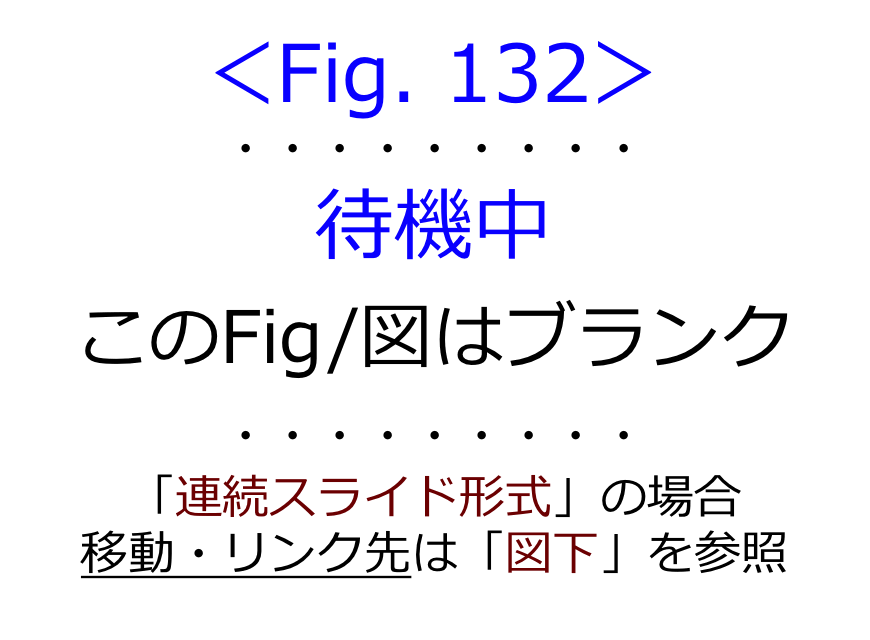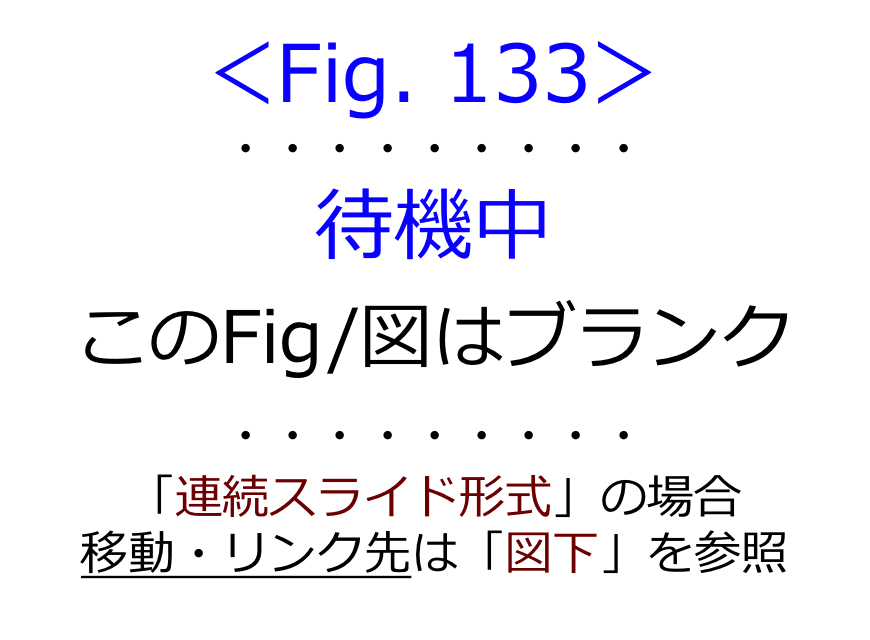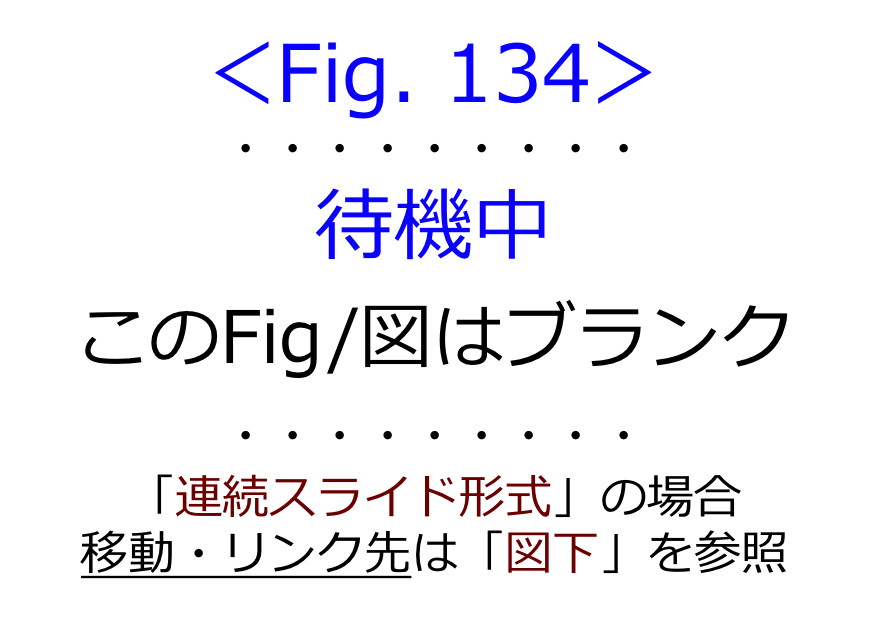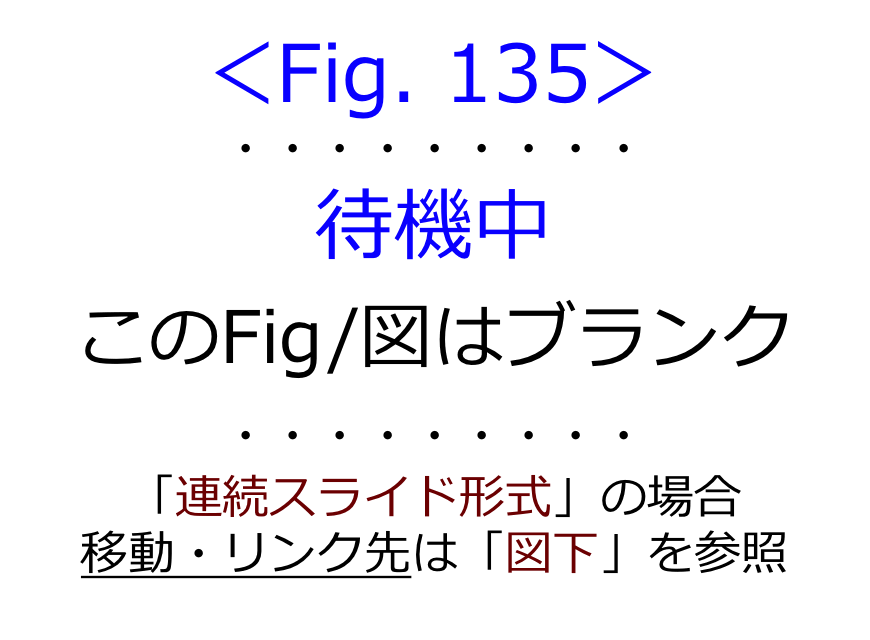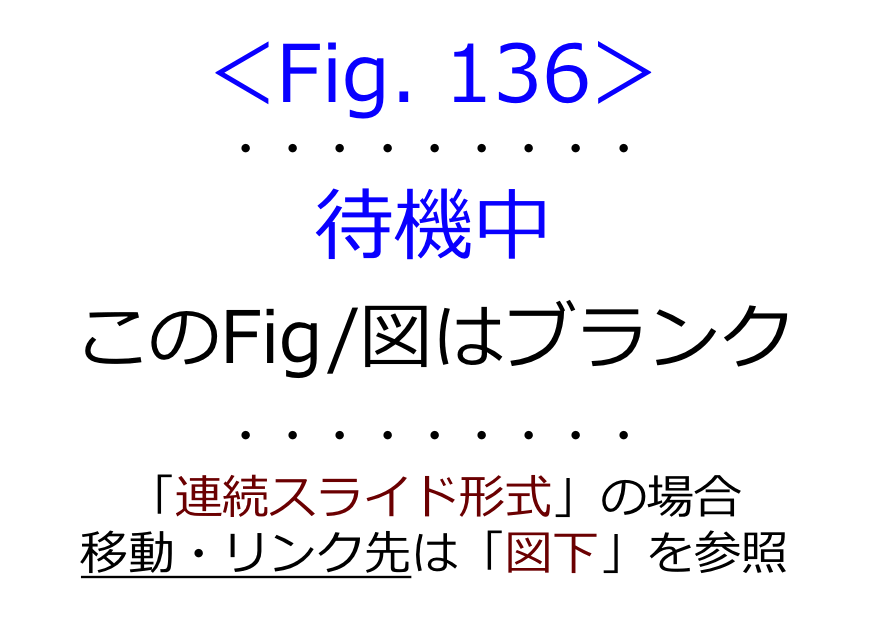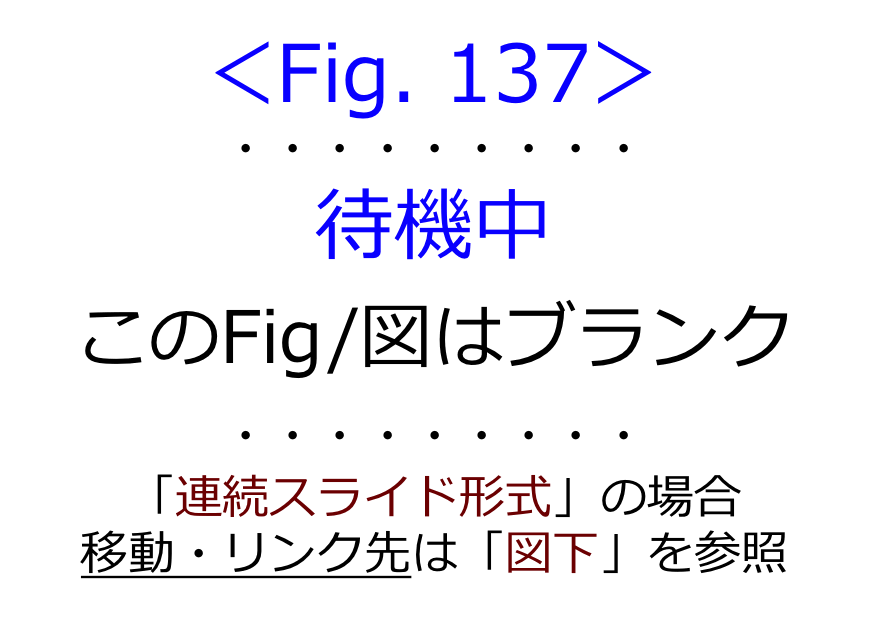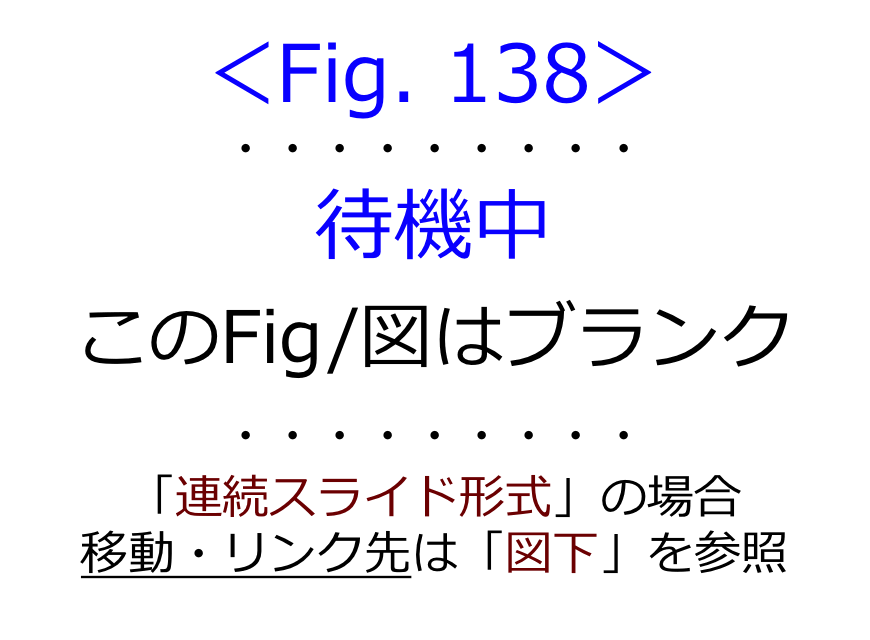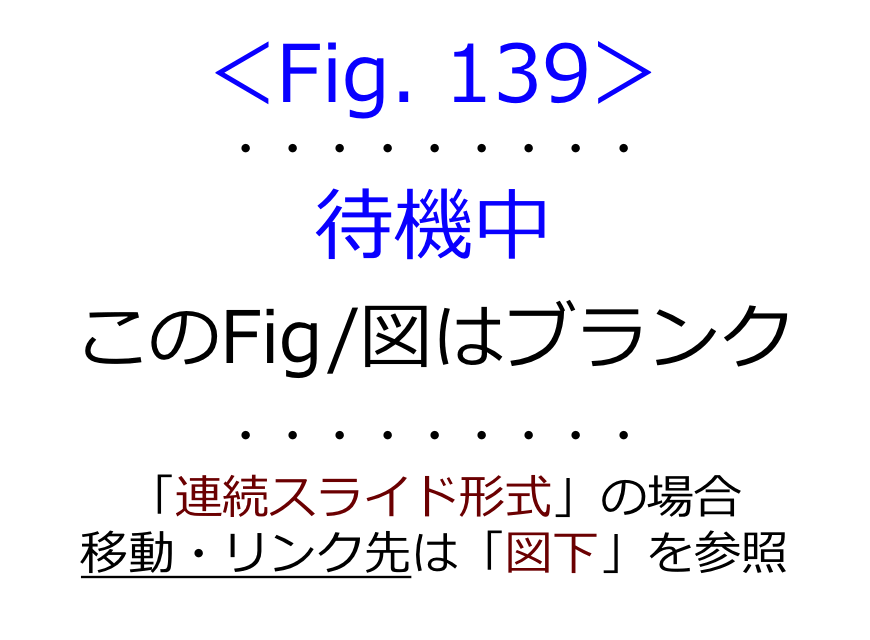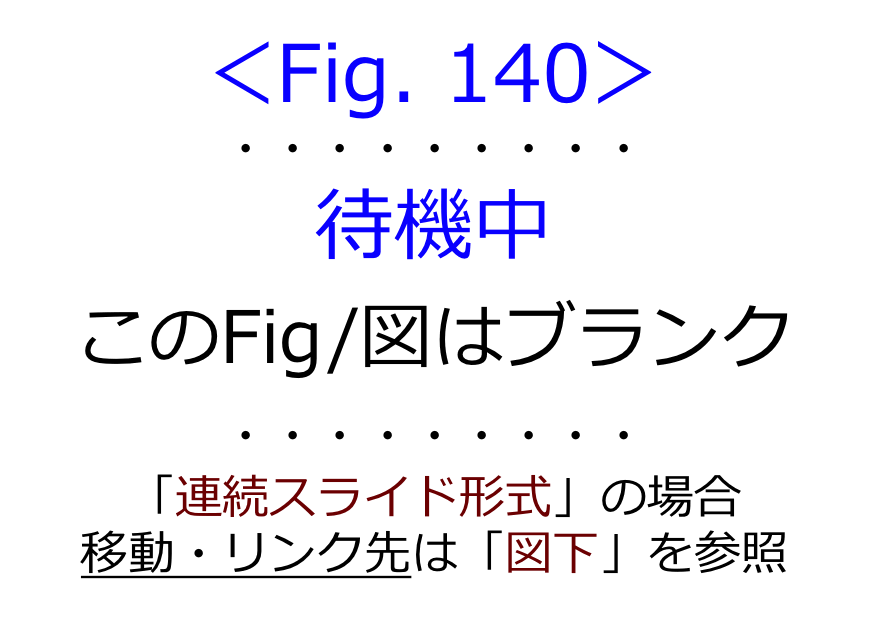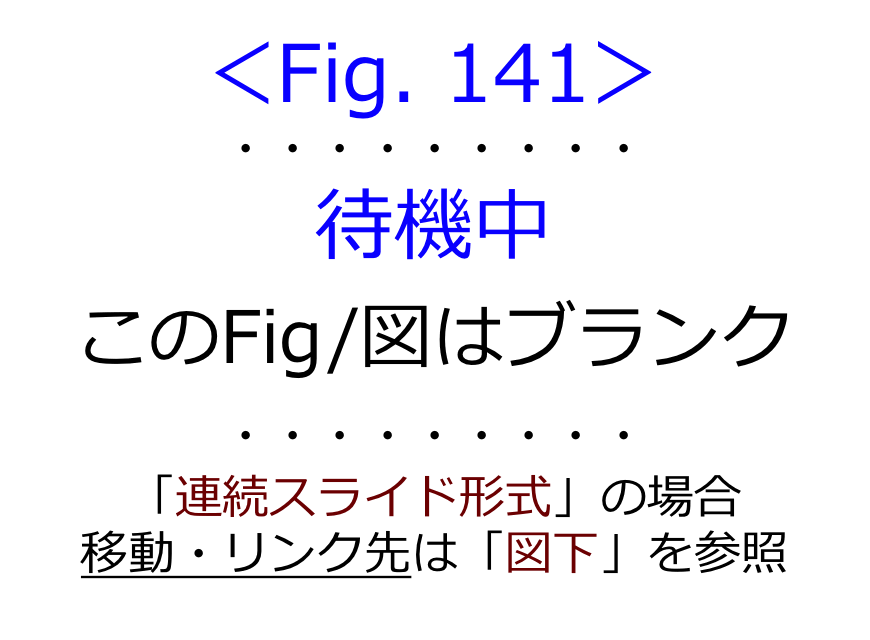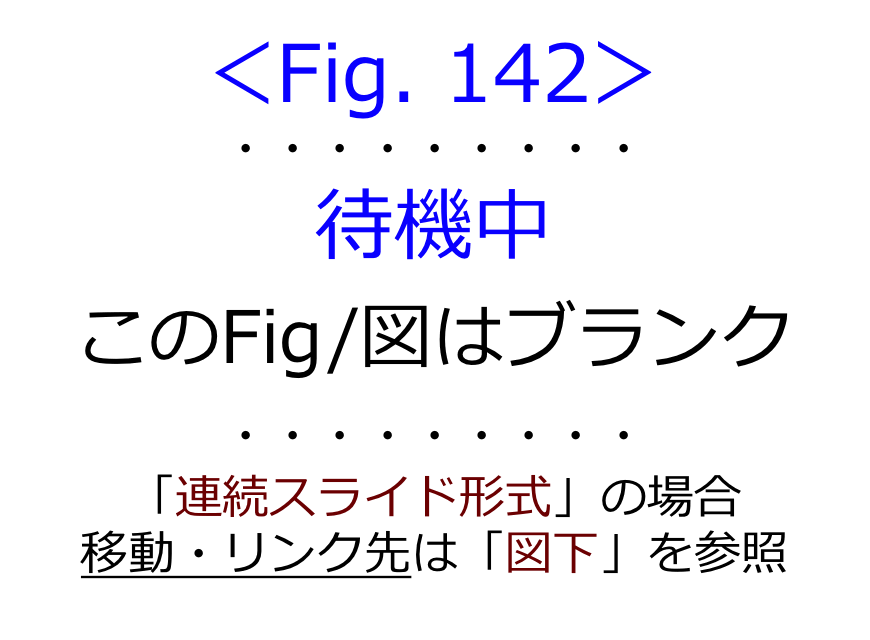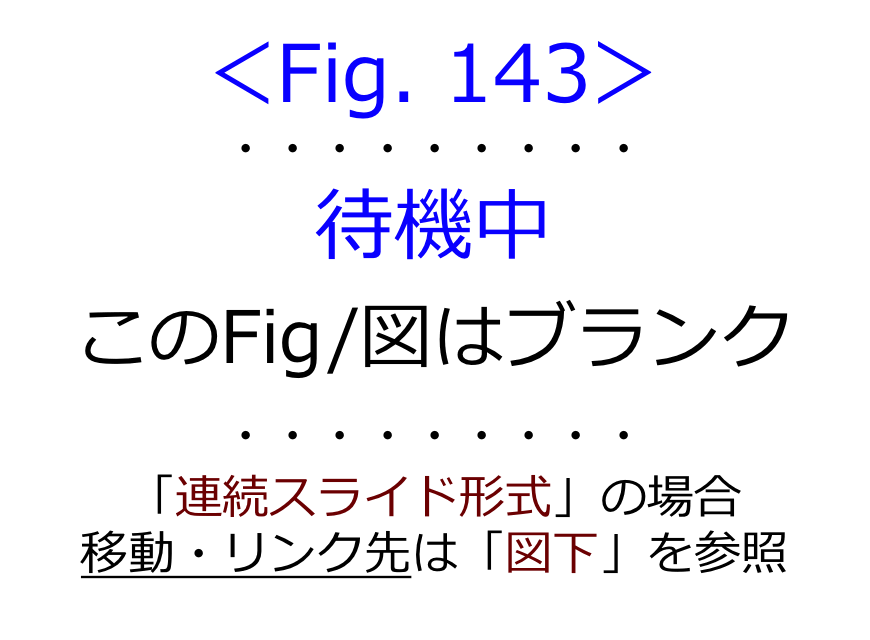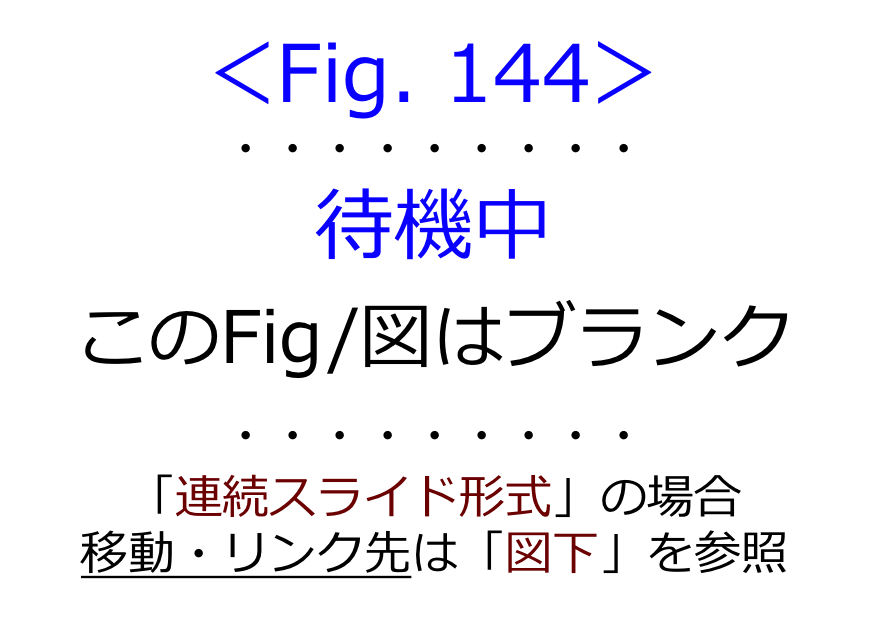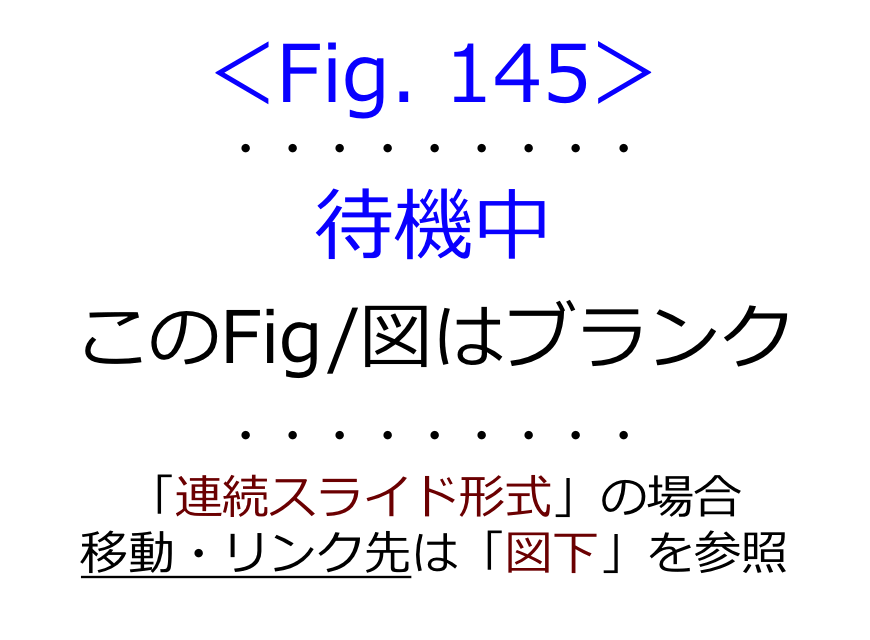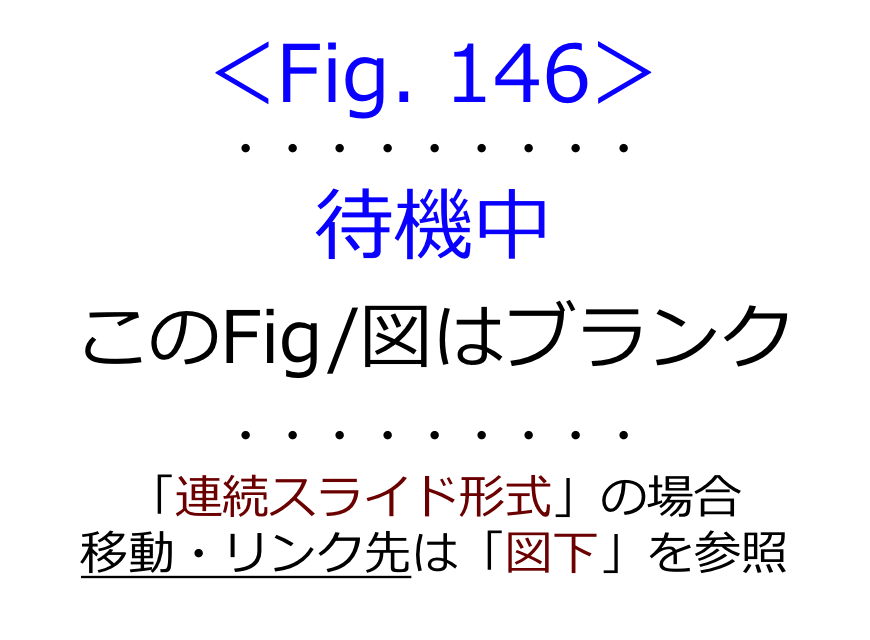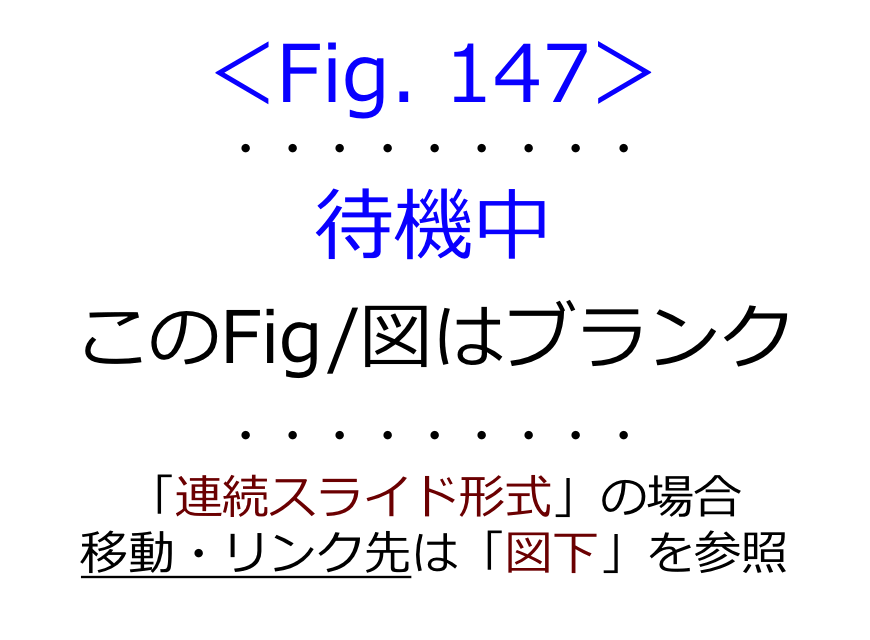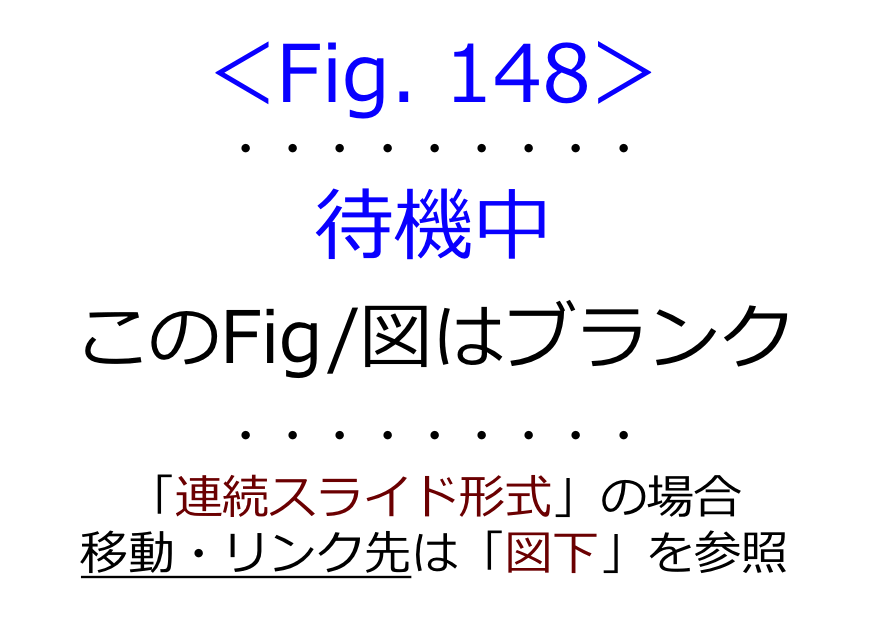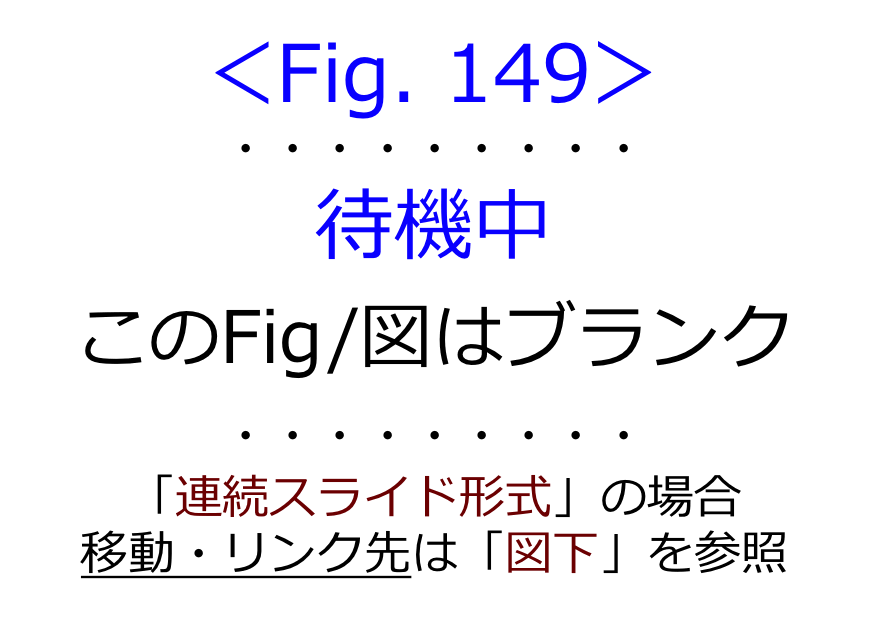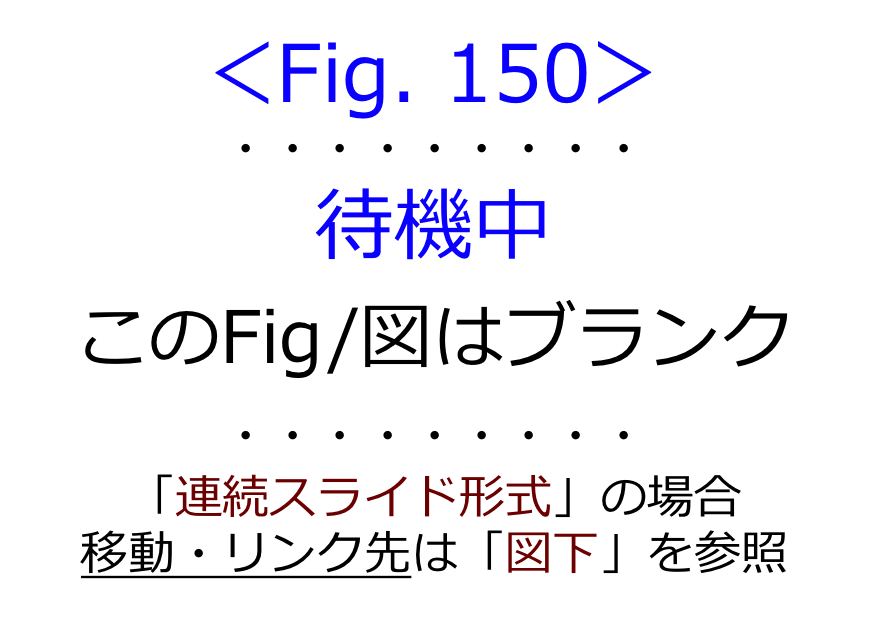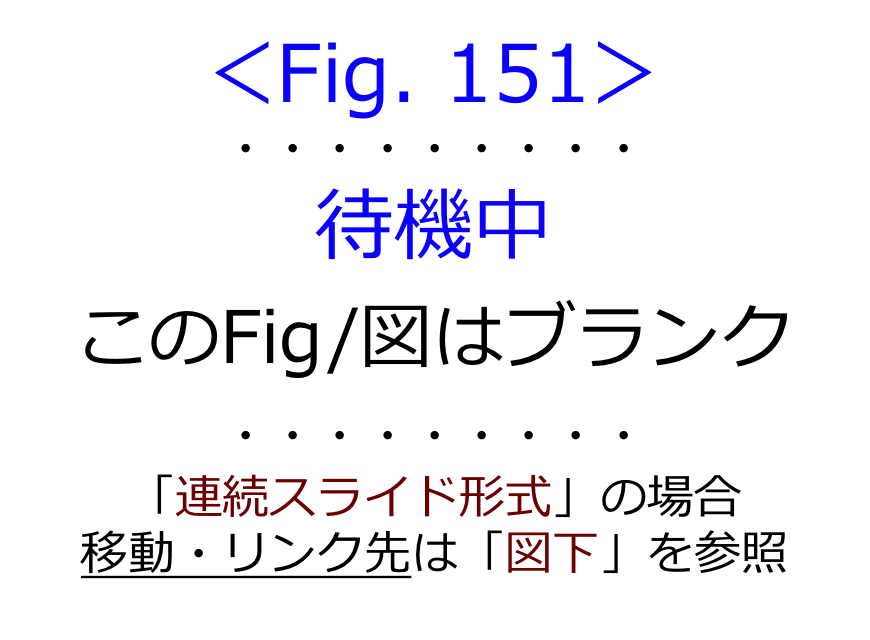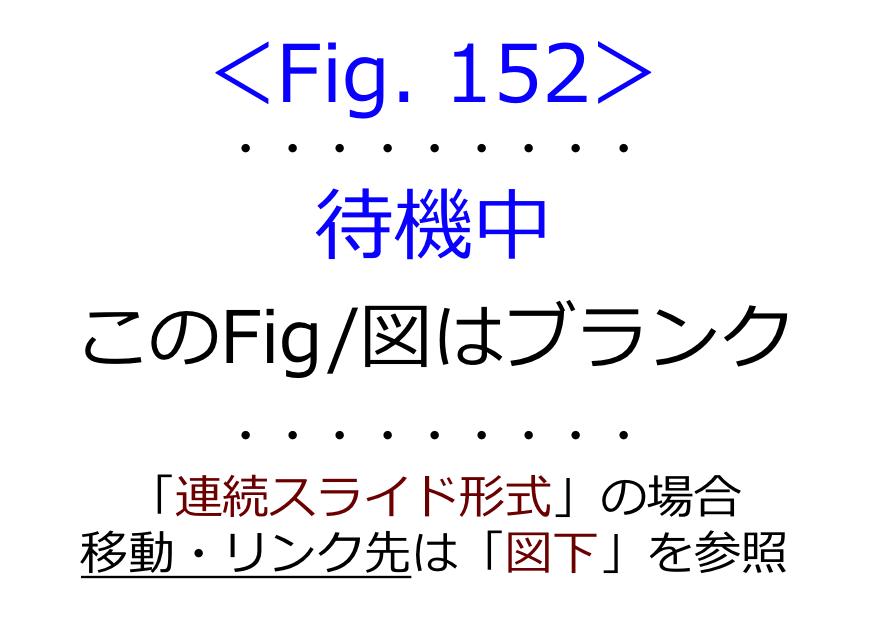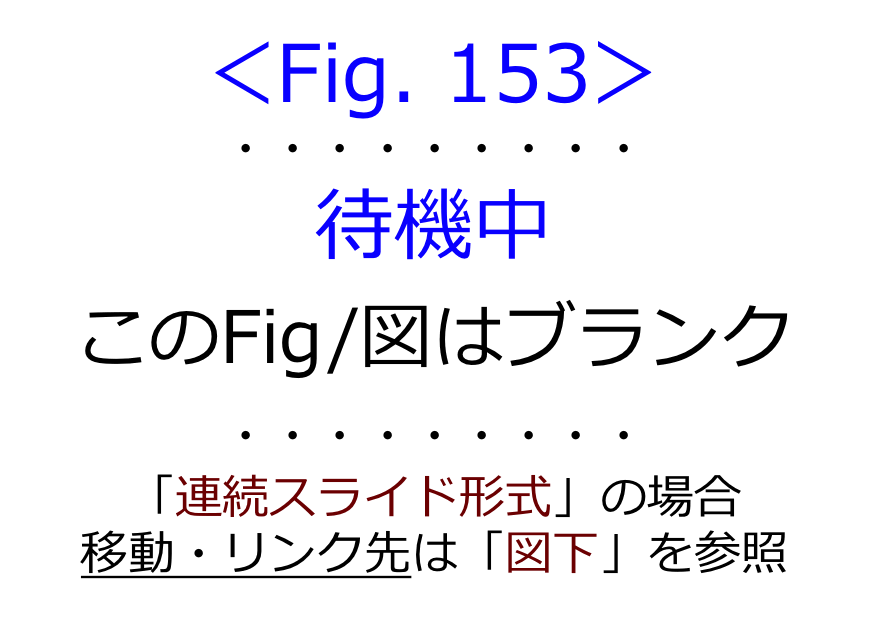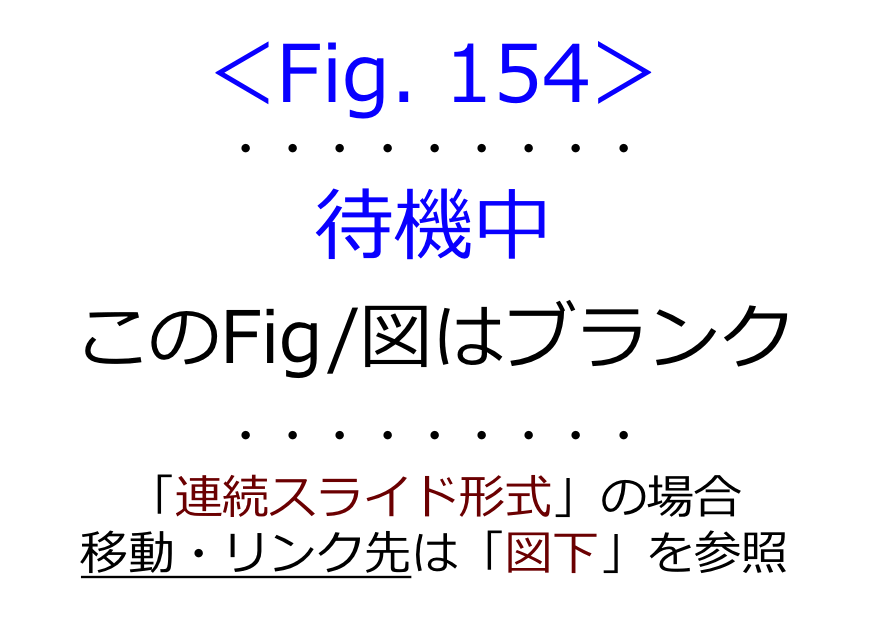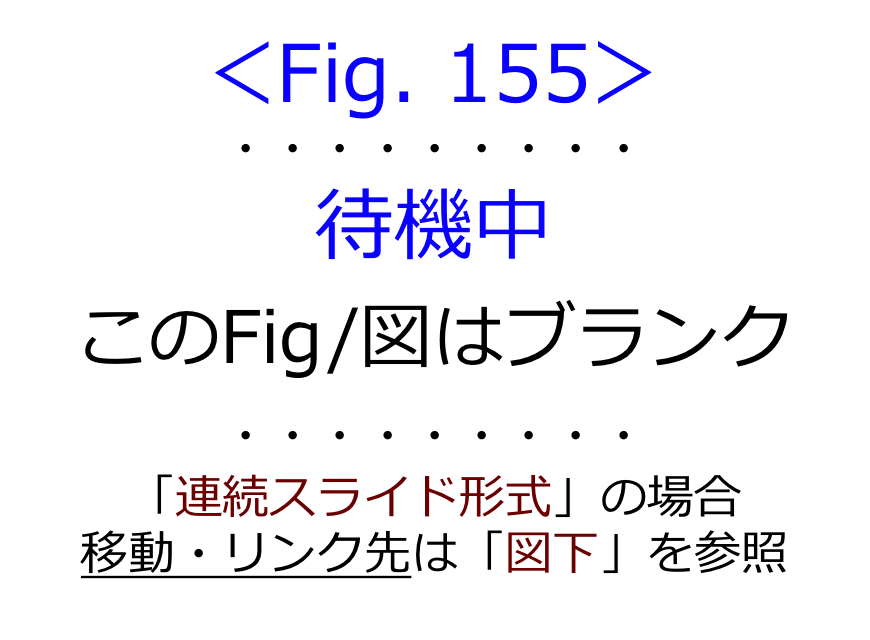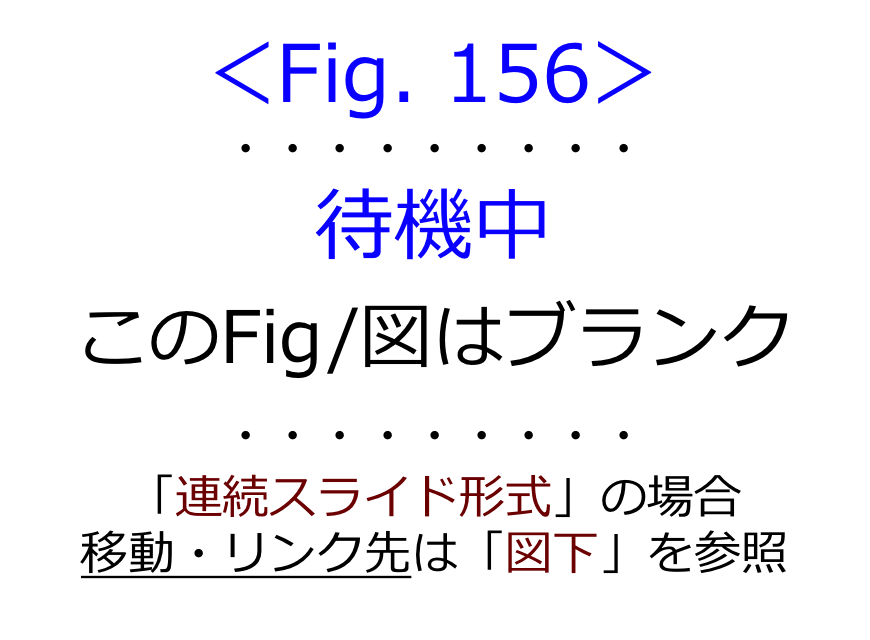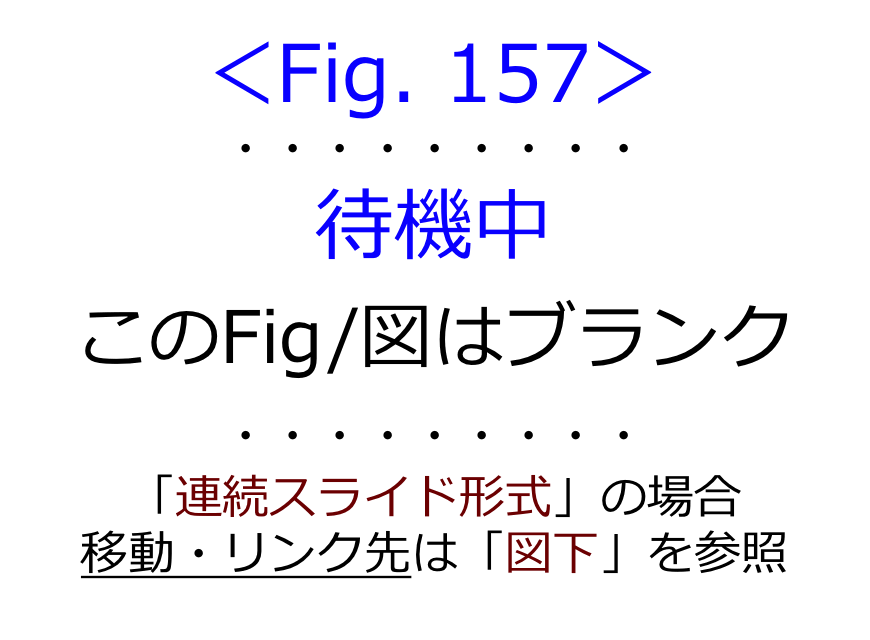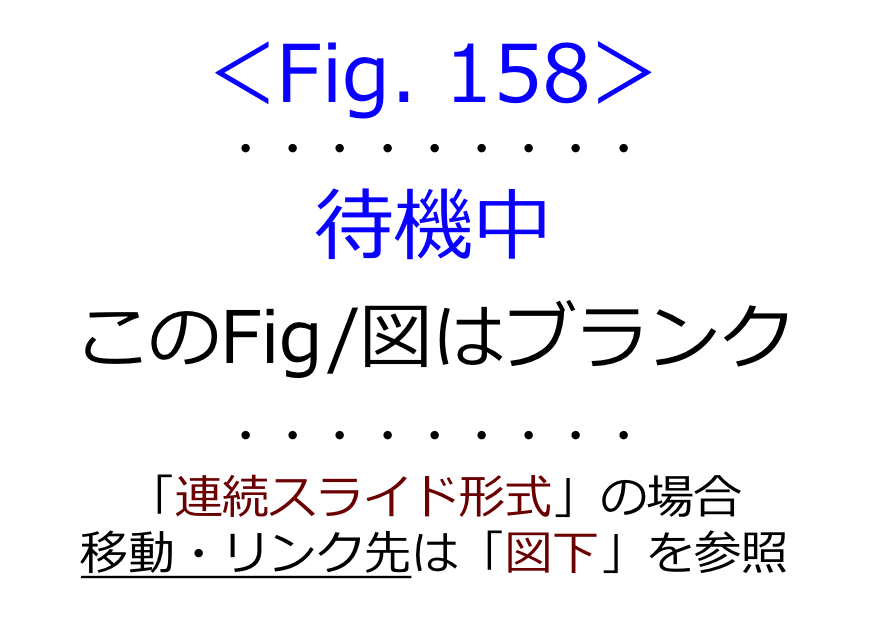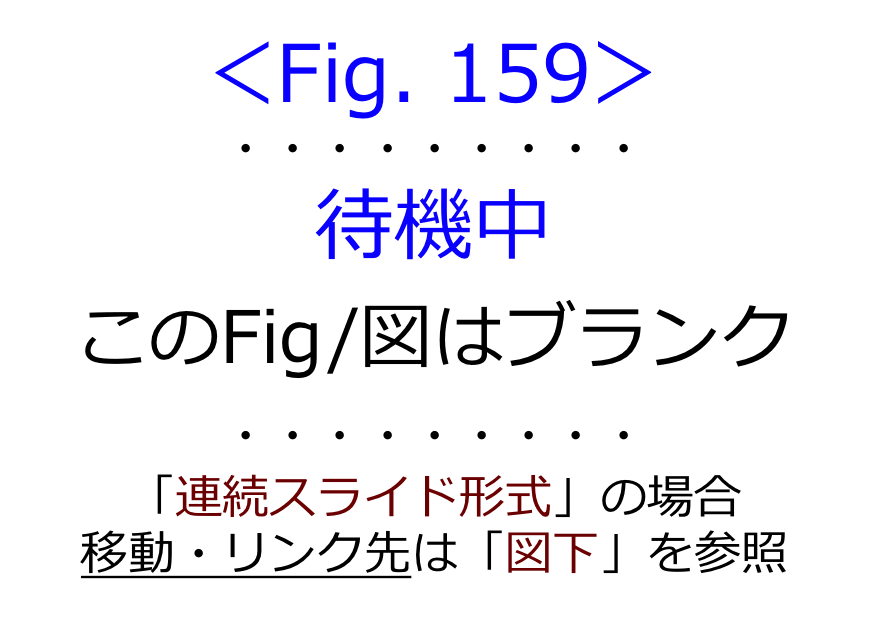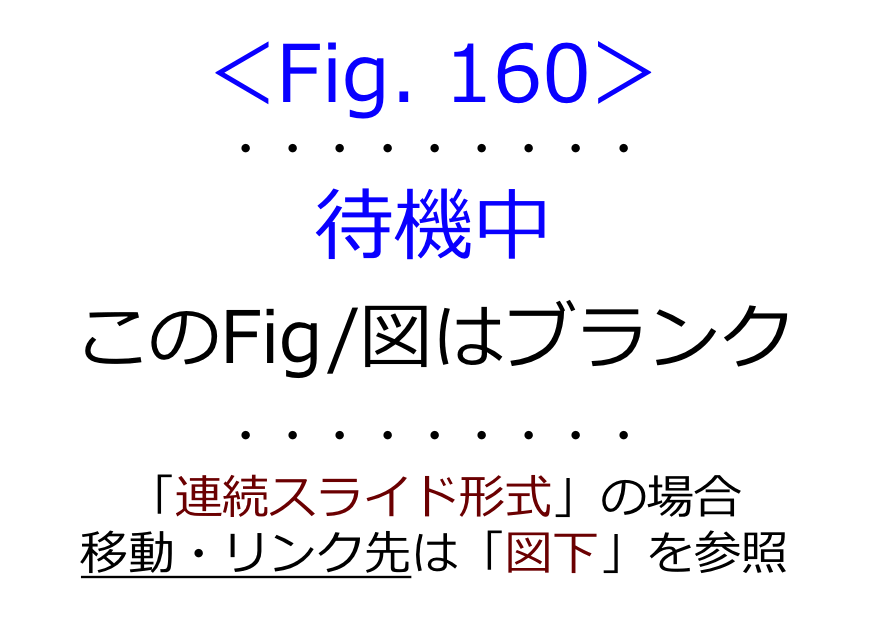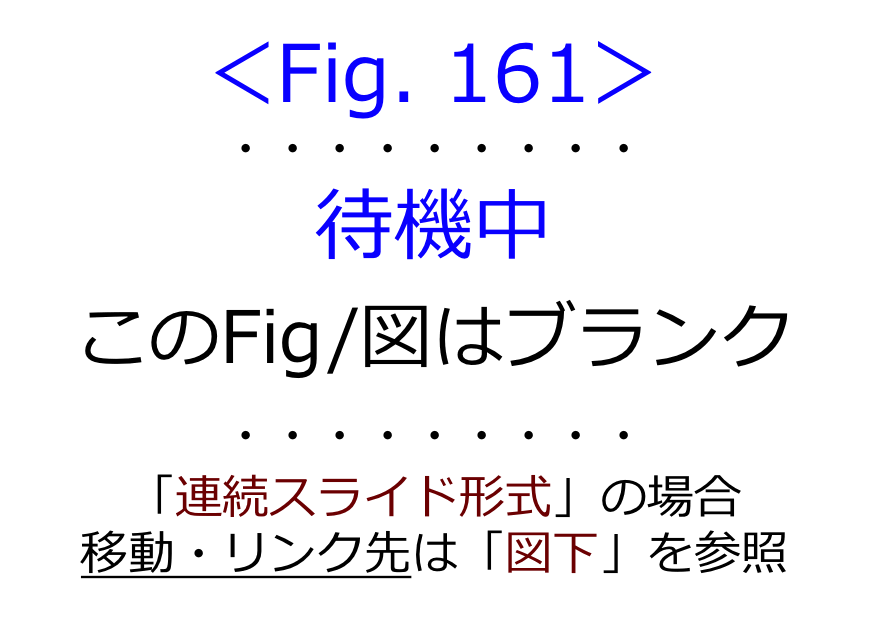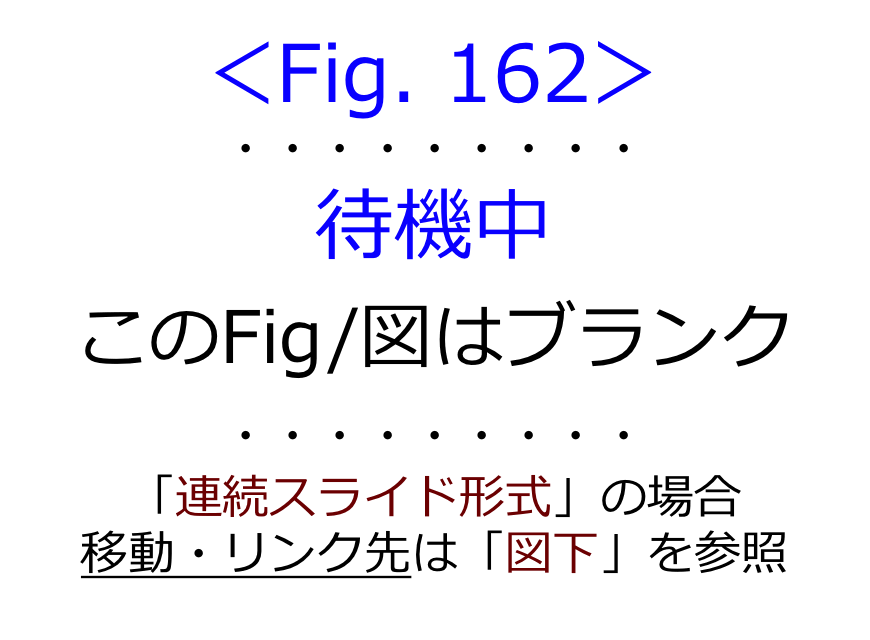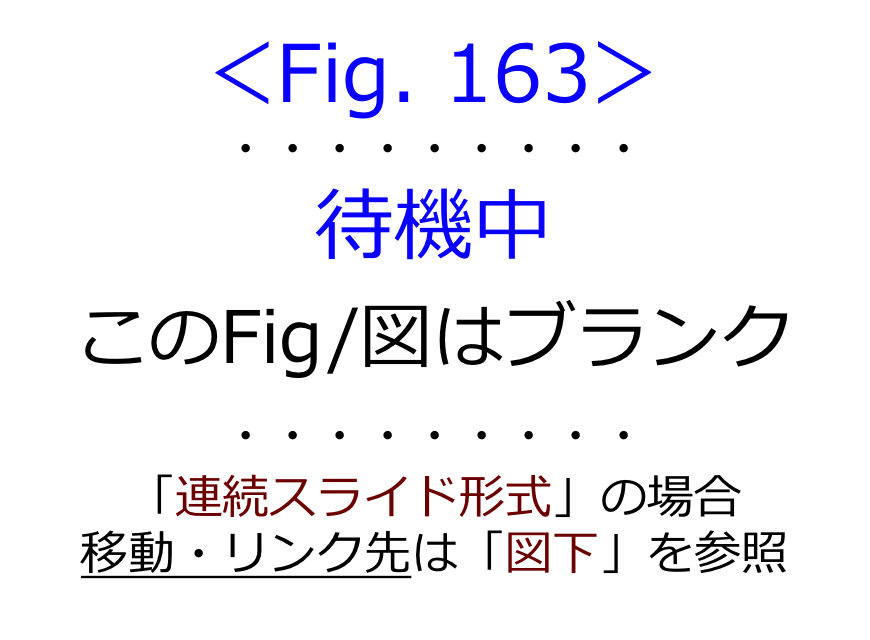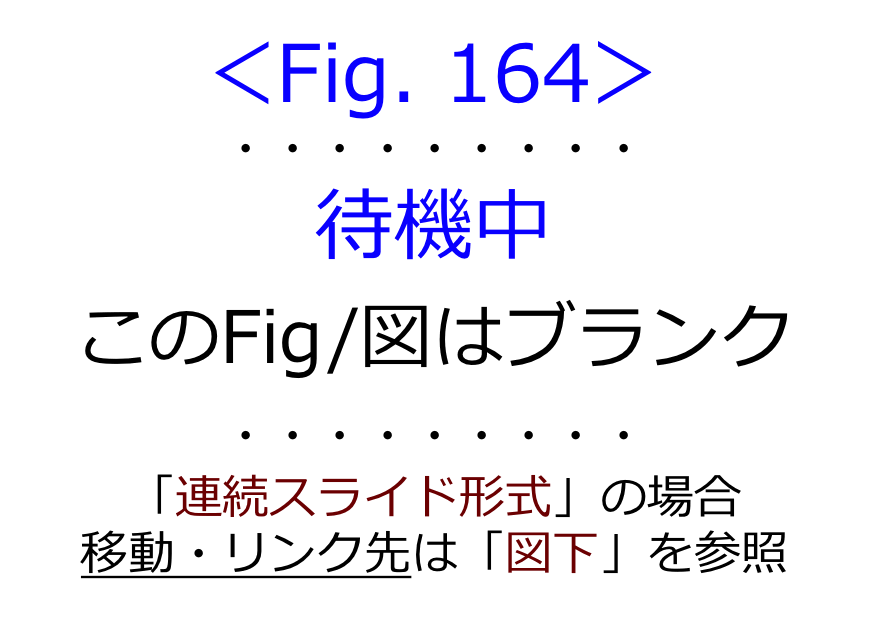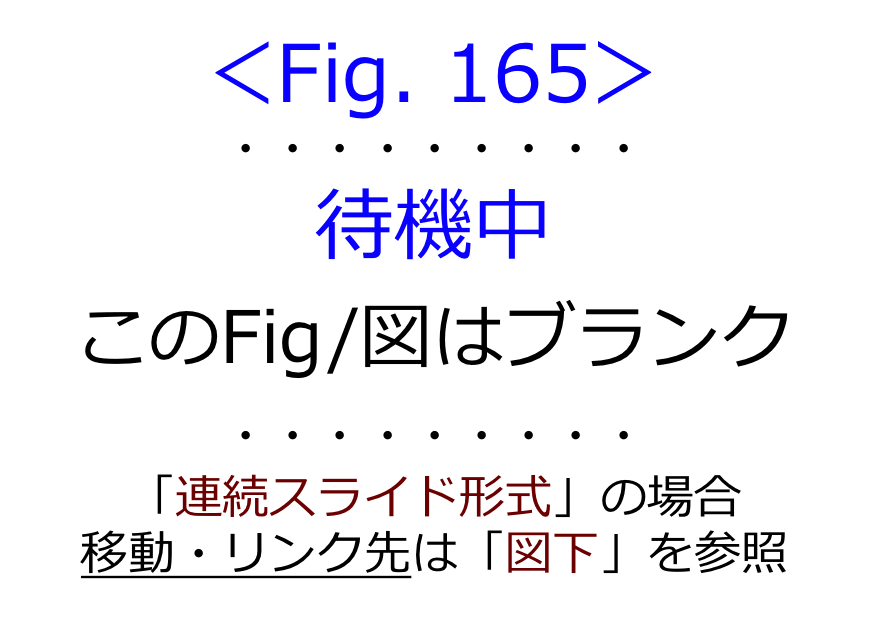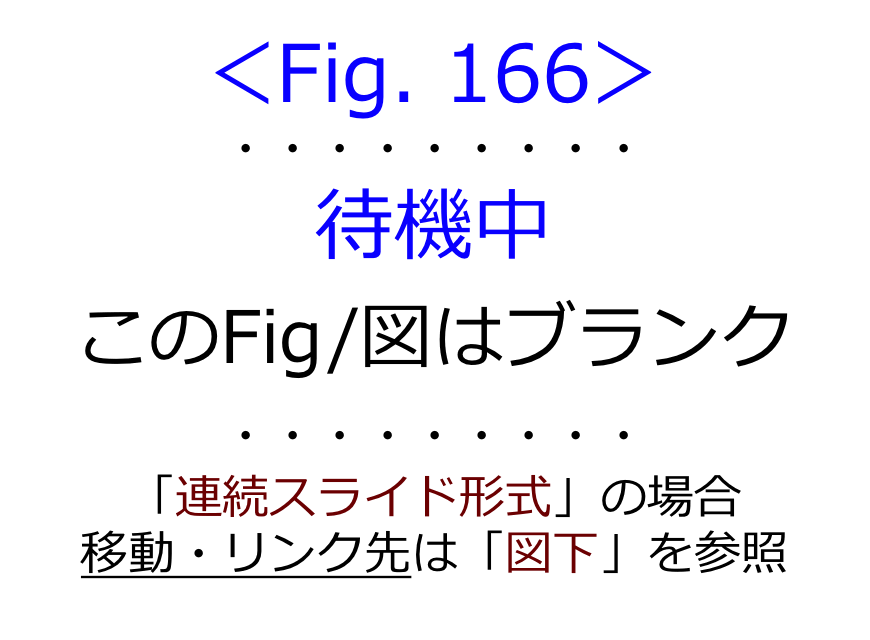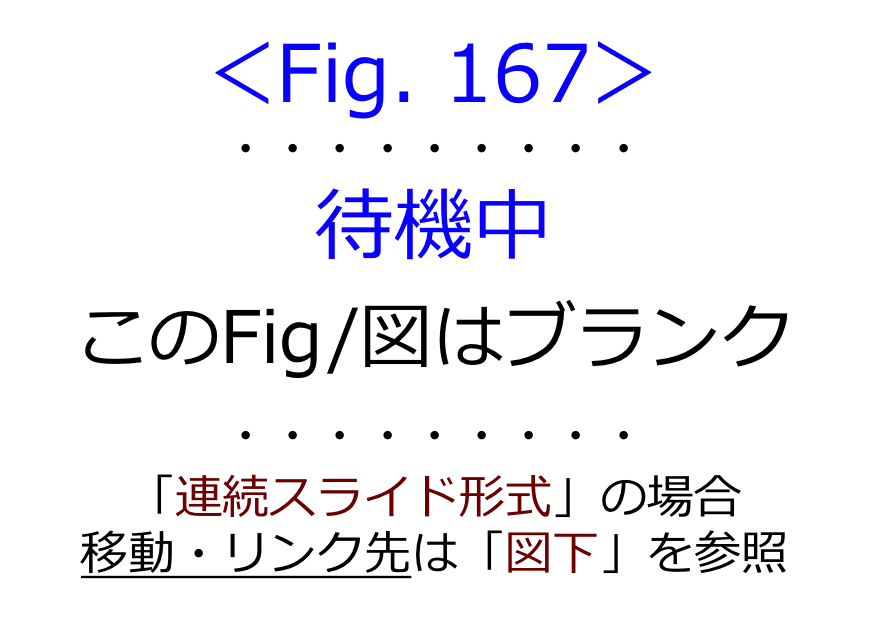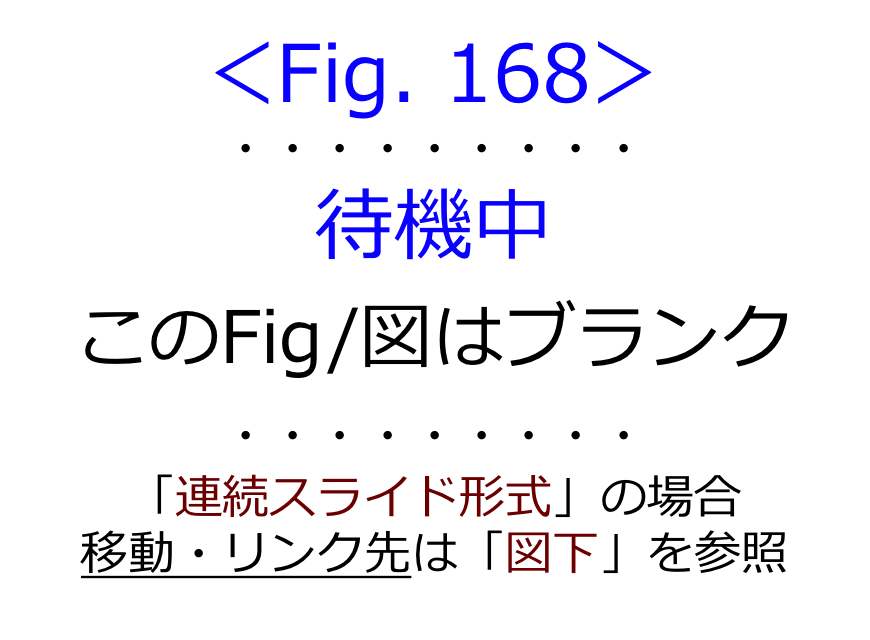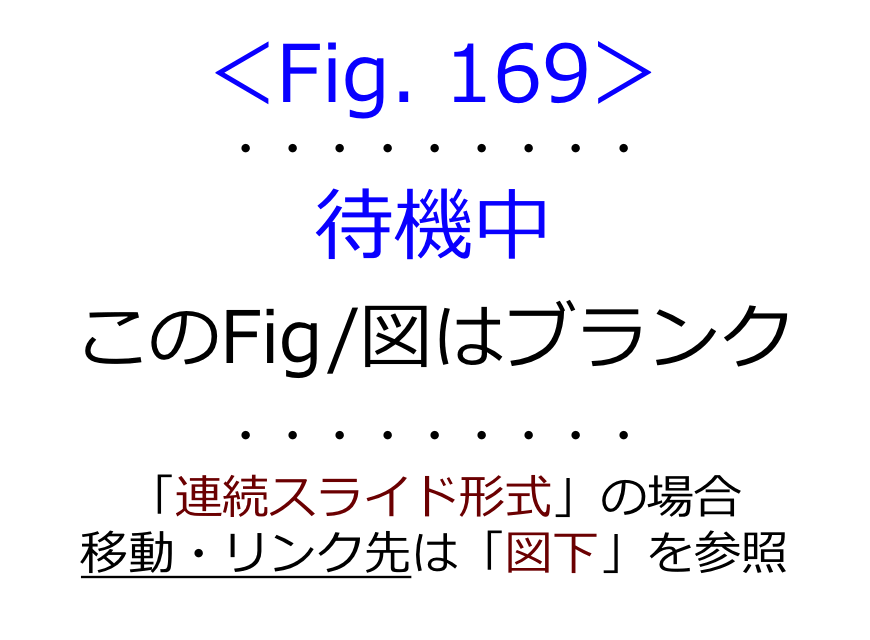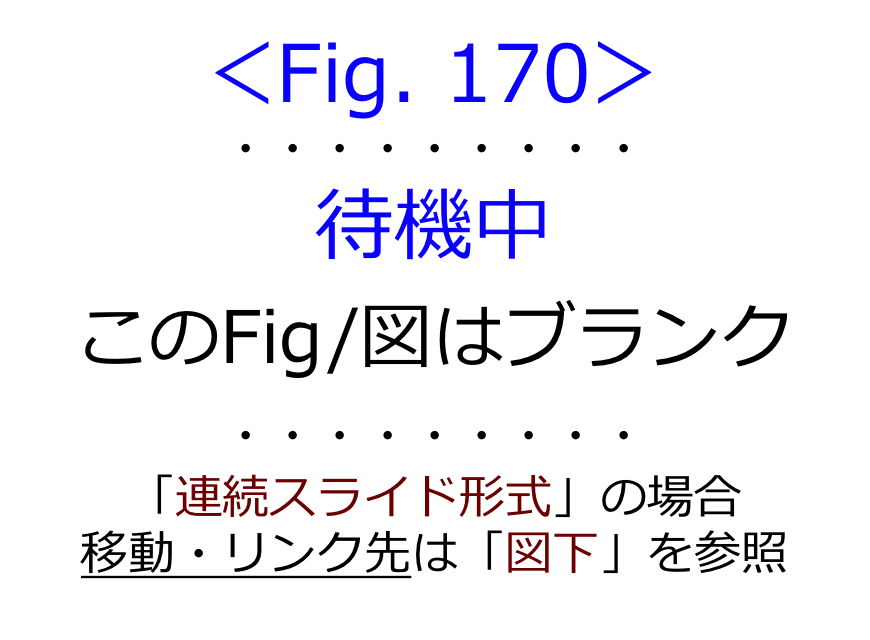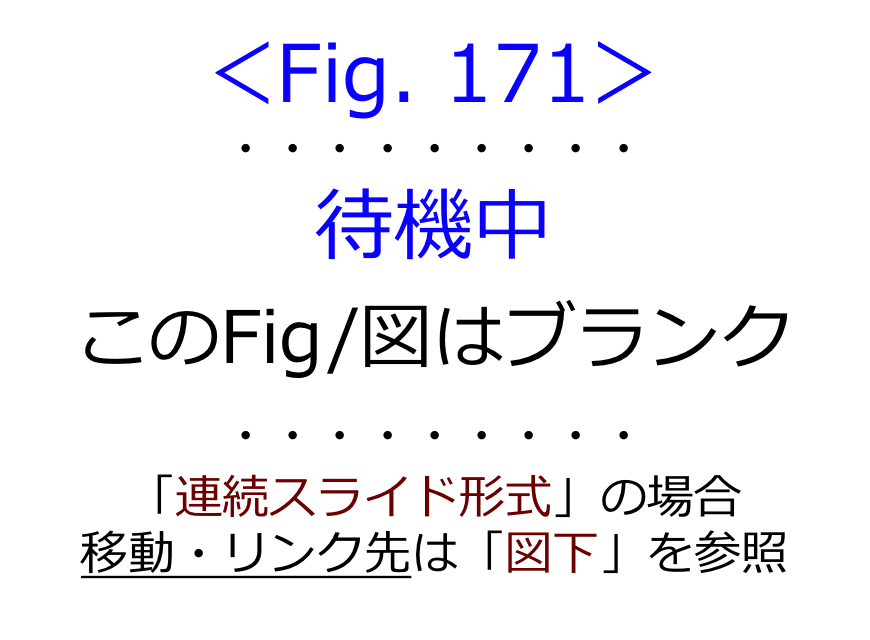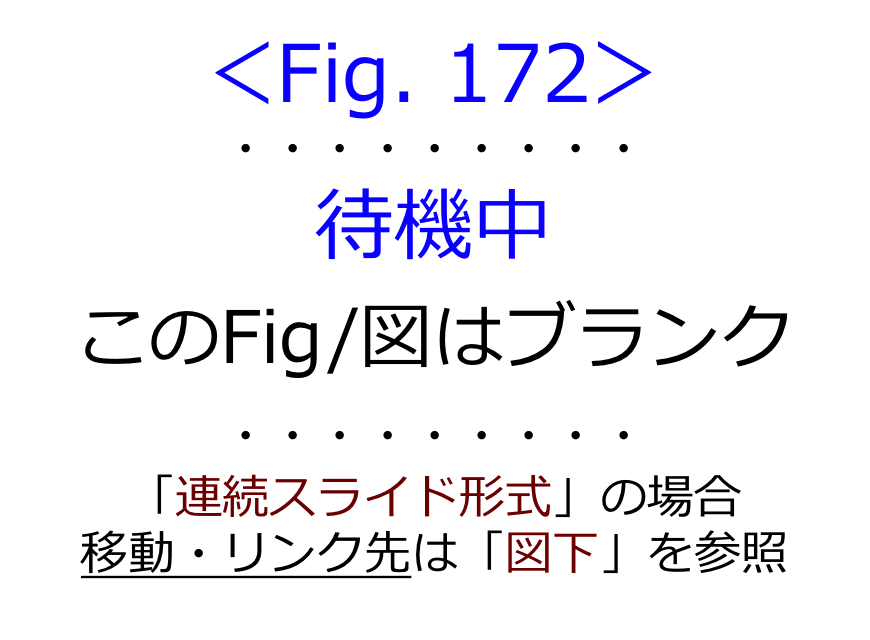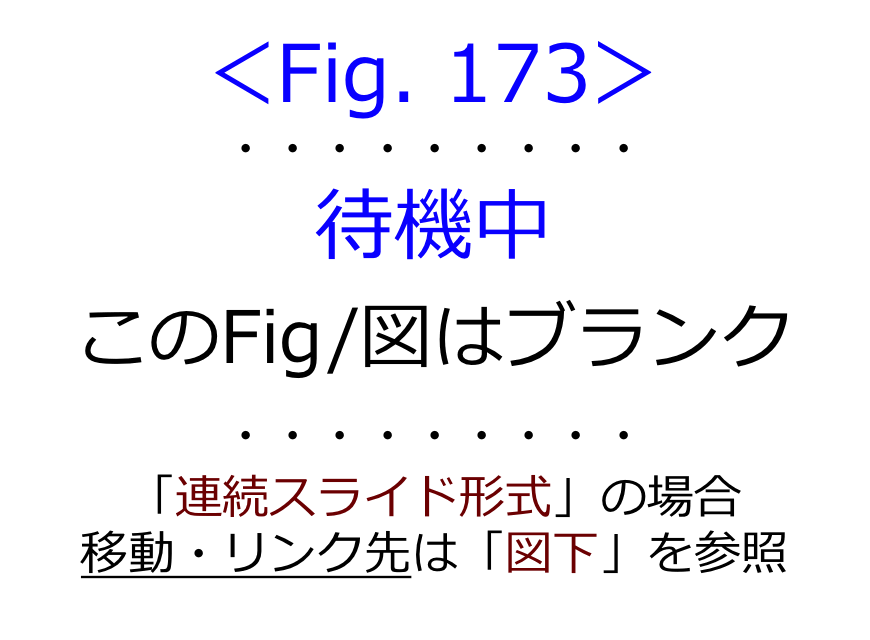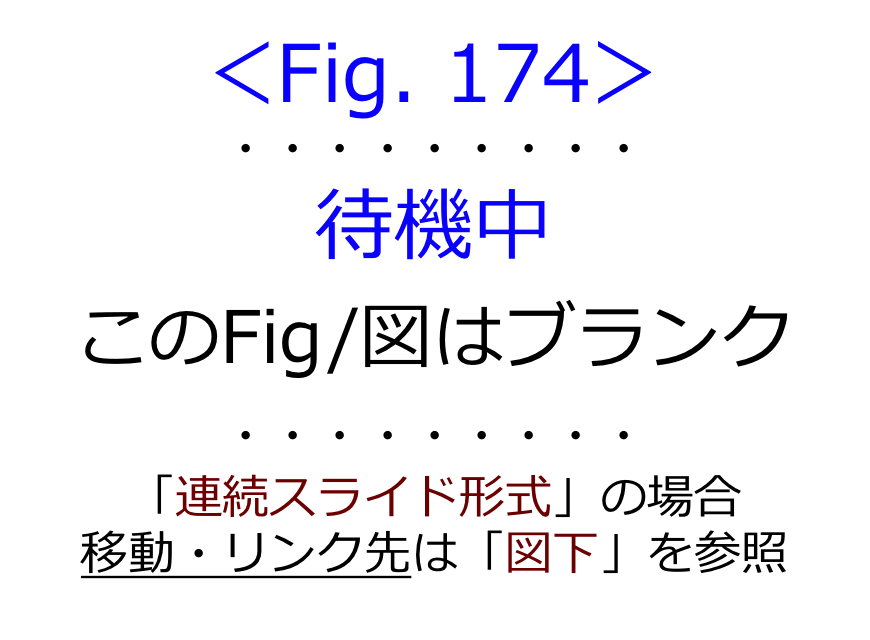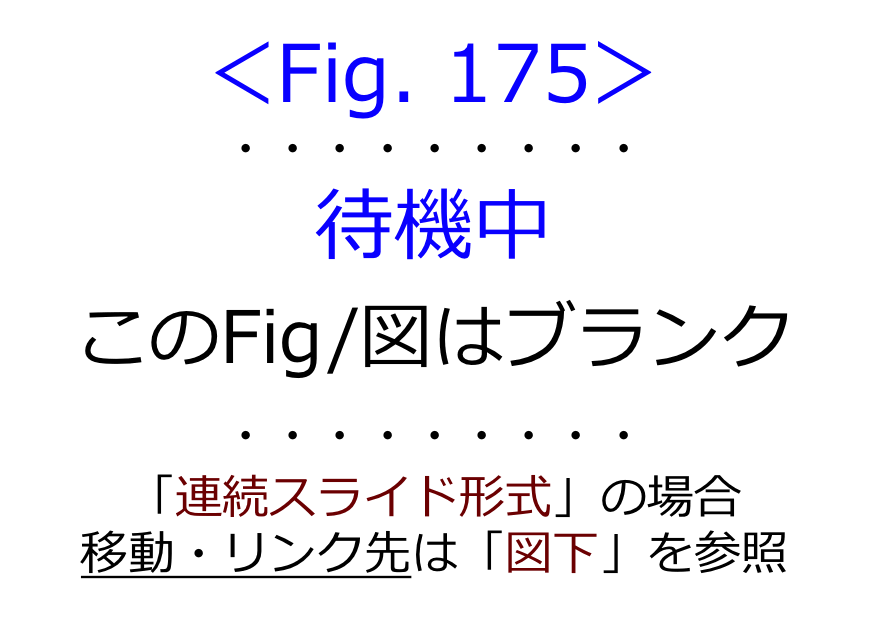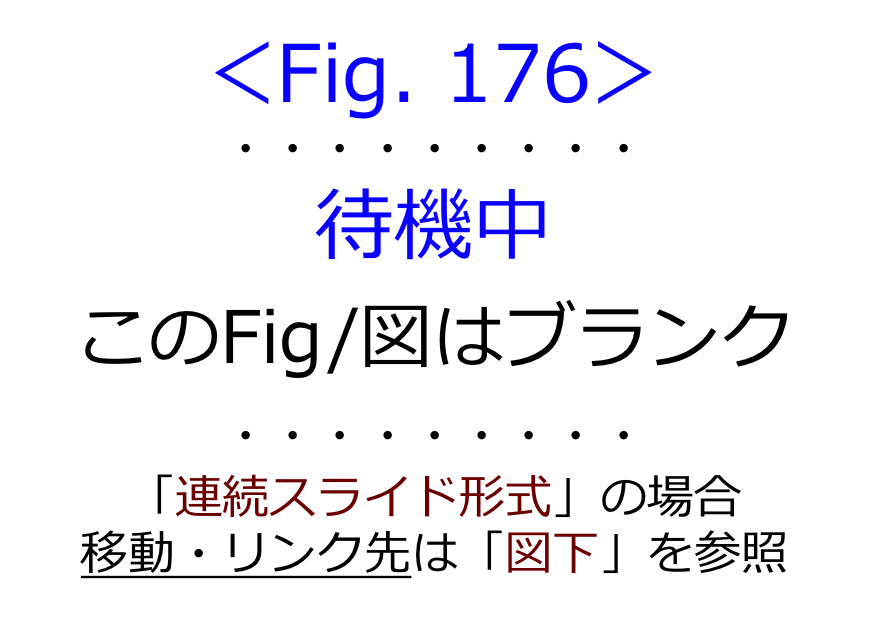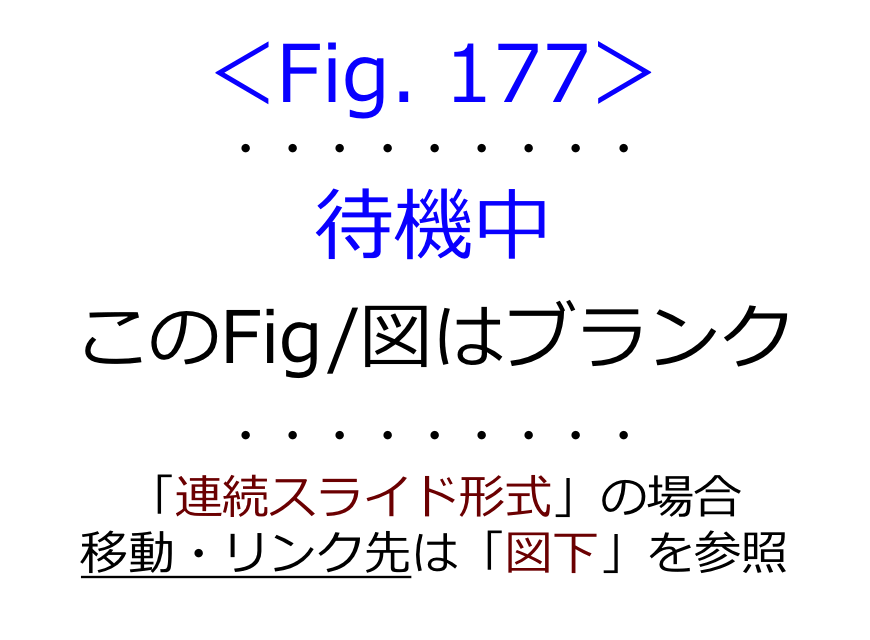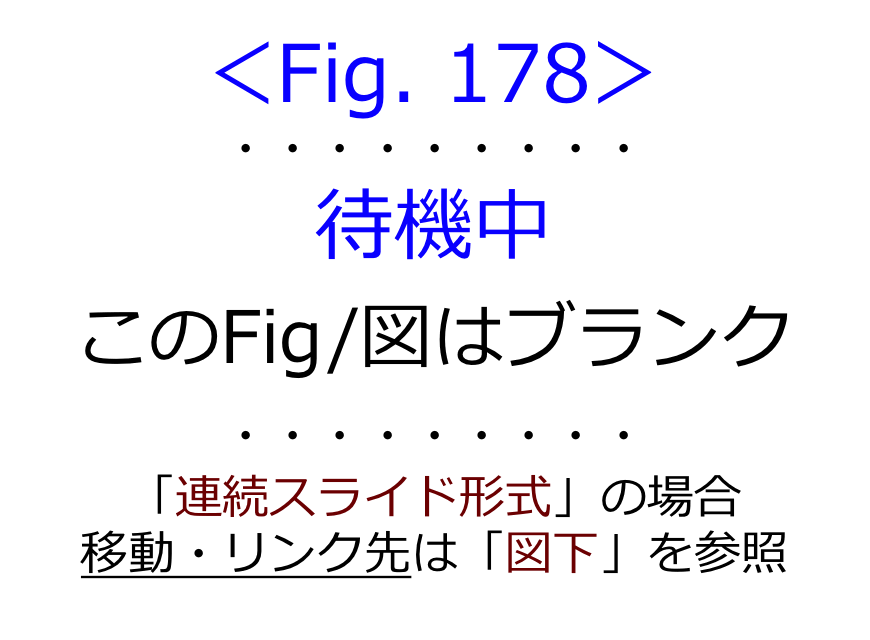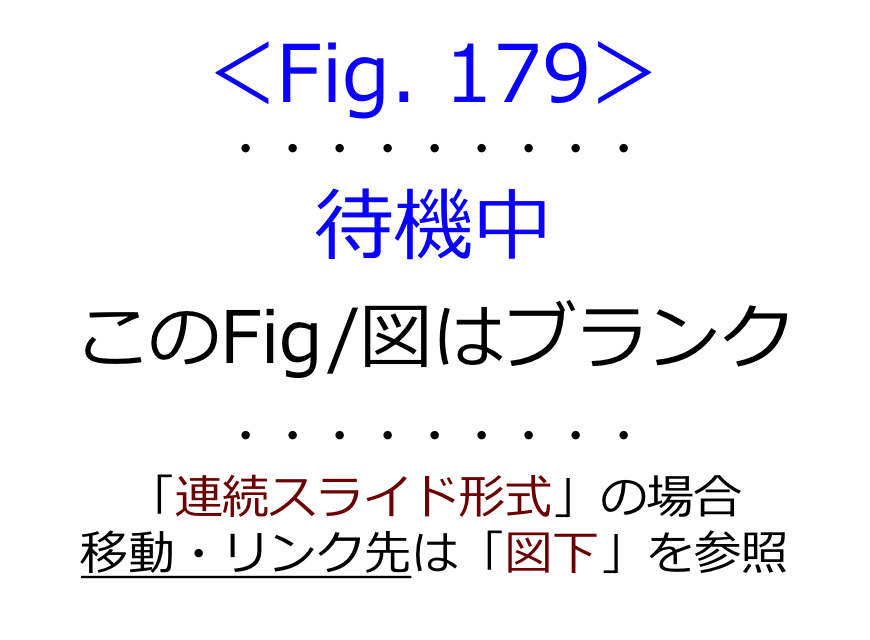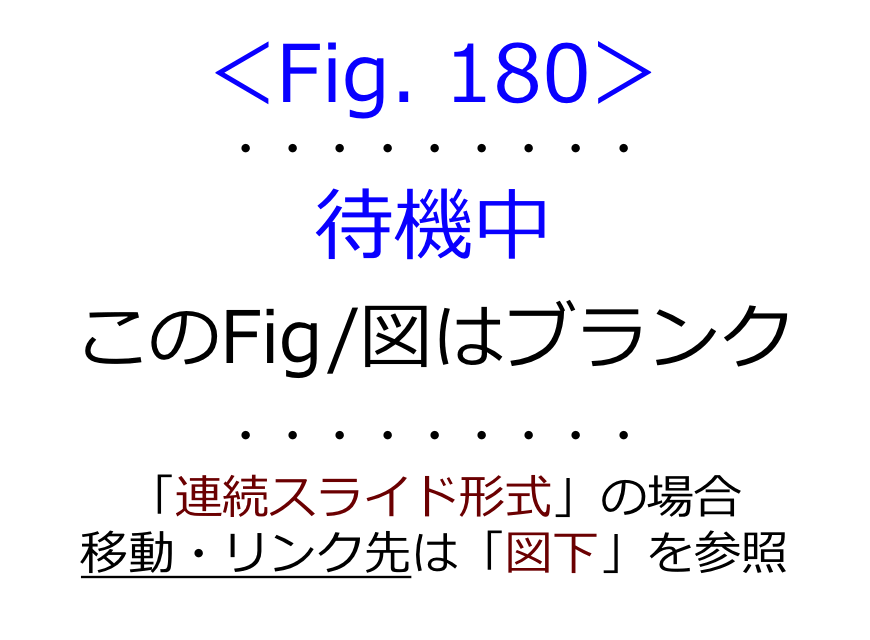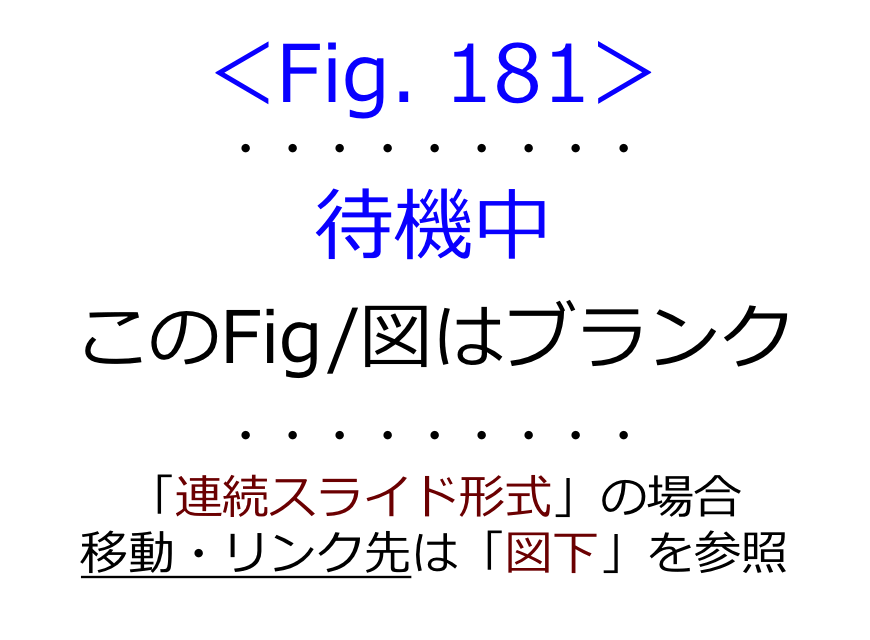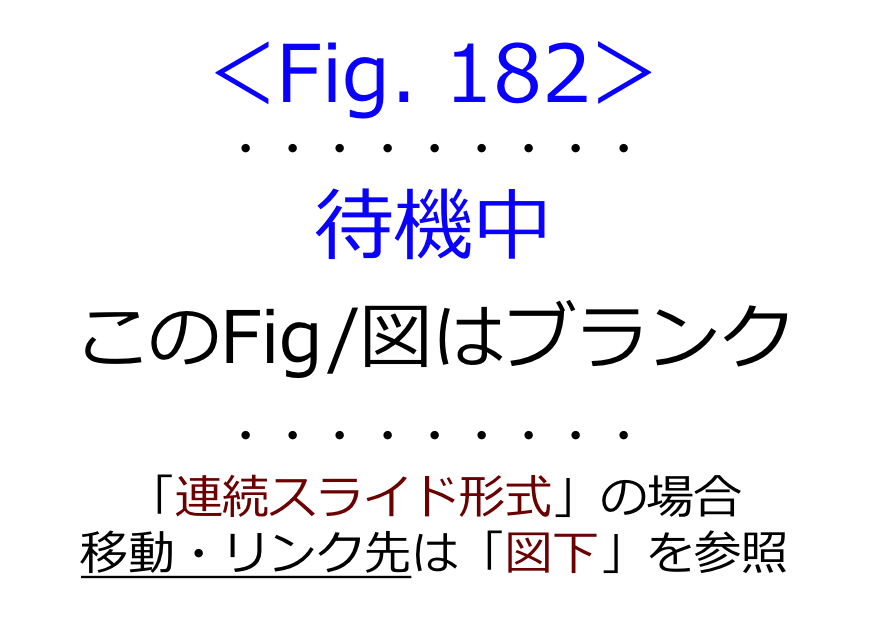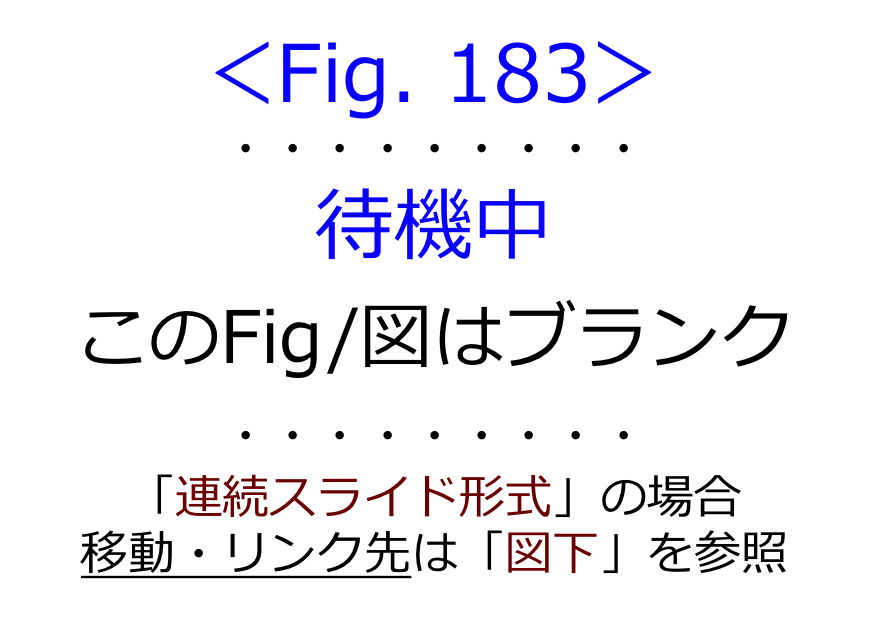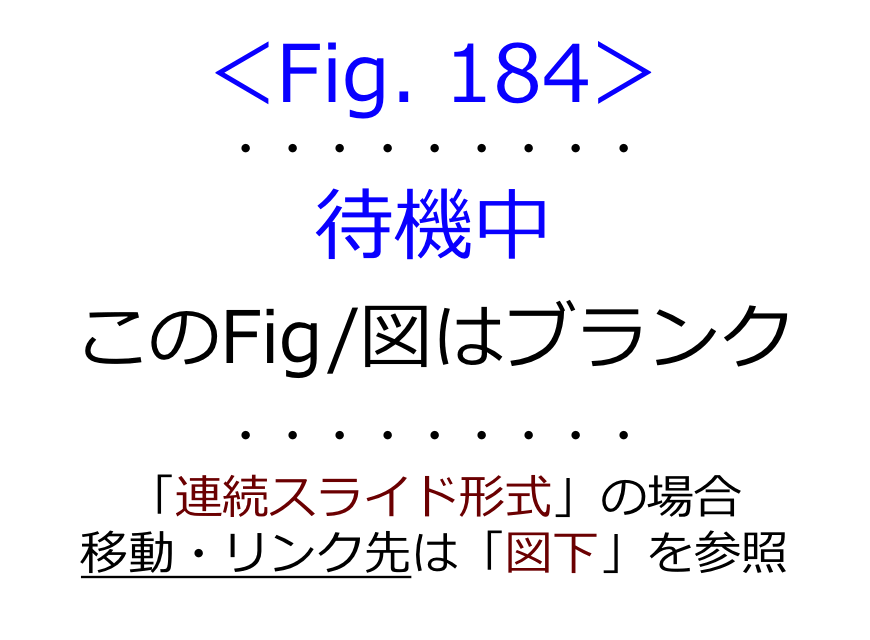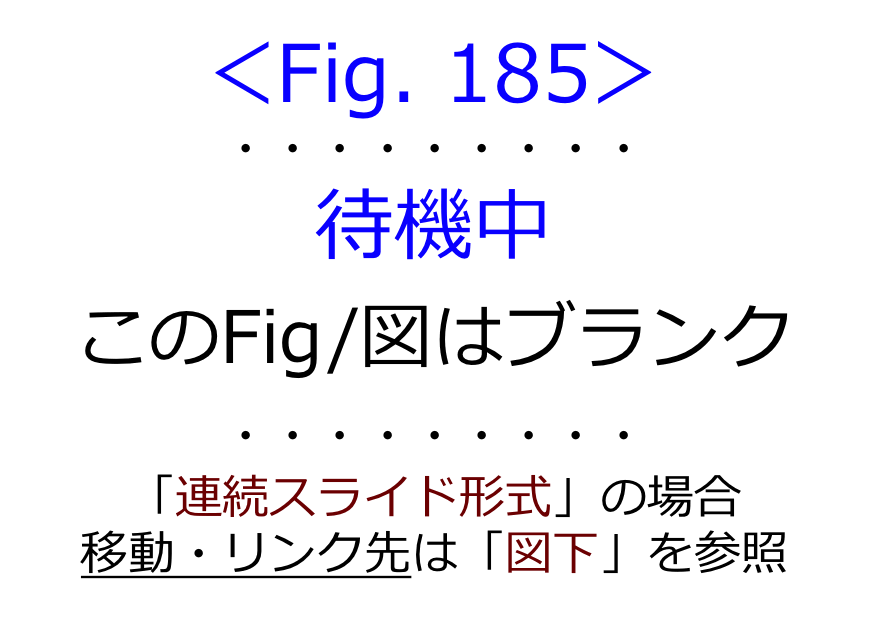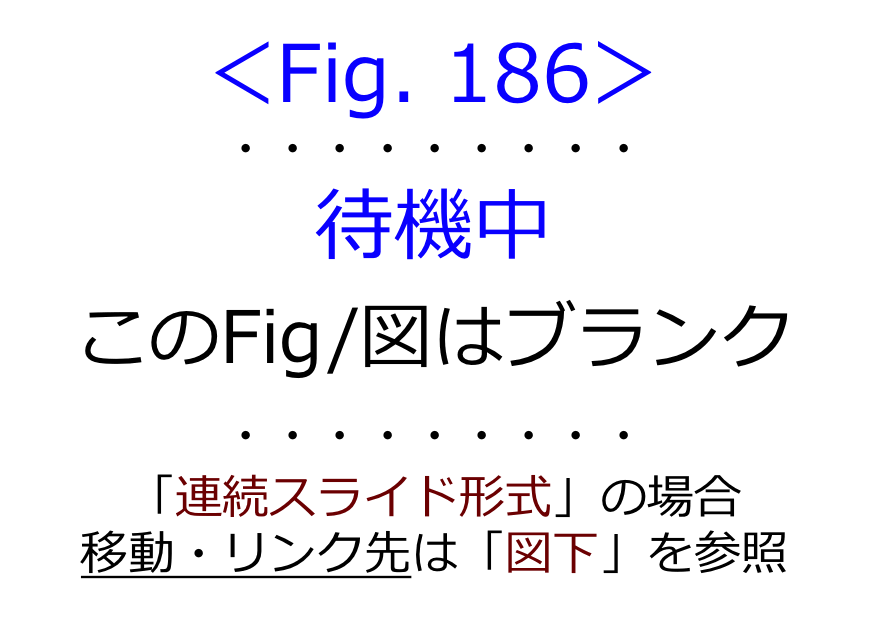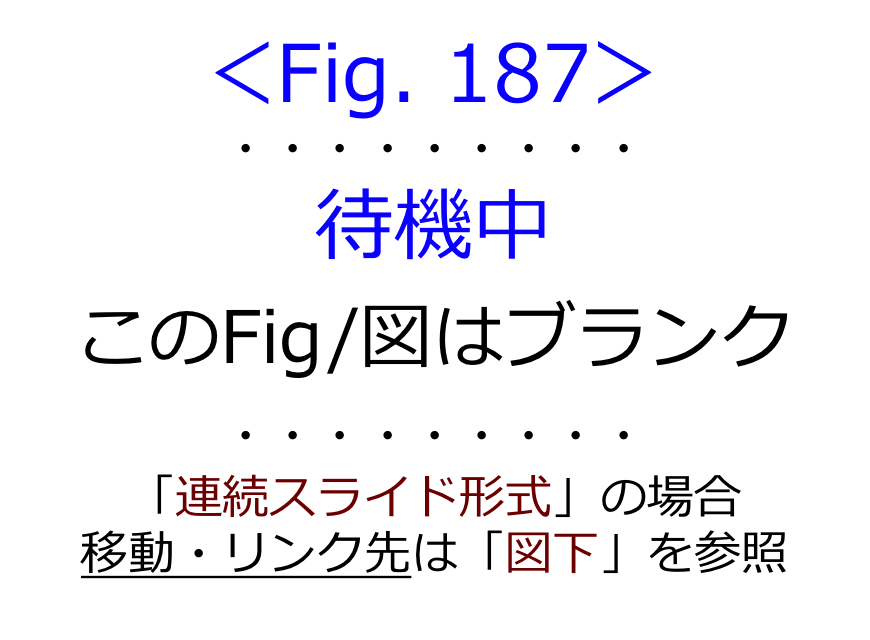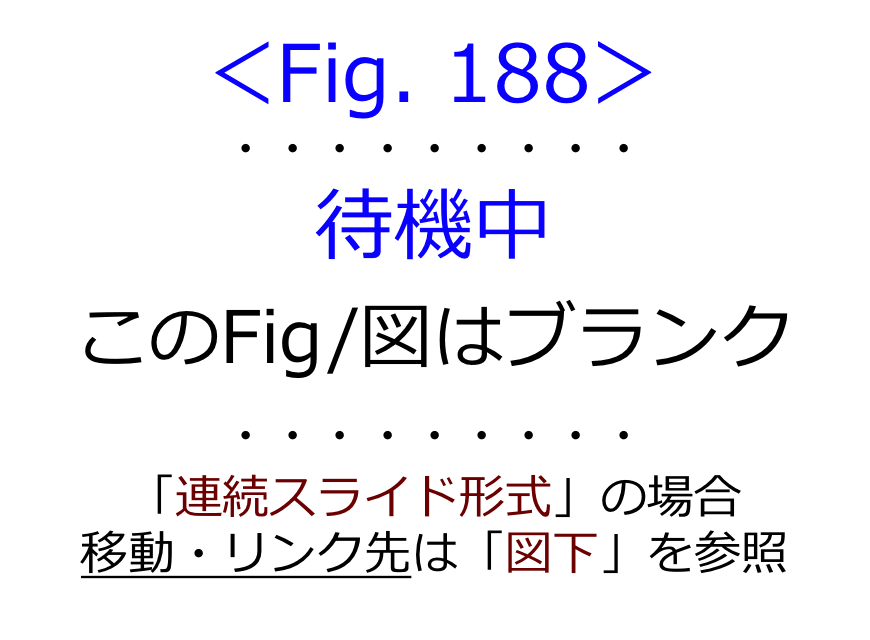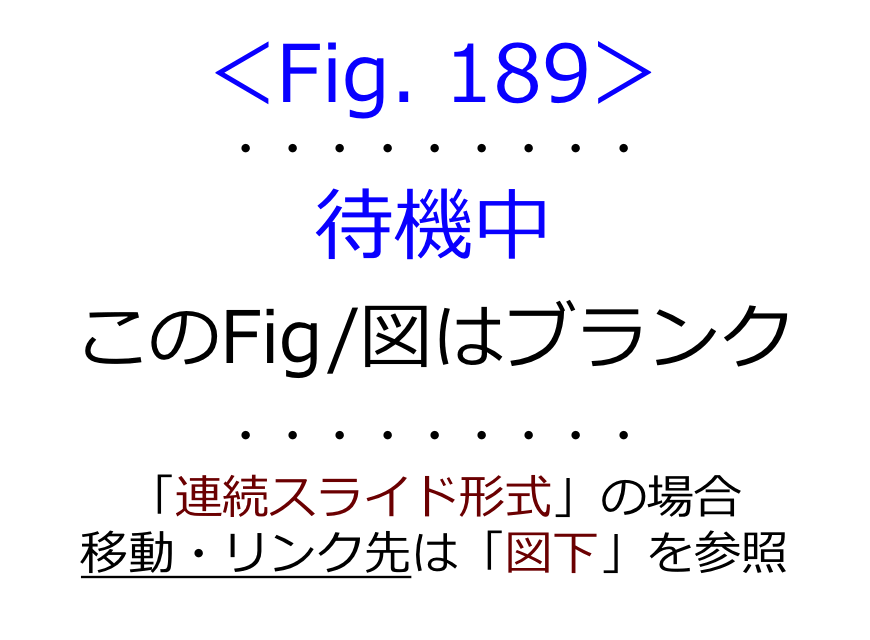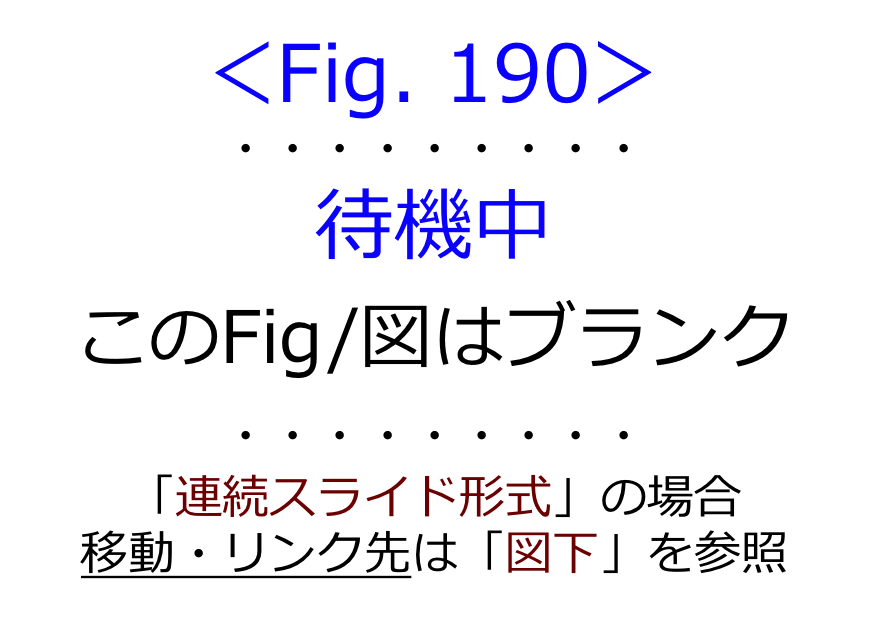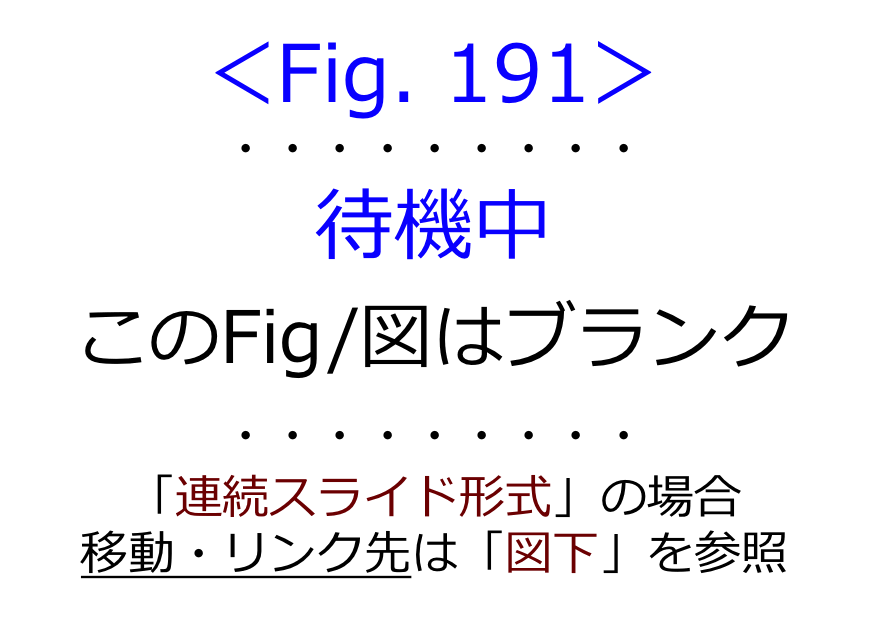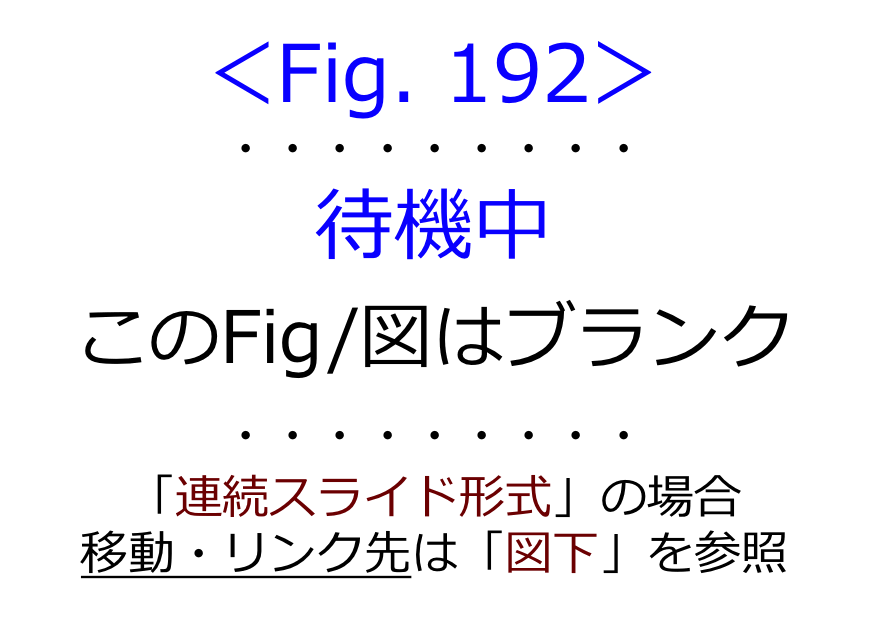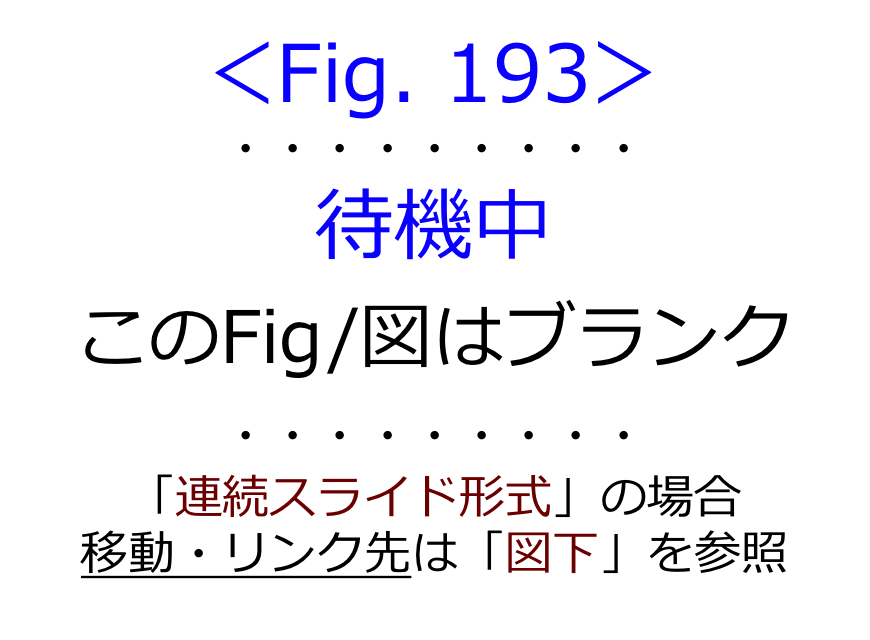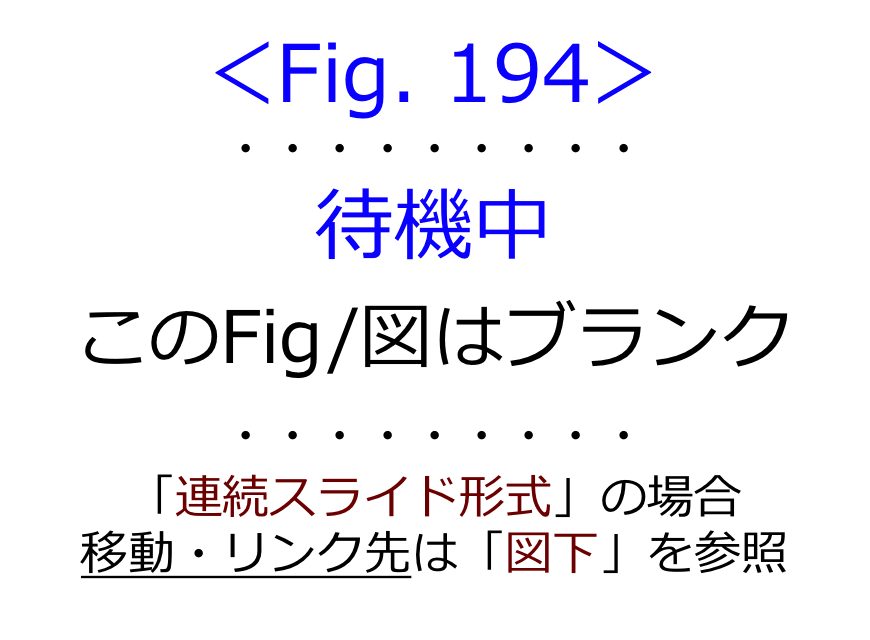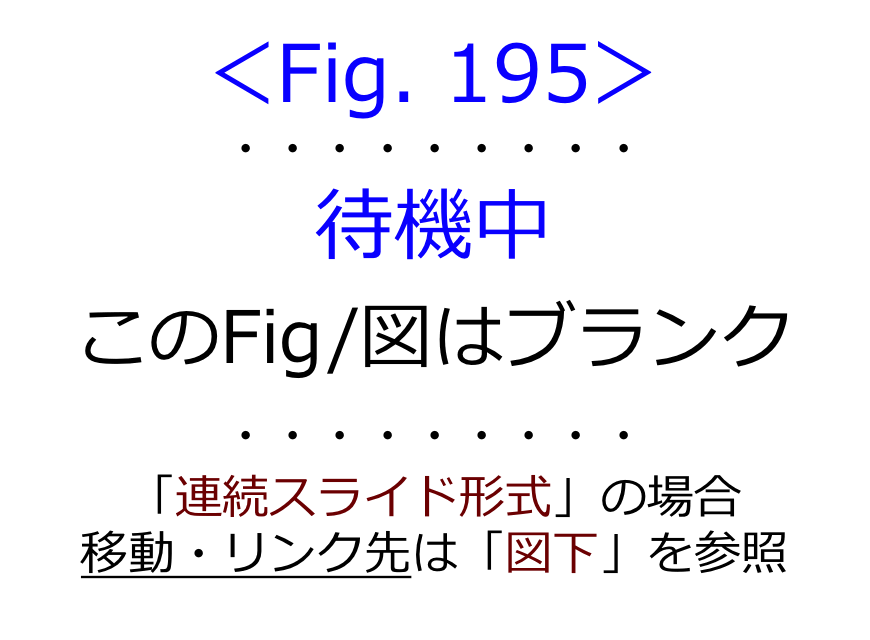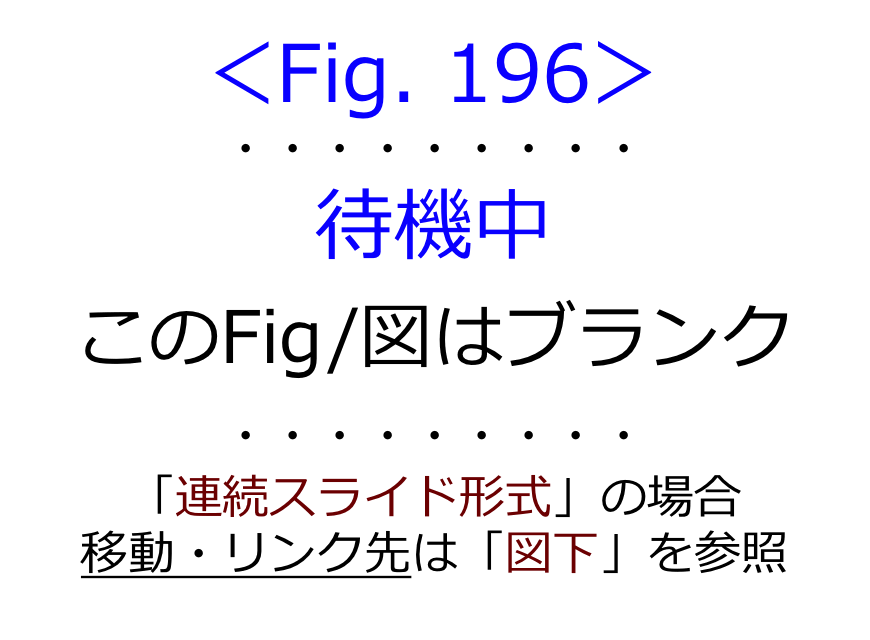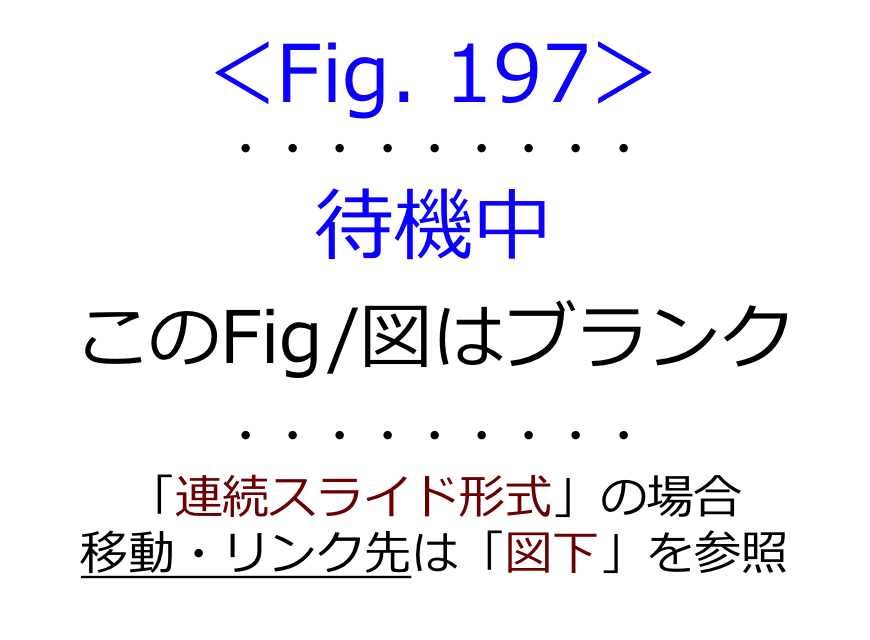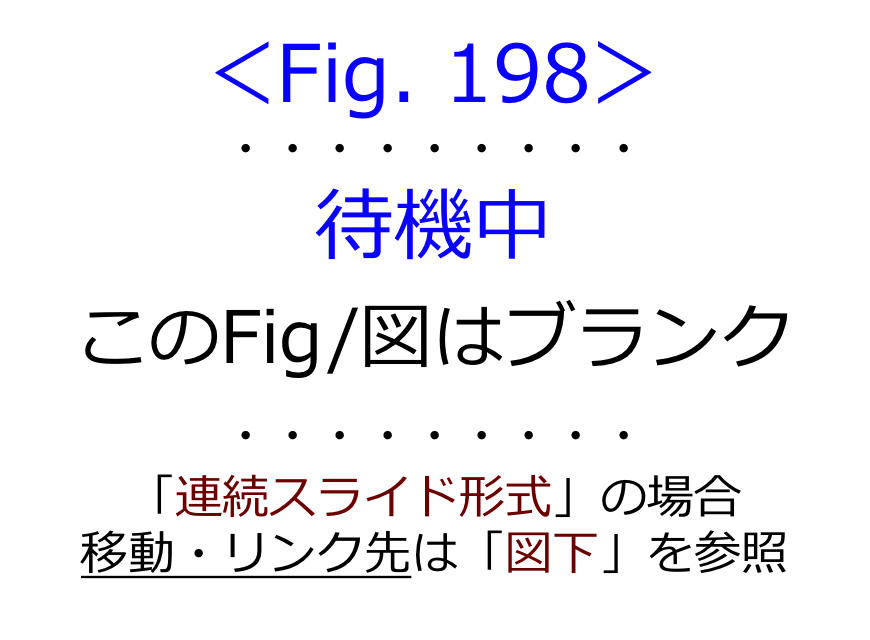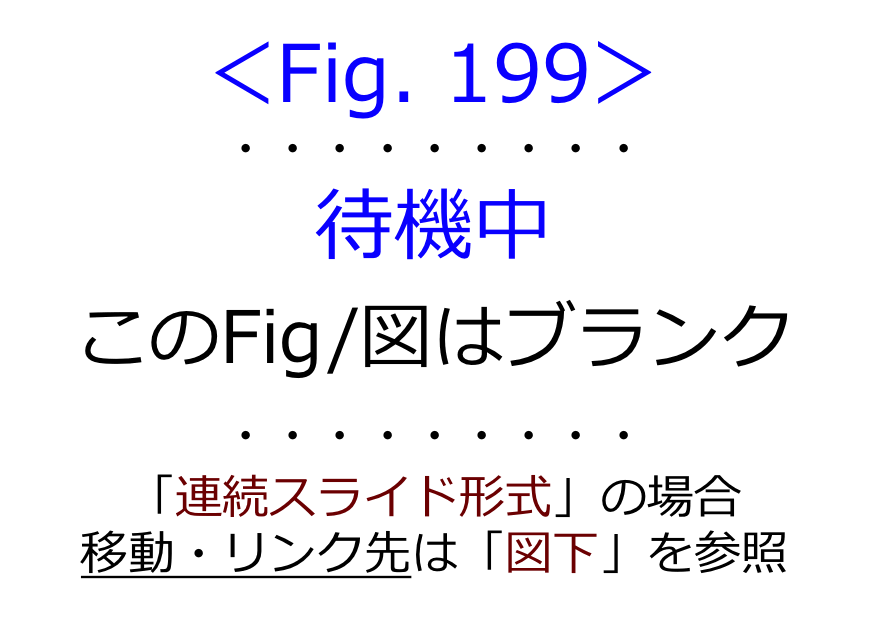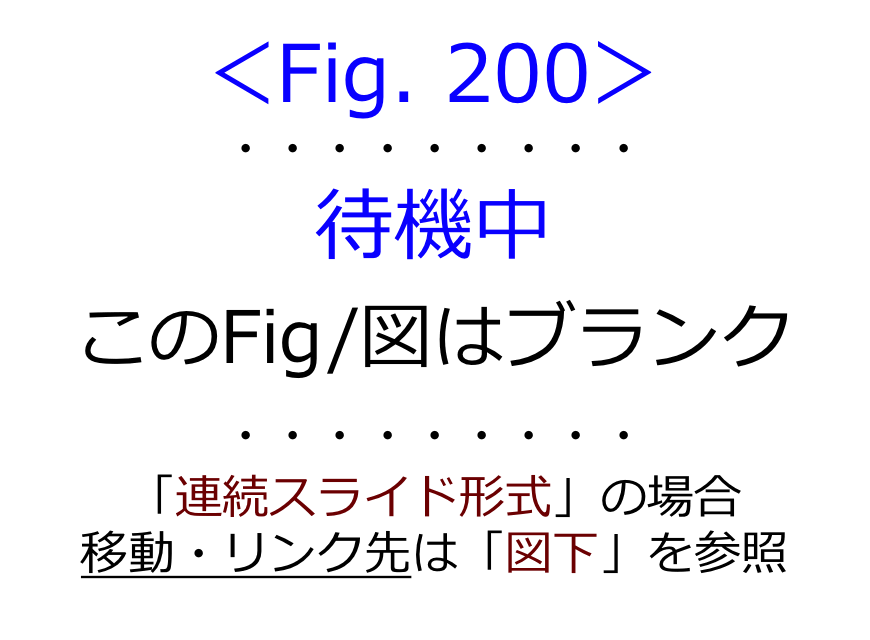<自然誌探求:魚類骨パズル実験学習 Top>
命題・原理・実証に基づく自然誌探求
なに・なぜ・どうして・どのようにして:それ本当?
<このシートは骨格系/骨パズルです>
その実験観察4区分へ移動/このPage
・・・・・・・・・・・食育知育 骨パズルへはココをタップ
海辺で拾った「この骨なに?」へはココ
板張り自然誌アートを見ながら
試して欲しいこと・考えて欲しいこと
(その「要 約」:ご意見大歓迎です)
<自然誌探求その他の関連サイトは次>
|
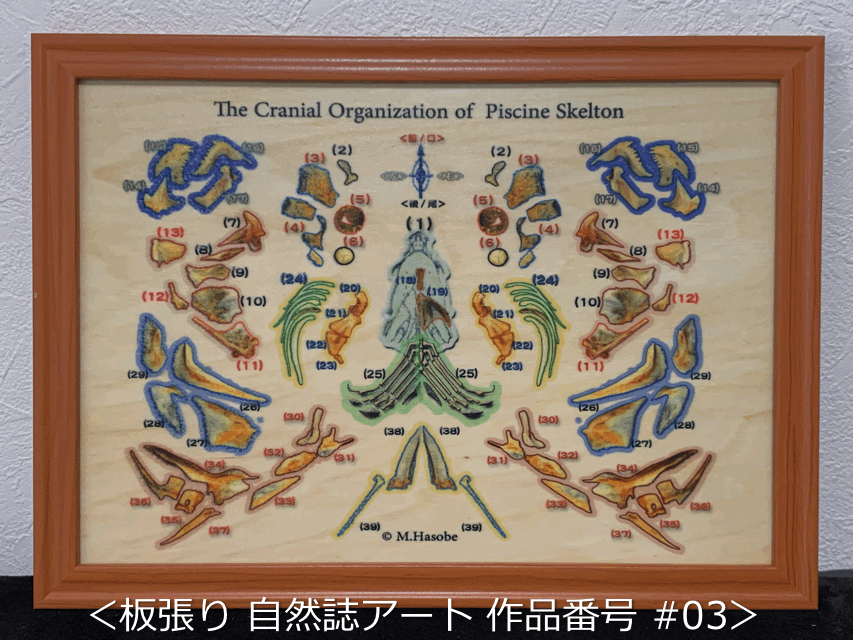 |
 |
(F.実験学習Topへ戻る:ココをクリック) |
|
(自然誌学習って何?/役に立つの?)
・・・実体と概念の連立連携とは・・・
| 魚類骨格系の見方/考え方(講義:スライド解説へ) |
| 自然誌アート Gallery へ (古代色"PISCINE"スケルトン作品一覧へ) |
| (少し付録-2:生物学習の深掘り PDF印刷テキスト) |
<魚類「頭部骨格系」の見方・考え方・進め方>
魚類骨パズル4実験:探求学習
(パズル/クイズ:試してね!)
コツ
コツ
A.立体
3D配置B.9区分
構造C.重層
摘出法D.展開
骨解説な に な ぜ どうして どのよう
にしてそれ本当? 下の〔移動〕をタップで上図サイトへ移動 スマホ 〔移動〕 〔移動〕 〔移動〕 〔移動〕
PC 〔移動〕
〔移動〕 〔移動〕 〔移動〕 (食育知育 マダイ頭部骨格の検索 パネルへ)
(魚類マクロ組織観察の場合はココ/タップで移動)
自然誌探求 プロトコール:骨パズルの巻
(左イメージの上をタップで実践サイトへ移動)〔1. これ なに?〕
・・・・導入・起点:イメージの共有<介在性学用品/自然誌アート>
・飾って/眺めて/触って/これ何?
・とりあえず3Dで確かめてみよう!
・スマフォで気軽にデジタル実験!〔2. なぜ こんな形なの?〕
・・・・命題:構造とは!<A.立体 3D>
・立体とは「構造と空間認識」
・ゲーム感覚で「繋がり」の確認
・でも「立体」って何故か・・だね!〔講義/解説〕 それでともかく
・魚類骨格系に関わる基本学習:講義〔3. どうして 9区分なの?〕
・・・・原理:仕組みとは?<B.構造9区分>
・複雑でも構造9区分はスッキリ!
・要素の配置とその繋がりだね
・実際に確かめてみたいね!
〔4. どのようにして 作ったの?〕
・・・・実証1:手順概要<C.重層状態:摘出順>
・その前に取り出し順を試してみよう
・デジタルシミュレーションだよ!
・なるほどね/楽しいね/本当かな?〔5. それ本当?〕
・・・・実証2:実践/実技実験実験とはともかく何かを確かめること・あなたは何が知りたい/確かめたい?(構造に基づき要素の配置とその繋がりを確かめる!)
<D.全展開図:実技実験法>
・テキストに従い試してみよう!
・自然誌探求・身近なチャレンジ
・実体と概念の連立連携だよ!では、次は、何をしようか!?
でも、なんとなく「モヤモヤ」を感じるね!
きっと「自然誌フィールド学習」の必要性!要約:つまり「学習フィールドはどこにあるのか?」ってことかな!?。通常のフィールドは「野外やスポーツ会場など:探求やトレーニングの場」を意味しますが、習う知識確認などの場でも学習フィールドのはず。つまり、学習の場(学習の枠組み)は身近なところにもあるというのが「生物学習」の本質です(我々は常に自然の一部であり、その学習の場は「実体と概念の連立連携」から成り立っています)。
それで、教室に限らず、自然誌学習/生物学習は「現実実体の枠組み:2系6要素」に従い、同時に、身近な人との話し合いを必要とします(共存共学の必要性)。
その目的は「なに・なぜ・どうして・どのようにして:それ本当?」という話題を、改めて段階的に確認し、前向きに取り組み共有するため。その近道として、とりあえず、自分自身で気軽にチャレンジ、身近な自然誌探求「骨パズル」を試してみることも有意義であろうと思っています。
つまり、「実体」が示すイメージを「構造から考える・それなりに納得する」という経験値は、空論ではなく、話し合いの確かな枠組みを提供します(生物学習の本質:観察的な視点を分析的な視点へ変換すること)。
そのためには、プロトコール /PCL(多くが納得する間違いが生じない取り決めや手順)も必要ですが、その主体的な取り組みこそ自然誌フィールド学習の意味意義と思っています。なお、「全てを求める」のではなく、段階的な取り組み/話し合いとしての対応が大切です。
従って、例えば、煮魚・潮汁の後には、お料理提供の方にお願い/了承を得て「骨パズル実験」を試してみることも自然誌探求学習です。つまり、科学実験の基本5ステップ「計画・事前準備・実践・記録・事後処理」に基づく構造解析(観察評価)と、時間があれば、成果公表(自己評価/自己表現/アサーション)に向かうはずです。なお「仮説」は使うもので立てるものではありません。
例えば、アジ・マダイ・スズキ・マグロ・トラウトなら手軽な材料。頭部骨格系の額縁標本(骨格系の展開配置標本)ならアジでチャレンジ。スズキやブリなら立体標本(サブサイト:自然誌ギャラリーあるいは自然誌アートGalleryも見てね!)、マグロ頭部なら「自然誌工芸品」にもなるよ!。作り方は「D.展開図」のサイトを参照です。
自然誌学習/生物学習は、些細な「はじめの一歩」で扉が開きます(それらは偏差値学習では開きません)。バランスの取れた教師やフィールドの必要性ですが、自然誌は多義に渡り無理もあるので、自分自身で確かめることも有意義と思っています。その経験値は確かに「読解力の志向」へ向かいます。試してください(つまり、なに・なぜ・どうして・どのようにして・それ本当?って段取りを思い出し考えてみること:自己分析能力の平易なトレーニング)。それらは、正否・優劣・知識レベルに関わりなく、誰もが共有可能な「共存共学の枠組み」を形成します。つまり、普通の話ですが、楽しげな前向な発展的な学習の場を提供します。
なお、「骨パズル」だけでなく、もう少し「自然誌生物学」の道筋を試してみたい方は、上記の「魚類マクロ組織のデジタル顕微鏡観察」や印刷用テキスト(PDF)などで深掘りしてください。それらは、つまり、階層構造レベル「個体・器官/組織・細胞」なので、同時に、動物細胞の形や運動性の顕微鏡観察も進めてください。もちろん、いわゆるフィールド学習(生態系という階層性)のことも気に留めて欲しいと思っています。
<E.骨パズルの発展/展開>
・階層構造性に従ってみよう!
・例えば組織の見方/考え方かな!
・でも器官や細胞も気になるね!
自然誌生物学の視座視点は「階層性」を基軸に成り立っています。複雑なこともその視座視点の学びがあればシンプルな扱いになるはずです。それで、例えば、体内構造を俯瞰する「魚類マクロ組織のデジタル顕微鏡観察」も試してください(上図をタップで移動します)。
少し難しいですが、その上位や下位の構造レベルの学びを導入すればスマフォで気軽に考えてみようとなるはずです。その目的は「これ何?」という主体的な扉を大切に「なるほどね」への道筋を確認すること。
その道筋には納得できる「見方・考え方・進め方」があるはずです。学習の場の経験値がその礎です。あるいは、実演生物学とそのプロトコール(解剖実験プロトコールなども含め「ログインサイト:実験学習」で確認してください)。
補足:自宅の庭や自然公園に加え、動物園・水族館・博物館・科学館なども大切な自然誌学習フィールドですが、その構成は「持ち主の好み」で表現/表象されています。それでも「自然誌の構造」から改めて観察してみる/分析してみると新たな発見や多様な学習フィールドの扉に満ちているはずです。それらは各々が身につけた経験値に基づき開かれた扉ですが、生物教師らの適切な支えも必要ではなかと思っています。
・・・・骨パズル自然誌PCL/選択へ戻る・・・・
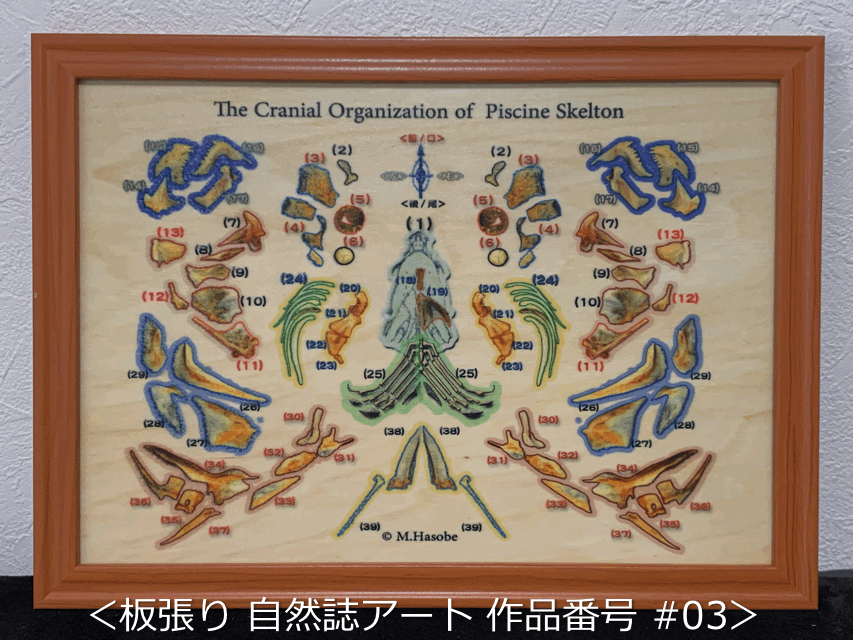
骨パズル・デジタル実験・自然誌生物学
上図はサカナの「頭部骨格系の全展開図」です。平面から立体やその構造を「考える」に適した「介在性学用品」と思って制作してみました。その目的は、構造と空間認識の試みです。平易に言えば「クイズ擬きの自然誌学習」ですが、その本質は読解力です(上表のA,B,C のデジタル実験学習を通じて試して下さい:質問はいつでもウェルカムです)。
ところで、サカナの頭部骨格系が30以上もの骨でできていると確かに複雑ですよね。しかし、少しインチキ臭い問いですが、ヒトの頭蓋骨(新生児の場合)でも40くらいあるって本当って思えますか?。つまり、多い少ないや優劣で物を扱うと戸惑いも生じますが、その戸惑いを感じるようなサカナの骨でも、その成り立ちは自然な「構造の見方・考え方・進め方」で成り立っています。日常的には役立たないかもしれませんが、イメージに囚われることなく、観察的な視点と分析的な視点の両面から段階的に少しづつ考えることも大切な経験値です。その経験値は多方面へ向かう手がかり/ヒントになるはずと思っています(構造なのでプログラミングと同じですよね!)。
つまり、自然誌学習は人に不可欠な学びの基本です。サカナは「食べてよし・釣ってよし・愛でてよし」の3拍子付きの身近な生き物ですが、自然誌の学びに深く関わる貴重な実体です。いつか、煮魚や潮汁などを食した後には「骨パズル」を試して下さい。きっと、自然/本質が見えてくるはずです。それでそのため、デジタル実験学習の前に「板張り自然誌アート:介在性学習品」を眺めることも有効かもしれないと思っています。さらに、そのことを話し合える学習の場があるといいですよ。
そのポイントはプロセスです。その目的は「不思議だね・なるほどね・考えるって楽しいね」から段階的に広がる幾つもの「自主学習の扉」が開くことと思っています。自主的な学びを俯瞰するにはその起点が必要ですが、板張り学用品がそのヒントになればと思っています。なお、専門用語は後追いするものです。覚える前に「なに・なぜ・どうして・どのようにして:それ本当?」って思って下さい。考えていると「時間や用語」は付いてくるはず、と思っています。試して下さい。補足:上図の番号は1〜39ですが、全てが左右対称の対骨ではないですが、単純には頭蓋骨は70前後です。従ってヒト頭蓋骨が40程度でもかなり多いですよね。しかし、エラやエラ蓋に関わる骨を除くとそれなりにヒト頭蓋とほぼ同じになります。いい加減な文章表現でした。すいませんが謎掛け生物学なので「あれ?」と思ってくれたら大正解です。ただし、正否や知識レベルに捉われないことが自然誌生物学の道筋ですよ。
<上図は自然誌学習フィールドの事例>人は「衣・食・住」に基づき「投資・消費・浪費の選択」で日常や文化を形成します。「衣」とは「どんな装いをしたいのか?」ですが、衣服だけの話でなく、「どんな学びの経験値で自分自身を表現したいか」ということも含まれます。いろいろあると思いますが、自然誌学習は以上の全てに関わる大切な学びと思っています。
デジタル学習は便利ですが臨場感も必要です。例えば、里山に隣接するフィッシングフィールドでもそのことが実感できます。例えば里山やフィッシングが成り立つ構造(要素の配置とその繋がり)を考えることは複雑ですが「身近な探求学習」であると思っています。「平和に疲弊する美しい日本にはしたくない」と思っています。今後は「消費型学習から持続型学習への投資」の時代であろうと思っています。如何でしょうか?
| <下図は骨パズルに関わる基本講義のスライドです> | |||||
| Fig. 0 | Fig. 1 | Fig. 5 | Fig.10 | Fig.15 | Fig.20 |
| Fig.25 | Fig.30 | Fig.35 | Fig.40 | Fig.45 | Fig.50 |
| Fig.55 | Fig.60 | Fig.65 | Fig.70 | Fig.75 | Fig.80 |
| Fig.85 | Fig.90 | Fig.95 | Fig.100 | Fig.105 | Fig.110 |
| Fig.115 | Fig.120 | Fig.125 | Fig.130 | Fig.135 | Fig.140 |
| Fig.145 | Fig.150 | Fig.155 | Fig.160 | Fig.165 | Fig.170 |
| Fig.175 | Fig.180 | Fig.185 | Fig.190 | Fig.195 | Fig.200 |
| ・< 先頭行へ ・ 「はじめに」へ ・ 「目 次」へ >・ | |||||
<下図は骨パズルに関わる基本講義のスライドです>
< Fig.0ーFig.0000 はその主イメージです>
| Fig.0 | Fig.00 |
| Fig.000 | Fig.0000 |
| Fig. 0-0000, は、本編の主要なイメージなどです。 (上図をクリックで拡大表示:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次>・<はじめに> |
|
<*-*>
| Fig.01 | Fig.02 | Fig.03 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.04 | Fig.05 | Fig.06 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.07 | Fig.08 | Fig.09 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.10 | Fig.11 | Fig.12 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.13 | Fig.14 | Fig.15 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.16 | Fig.17 | Fig.18 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.19 | Fig.20 | Fig.21 |
| (上図/画像の上をクリックで拡大表示:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先(上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.22 | Fig.23 | Fig.24 |
| (上図/画像の上をクリックで拡大表示:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<スマフォ形式へ>・<目次>・<はじめに>・<関連サイト一覧> |
||
<*-*>
| Fig.25 | Fig.26 | Fig.27 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.28 | Fig.29 | Fig.30 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.31 | Fig.32 | Fig.33 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.34 | Fig.35 | Fig.36 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.37 | Fig.38 | Fig.39 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.40 | Fig.41 | Fig.42 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.43 | Fig.44 | Fig.45 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.46 | Fig.47 | Fig.48 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.49 | Fig.50 | Fig.51 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.52 | Fig.53 | Fig.54 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.55 | Fig.56 | Fig.57 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.58 | Fig.59 | Fig.60 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.61 | Fig.62 | Fig.63 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.64 | Fig.65 | Fig.66 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.67 | Fig.68 | Fig.69 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.70 | Fig.71 | Fig.72 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.73 | Fig.74 | Fig.75 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.76 | Fig.77 | Fig.78 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.79 | Fig.80 | Fig.81 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.82 | Fig.83 | Fig.84 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.85 | Fig.86 | Fig.87 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.88 | Fig.89 | Fig.90 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.91 | Fig.92 | Fig.93 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.94 | Fig.95 | Fig.96 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.97 | Fig.98 | Fig.99 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.100 | Fig.101 | Fig.102 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.103 | Fig.104 | Fig.105 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.106 | Fig.107 | Fig.108 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.109 | Fig.110 | Fig.111 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.112 | Fig.113 | Fig.114 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.115 | Fig.116 | Fig.117 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.118 | Fig.119 | Fig.120 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.121 | Fig.122 | Fig.123 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.124 | Fig.125 | Fig.126 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.127 | Fig.128 | Fig.129 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.130 | Fig.131 | Fig.132 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.133 | Fig.134 | Fig.135 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.136 | Fig.137 | Fig.138 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.139 | Fig.140 | Fig.141 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.142 | Fig.143 | Fig.144 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.145 | Fig.146 | Fig.147 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.148 | Fig.149 | Fig.150 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.151 | Fig.152 | Fig.153 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.154 | Fig.155 | Fig.156 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.157 | Fig.158 | Fig.159 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.160 | Fig.161 | Fig.162 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.163 | Fig.164 | Fig.165 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.166 | Fig.167 | Fig.168 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.169 | Fig.170 | Fig.171 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.172 | Fig.173 | Fig.174 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.175 | Fig.175 | Fig.177 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.178 | Fig.179 | Fig.180 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.181 | Fig.182 | Fig.183 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.184 | Fig.185 | Fig.186 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.187 | Fig.188 | Fig.189 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.190 | Fig.191 | Fig.192 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.193 | Fig.194 | Fig.195 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
| Fig.196 | Fig.197 | Fig.198 |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
<*-*>
・・・・・・・・ |
||
| Fig.199 | Fig.200 | Fig.XX |
| (上図をクリックで拡大スライド:ここに戻る時は「テキスト形式」をクリック) <先頭行へ>・<目次へ>・<はじめに> |
||
この続きは「目次」に基づき移動してください。